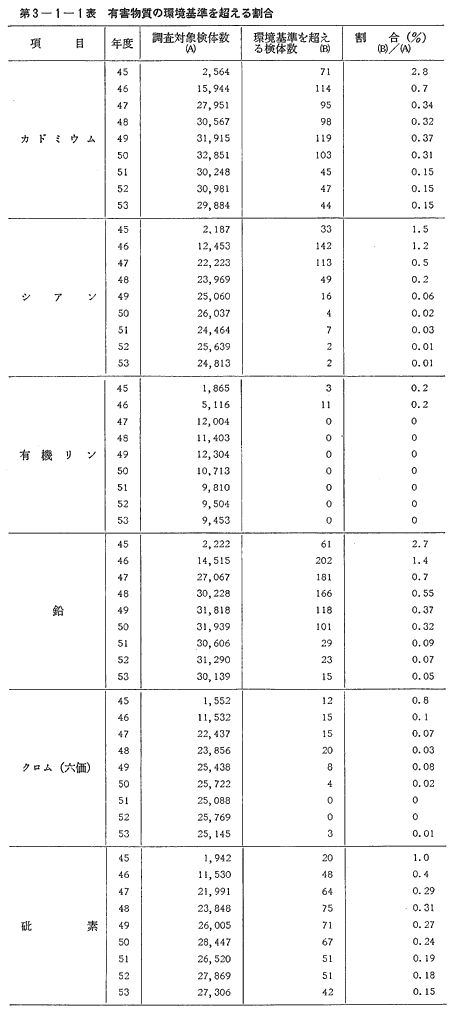
1 現況
最近における我が国の水質汚濁の状況は、総体的には改善の傾向が見られるが、望ましい水質環境に達していない水域も数多く残されている。昭和53年度全国公共用水域水質測定結果によると、カドミウム等の人の健康にとって有害な物質については、その環境基準値を超える検体数の調査総検体数に対する割合は、45年度に1.4%であったものが年々減少し、53年度には0.07%と大幅に改善されている。特に、総水銀については環境基準を超えると認められる地点はなく、アルキル水銀及び有機リンについては前年度に引き続き1検体も検出されなかった(第3-1-1表)。
一方、BOD、COD等の生活環境の保全に関する項目に関しては、昭和52年度までに環境基準類型のあてはめられた2,814水域(河川2,199、湖沼93、海域522)について、代表的な水質指標であるBOD(又はCOD)の環境基準の達成状況をみると、1,737水域(河川1,309、湖沼35、海域393)と全体の61.7%(前年度61.2%)が達成されており、水域別では、河川59.5%(58.5%)、湖沼37.6%(35.2%)、海域75.3%(76.9%)であり、依然として全体で38.3%の水域においては、環境基準が達成されていない。
これら水域には未だ環境基準の達成期間を経過していない水域も含まれているが、既に達成期間を経過している水域として昭和48年度までに類型があてはめられた水域のうち達成期間「イ」及び「ロ」の水域をとってみても環境基準の達成率は、67.1%と環境基準を達成していない水域が多く残されており、今後水質保全行政の一層の推進を図る必要がある。
次に、主要公共用水域のうち97か所における平均水質(BOD又はCOD)について41年頃から54年までの長期的推移を見ると、46年以前に水質汚濁のピークがあり、その後、改善の傾向を示しているものが多く全国的に見れば、最近の排水規制の強化等を反映し、水質汚濁の状況は総体的には改善されつつあるが、最近3か年の推移を見ると、全般的には横ばいの傾向が見られる(第3-1-3図、第3-1-4図及び参考資料21)
なお、その他の水質汚濁の態様としては、一時的な油等の流出による公共用水域の汚濁、一部の水域についてではあるが、ダムの築造に伴う長期濁水、火山地帯における河川又は湖沼の自然的要因による酸性化、大規模発電所の温排水による環境への影響等の問題がある。