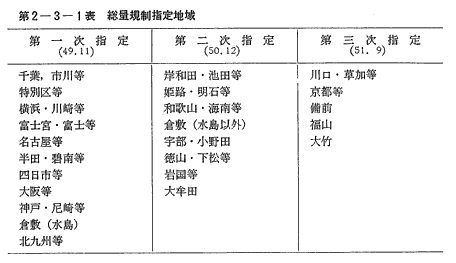
1 硫黄酸化物対策
(1) 硫黄酸化物の発生源
ばい煙中の硫黄酸化物は、硫黄分を含有する燃料又は原材料の燃焼によって発生する。例えば、重油中には平均1.4%程度(昭和53年度)の硫黄が含まれており、この硫黄が燃焼によって酸化されて硫黄酸化物、主に二酸化硫黄となるものである。
(2) 規制の方法
硫黄酸化物の排出規制は、施設単位に排出基準を定める方法を中心として、高汚染地域に対しては更に工場単位に総量規制基準を定める方法が併用されている。
この他、暖房等の中小煙源のために季節的な高濃度汚染を生ずる地域のばい煙発生施設及び総量規制指定地域にあって総量規制基準が適用されない小規模工場・事業場に対しては、石油系燃料の硫黄含有率に係る燃料使用基準を定めることにより、硫黄酸化物対策に万全を期している。
(3) 排出基準
施設単位の排出基準はK値規制と呼ばれ、排出口の高さに応じて排出量の許容量が定められる。
Q=K×10
-3
×He
2
Q:硫黄酸化物の許容排出量
K:地域ごとに定められる定数(3.0〜17.5の16ランク)
He:有効煙突高(煙突実高+煙上昇高)
K値規制は、Kの値が小さい程厳しい基準となる。二酸化硫黄の環境基準の達成を目標として、Kの値は、43年12月(第1次規制)以後51年9月(第8次規制)まで段階的に改定強化が行われてきたところである。
また、施設が集合し、高濃度汚染が生じるおそれのある地域にあっては、新設施設については特別のKの値(1.17〜2.34の3ランク)が定められている。
(4) 総量規制基準及び総量規制指定地域における燃料使用基準
工場又は事業場が集合している地域で、施設単位の排出基準のみによっては大気環境基準を確保することが困難である地域については、国が総量規制指定地域として指定を行い、都道府県知事が総量削減計画を作成し、一定規模以上の特定工場等に対しては総量規制基準を、特定工場等以外の工場等に対しては燃料使用基準を定めることとしている。
硫黄酸化物に係る総量規制方式は、電子計算機等を利用する拡散理論計算又は風洞実験により汚染予測を行って排出量と環境濃度とを対照させ、大気環境基準を満足するよう地域全体の排出総量を削減するための総量削減計画を作成し、その計画に基づいて総量規制基準及び燃料使用基準を位置づけようとするものである。
総量規制指定地域としては24地域が指定され、すべての指定地域において、53年5月末にはこれら規制基準が全面適用された。なお、総量規制指定地域については、第2-3-1表、総量規制基準、総量削減計画についてはそれぞれ、参考資料15及び参考資料16のとおりである。
(5) 硫黄酸化物発生源対策の状況
硫黄酸化物の排出規制に対応する発生源対策として、?輸入燃料の低硫黄化 ?重油の脱硫 ?排煙脱硫等の対策が講じられてきている。
?輸入燃料の低硫黄化については、LNG、LPG等の硫黄をほとんど含有しない燃料の輸入拡大を含め、我が国の一次エネルギー供給源の約7割を占める石油系燃料の低硫黄化が進められ、例えば、輸入原油の平均硫黄含有率は第2-3-2表のように低下傾向を示してきた。しかし、53年度はわずかに上昇した。
?重油脱硫については、42年度以来、直接脱硫、間接脱硫装置が建設され、53年度末の重油処理能力は、それぞれ11基6.7万kl/日、32基15.5万kl/日に達している。なお、重油脱硫能力の推移は第2-3-3図のとおりである。
このような原重油等の低硫黄化、重油脱硫等により、内需用重油の平均硫黄含有率は、42年度2.5%から53年度1.36%に低下、硫黄含有率1.0%未満の重油が占める割合は、42年度8.6%から53年度50.8%に上がってきている。硫黄分別に見た重油供給の推移と平均硫黄含有率の推移は、第2-3-4図のとおりである。
?排煙脱硫装置については、41年から通商産業省による大型工業技術研究開発として研究開発が進められ、45年から実用装置が稼動を始めたが、その後設置基数及び処理能力とも増大し、53年度末の排煙脱硫能力は1,357基、約134百万Nm
3
/hとなっている。年度別の排煙脱硫施設設置状況は、第2-3-5図のとおりである。
以上の諸対策により、SO2(二酸化硫黄)による大気汚染の状況は著しく改善された。
今後は、予想される輸入原油の重質化あるいは石炭利用の拡大等エネルギー事情の変化を見守りつつ、環境基準の維持・達成を図るべく、引き続き所要の対策を講じていく必要がある。