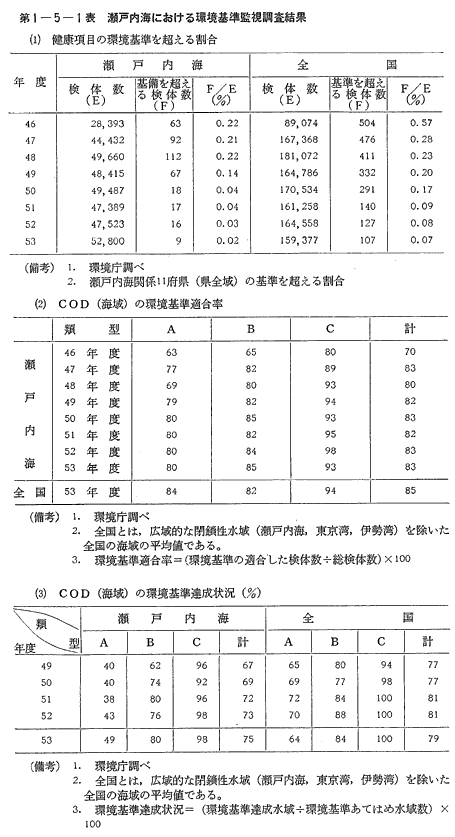
1 瀬戸内海の環境の現況
(1) 水質汚濁の現況
瀬戸内海の水質汚濁の状況を見ると、有害物質による汚染については、環境基準値を超えて検出される検体の割合は全国的にも減少傾向にあるが、瀬戸内海においては更に低い水準で推移し、53年度には0.02%となっている(第1-5-1(1)表
)。
有機汚濁の代表的指標であるCODに係る環境基準の達成状況(環境基準類型あてはめ水域数に対する達成水域の割合)については、53年度においては、A類型が40%、B類型が80%C類型が98%、全体で75%となっている。これを全国の値と比較してみると、海域の大部分を占めるA類型の達成状況が著しく低い(第1-5-1(3)表
)。
一方、瀬戸内海は、窒素、燐等の栄養塩類が流入するとともに、それが蓄積するといういわゆる富栄養化の傾向を示している。
また、赤潮はここ数年広域的に多発しており、54年には193件の発生が確認された(第1-5-3表)。これら赤潮の発生に伴う被害は、赤潮発生時における養殖魚の赤潮発生海域からの避難等の対策がとられたこともあり、大規模なものはなかった。
瀬戸内海における油による海洋汚染の発生件数は、47年の874件から53年には374件と大幅に減少しているものの、なお全国の約34%を占めている。
これらを総合すると、瀬戸内海における水質は、すう勢的には改善の方向にあると思われるが、なお、有機物による汚濁、富栄養化の進行等多くの問題を残しており、今後とも施策の徹底を図っていく必要がある。
(2) 海浜地の現況
瀬戸内海においては、人口及び産業の集中に伴う開発等により人工海岸が増加しており、全国的に見ても海岸の人工化の進んだ地域となっている。残された純自然海岸等自然海浜は、海水浴、潮干狩り等の海洋性レクリエーションの場として利用されてきたが、53年現在の利用状況を見ると、瀬戸内海全体で423箇所、利用者数の合計は約1,690万人である。利用者の形態を見ると、海水浴による利用が215箇所、潮干狩りが81箇所、複合利用が127箇所である。