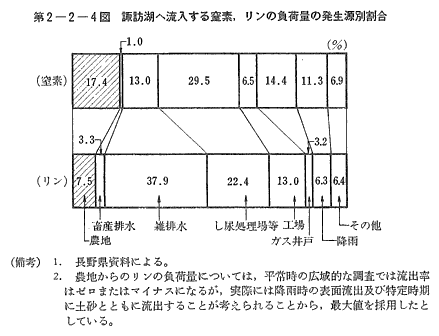
2 農林水産業による環境負荷
農林水産業は、基本的に自然の生産力にその生産の基礎を置きながらも、大規模な利水、ビニールハウスなどの施設栽培、化学肥料や農薬あるいは水産養殖業等技術開発によって農林水産業の生産性を向上させてきている。一方において、このようなことが環境負荷と生態系の受容量の間に新しい環境問題を生じさせることとなった。
1960年代後半から1970年代初頭にかけてそれによる環境汚染が世界的な問題となったDDT、BHC、ディルドリンなどの農薬は、農業生産の中に新たに持ち込まれた人口の化学物質である。これら有機塩素系農薬については、我が国では、46年に販売禁止や使用規制などの厳重な規制措置がとられた。このような例は農業においても、使用する化学物質がその環境中での特性により環境汚染を起こすことがあることを示している。
また、従来農地の生態系に存在していた物質であっても、環境への負荷となる場合もある。例えば、肥料に含まれる窒素、リンについては、肥料を一時に過剰に施用した場合には、その一部が農地から流出するという指摘もある(第2-2-4図)。なお、農作物、土壌の働きにより農地には窒素、リンを吸収、浄化する機能があることも知られており、水田では流入する用水の水質、降雨の状況などにもよるが、流入水よりも流出水の方が窒素、リンの濃度が低くなっているという事例もある。
また、我が国の畜産業は国民の畜産物の消費の拡大に支えられ、農業全体の中での相対的ウェイトを高めつつある。食肉類の消費量は、42年から52年の10年間に1人当たり年間10.8kgから20.3kgへと約2倍に増加した。この間、家畜の飼養頭羽数は、全国で肉用牛が1.3倍、豚が1.4倍、ブロイラーが3.3倍に増加し、このような畜産物生産の急速な拡大の中で、各畜産経営農家の経営規模の拡大が進行した(第2-2-5図)。
従来、家畜のふん尿は農地に肥料として還元されていたが、畜産経営の大規模化及び専業化により飼養頭羽数は増加し、ふん尿を還元すべき自己の農地を所有する畜産経営は減少傾向にあり、自己農地還元率は低下してきた(第2-2-6図)。
家畜のふん尿は、飼料の組成などによってかなりの変動があるが、BOD負荷量でみると人のし尿に比べ、牛、豚の一頭当たりのふん尿は、豚で人間の一人当たりし尿の約10倍、牛では約30倍の負荷があるとしている試算もあり、経営規模の拡大に伴って、ふん尿について所要の対策を講じているものの、一部に、水質汚濁の一因となっている例もみられる。
また、その処理は多大の費用を要し、畜産経営にとって大きな負担となっている。
このため、良質な有機質資材としての特性をもつ家畜ふん尿の活用を図る意味もあって近年家畜ふん尿の処理・流通のシステムを改善し、農地還元を促進するための施策が進められ、家畜ふん尿の農地還元率も最近においては上昇している。これは、かつて農業のなかで機能していた有機物の循環を新たな社会経済条件のもとで再構築し、農耕生産の環境保全機能を活かして行こうとする重要な動向である。