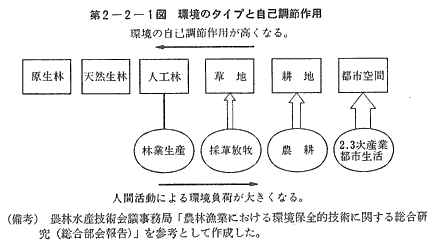
1 農林水産業の環境保全機能
人間の生存は環境の浄化、復元の働きによって支えられており、自然の大きな物質とエネルギーの循環系の生存の上に成り立っている。すなわち、人間の活動に伴って生ずる環境への諸々の負荷は、それが自然の受容可能な範囲であれば、自然界に存在する様々な物質やエネルギーの循環系のなかに吸収され、環境質は全体として安定的なものに保たれるのである。
このような生態系の自己調整作用による環境の浄化、復元の働きは、自然に人間が手を加えない地域ほど高いことが知られている。第2-2-1図は、生態系の自己調整作用の高さに従って、環境を序列化して示したものである。我が国においては、生態系の最も安定した状態は原生林であり、これから生態系が極度に人間によって単純化された都市に向かって生態系の自己調整作用は低下していき、人間活動による環境への負荷の増大とそれを受容する自然の機能との間のバランスが生じ易くなっているといえる。
今日の都市空間は、人間活動による生態系への負荷が集中する一方で生態系の自己調整作用が極端に低下している。そこにおいて環境の浄化能力を超えて発生した環境負荷は、大気汚染や水質汚濁となって都市域での環境汚染を引き起こしているだけではなく、都市空間を越えて都市を取り巻く農林水産業空間に環境負荷はオーバー・フローしている。
このような地域では、農林水産業はその生産活動を通じて、都市の環境を浄化してきているだけでなく、その水や土を保全する機能などによって都市の環境を支えているのである。
また、都市をとりまく緑の空間として、豊かな水辺として、農林水産業空間が都市住民にとって潤いのあるレクリエーション空間となっていることも、農林水産業の環境保全機能をみるときに無視し得ない機能である。
このような農林水産業の環境保全機能の働きとその変化を、いくつかの事例に即して、次にみていくこととしよう。
その一つは、森林のもつ公益的機能としての多面的環境保全機能である。我が国の国土面積約3,800万haのほぼ3分の2は森林であるが、これらの森林は、起伏が多くそれ故に水や土砂の急激な流出とそれに伴う災害の危険の多い我が国において、水を溜め、土壌を保持し人々の生活の基盤である水と国土を守っている。ゴルフ場や宅地などの開発によって森林が失われたことにより土砂崩れなどの災害が起こった例などは、この森林の働きを教えるものであろう。
また、我が国の自然公園の総面積の8割以上が森林であることなどからもうかがえるように、森林はそれ自体緑の空間として人々に豊かなレクリエーションの場を提供しているし、鳥獣など野生動物の生息の場となり、あるいは大気浄化、気象緩和などの機能を持つなど多面的な環境保全機能を持っている。また、農地においても森林と同様な水、土、大気等に係る環境保全機能を有することが知られている(第2-2-2図)。
その二つは、農業と廃棄物の関係である。かつて、我が国の農業は、農村の中で発生するし尿、家畜のふん尿、わらくず、残菜などをすべて農地に還元していたばかりでなく、近郊地域で排出されたし尿なども肥料として農地に受け入れていた。
第2-2-3図は、東京23区におけるくみとりし尿の農地への還元率の推移であるが、33年には、し尿33%が農地に還元されていたが、都市における下水処理の進展と軌を一にして、それが急速に低下してきたことがわかる。
その三つは、農村と水との関係である。かつては農業用水路は集落を含めた地域の排水路としての機能を有しており、また、そこに排出される生活排水も少なく、農村地域周辺の生活雑排水は水田等に流れ込み、そこで浄化された水が再び川に戻っていた。
このような農村と、その近郊地域における水や有機物の循環は水田に大きく依存し、形成されたものである。しかし、都市の拡大が進み、都市の生活排水は下水道などを通じて直接川や海に排出されるようになり、農業においても、生産技術や経営形態の高度化、近代化が進んだこともあって、水や有機物の循環も変化をとげた。
このような事例として、琵琶湖の湖畔にかつて広くひがっていた葦原の消長をみていくこととする。葦が「よしず」や「す戸」などの材料を提供し、周辺農家の人々の生活を支える大きな作目であった時代には、葦原のなかに通ずる水路にたまる汚泥は、田畑への肥料となり、また、近江特産の瓦を焼く土になっている。
この葦原は、湖際にあって琵琶湖に流入する種々の排水を受け入れてその養分で生長すると共に、これによって水を浄化して湖に引き渡す水の浄化機能を発揮していた。
このような自然の営みを活かした葦原を軸とした生産のシステムも、葦による製品がプラスチックその他の工業製品の出現によって取ってかわられ、一方で葦原の改変が進んだこともあって湖畔の葦原は減少し、大きなまとまりとしては近江八幡市の湖際など一部に残るだけとなっている。周辺の人々の経済活動の中からも切り離されかけ、葦原がかつて果たしていた水の浄化機能も忘れられようとしている。かつて生活と葦原が一体となって作り出していた豊かな葦原の景観も、葦原をめぐる人々の生活の変化の中で次第に失われようとしている。
その四つは、農林水産業の環境汚染を監視する機能である。農林水産業は油濁や赤潮による漁業被害やカドミウムなどの重金属などによる土壌汚染などの深刻な公害による被害を受けてきたことが知られている。
水、大気、土壌などを生産の基盤とする農林水産業は、その性格故に環境汚染の影響を受け易い。そのため、環境の変化に対して鈍感になった都市に対し、農林水産業とその従事者が環境悪化の警鐘ならし、それに歯止めをかけるという働きを果していることを見逃すことはできない。
環境汚染の影響は、農作物や魚介類に現れる。水俣沖や瀬戸内海あるいは東京湾において水質、底質の汚濁、汚染により魚相が変化したり、奇形の魚が生じたりしたことはよく知られているが、これらの変化に最初に気付き、またそれによって深刻な影響を蒙ったのは漁民であった、生物に現れる変化は、環境の悪化を総合的に反映し、未だ知られない汚染物質の危機や自然の生態系の大きな変化を示すものである。このような変化を受け止める農林水産業は、大きな環境汚染の監視機能を持つべきである。