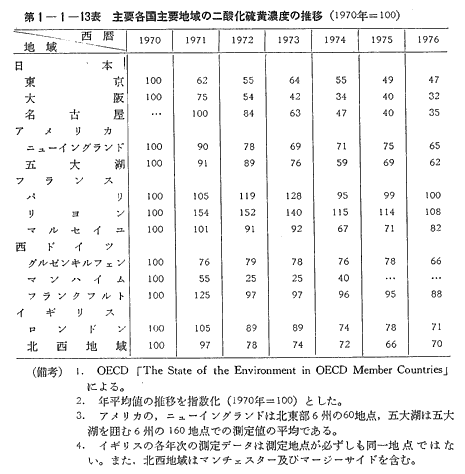
5 諸外国との比較
産業化の進行に伴い、経済社会活動が環境に与える負荷は質的に変化してきている。
1960年代になって、多くの先進工業国において環境問題が大きな政策課題としてクローズ・アップされてきており、その中で環境問題が先進国共通の政策課題であるという認識が強まり、1970年にはOECD(経済協力開発機構)に環境委員会が設置され、また環境問題の解決が先進国、発展途上国を通じた人類的な政策課題であるという認識も生まれ、1972年には国連人間環境会議が開催されるとともに、そこでの合意に基づき国連環境計画(UNEP)が国連機関として設置された。
先進国の経済問題の解決に主眼を置いているOECDが環境問題を取り上げるようになった背景として、OECDは、第1に先進工業国において環境問題が急激に大きな社会問題となってきていたが、環境の測定、分析に始まって政策の対応、考え方などがまだ未熟な段階で、その前進を図ることが各国に共通する緊急の政策課題となってきたこと、第2に環境問題は地球的規模の人口と資源のバランスなどの問題を含んでいたり、越境汚染が引き起こされたりする場合もあるなど国際性を持った問題であること、及び第3に環境規制のレベルのちがいなど各国の環境政策の対応のちがいが交易条件を変えこれが非関税障壁を生むこと、の3点をあげている。
我が国は上にあげたOECD、国連環境計画などの国際機関における環境問題の検討に参加しているほか、アメリカ、西ドイツ、EC(欧州共同体)などとの間でも相互の知見、情報の交換、専門家の交流等を行っている。
各国とも環境政策の歴史は新しく、環境汚染の発見、汚染物質の確定、汚染との因果関係の化学的解明、基準の設定、規制の体系の確立などを一層推進していく必要がある。世界の各国が、それぞれの環境問題の解決の前進をめざして、それぞれの経済、社会条件のちがいを認識しつつ、その知見と政策上の経験を相互に交換し合い国際的な協力活動を進めていくことは、環境政策の発展にとって有効なことである。
これまでの各国の環境政策の経験では、国によって産業や都市の構造、そして自然条件にも差があり、汚染のあらわれ方も違っている。また、生態系のなかでの人口の化学物質の挙動などを追跡することによって、被害が顕在化する前に汚染を防止するという事前の対応の必要性を強く意識している国もある。
ここでは、昨年5月に発表されたOECDの「OECD加盟国の環境の状況に関する報告書」などを活用して、主要先進工業国における大気汚染、水質汚濁及び騒音を中心とした公害の推移を追うことによって、このような諸外国における環境問題と我が国の特性を比較することにより、我が国の公害の現状認識を深めることとしたい。
(1) 大気汚染
主要先進工業国においても、我が国と同様大気汚染問題は、主要な公害問題の一つである。硫黄酸化物やばいじんによる汚染は、各国とも早くから問題となっていたため対策もかなりの進展を見せており汚染の改善も進んできているといえる。
先進諸国の主要地域での1970年から1975年の間の二酸化硫黄(SO
2
)の濃度の推移を第1-1-13表によってみると各地域ともピーク時に比べかなりの改善を示しており、特に我が国の都市における改善は著しいものがある。このような二酸化硫黄による大気汚染の改善の背景として、エネルギー消費単位当りの二酸化硫黄排出量の推移を第1-1-14図によってみると日本のエネルギー消費単位当りの二酸化硫黄排出量は、1970年にはアメリカ、西ドイツと並んでいたが、1975年には半分以下となりアメリカ、フランス、西ドイツの50%から60%、イギリスに対しては30%程度の排出量まで低下している。
我が国において二酸化硫黄による大気汚染の改善が進んだ理由としては、イギリスをはじめ欧米諸国ではエネルギーに占める石炭のウエイトが比較的高いのに対して、我が国では石油のウエイトが高く低硫黄原油の輸入、重油脱硫技術及び排煙脱硫技術の導入などの石油中心の公害防止対策が顕著な効果をあげたことなどがあげられよう。
一方、窒素酸化物の総排出量については、諸外国においても概してはかばかしい改善はみられていない。第1-1-15図は、主要国の窒素酸化物の総排出量の推移を1970年を基準としてそれぞれの国について示したものであるが、ほとんどの国で1975年の総排出量は1970年のそれを上回っている。
窒素酸化物と炭化水素に起因して発生する光化学オキシダントは我が国以外でもオーストラリア、カナダ南東部、アメリカなどで問題として認識されている。
光化学オキシダントの発生ひん度は気象条件によって年々大きく変動するため、はっきりとした傾向を探ることが難しい。しかしながら日本やアメリカのカリフォルニア州の都市などの地域では、光化学オキシダントの濃度が近年には減少傾向にあると考えられている。
(2) 水質汚濁
主要先進諸国における水質汚濁の状況を、いくつかの主要河川について、代表的な有機汚濁の指標であるBODの推移でみると、アメリカ、フランス、オランダ、スウェーデンなどの国の河川の有機汚濁については、改善もしくは横ばいの傾向がみられるが、なお、汚濁の進んでいる河川もある(第1-1-16図)。また、汚濁の改善がみられた河川のなかでもいまだ高いBOD濃度の河川があるなど、全体として目標とする水質の達成には一層の努力が必要と考えられる。
また、個別汚濁物質のなかでは、工場、事業場の排水に加え、都市排水や肥料の農地からの流出を主因とする窒素、リンなどの栄養塩類が水域の富栄養化と関連して問題とされている。エリー湖、オンタリオ湖、ジュネーブ湖など多くの湖沼では以前から水質の悪化が指摘され、近年対策の強化が図られている。
(3) 騒音
OECDは、加盟諸国において、騒音問題が人口と経済活動の高密度化及び自動車利用の増大と密接に関連して空間的、時間的に拡大しており、その主要な発生源は、運輸交通機関、特に自動車と航空機であるとしている。
道路交通騒音は、交通騒音のなかでも最も多くの人々に被害を与えている。OECDが行った主要先進国の1970年代中期における道路交通騒音にさらされている人口の体全人口比の推計によると、我が国においては、他の主要先進国に比較して、道路交通騒音にさらされている人口の割合が高いことが示されている。(第1-1-17図)。
OECDは、アメリカに比べヨーロッパ諸国で道路交通騒音にさらされている人口の割合が高いことの理由として、高密度の自動車利用、道路の狭小さなどをあげているが、我が国においても、第1-1-17図に示した市街地面積当たりの自動車保有台数にみるように国際的にみても高密度な自動車利用が行われており、これが道路交通騒音にさらされている全人口比の高い一因となっているものと考えられる。
道路交通による騒音問題は都市に集中しているが、交通量は人口密度に比例する傾向があるので、大都市においては一般的に中小都市に比較して騒音が高いレベルになっている。例えば、ロンドンとパリでは、平均的な都市に比べ約7デシベルほど騒音レベルが高くなっている例がOECDによって紹介されている。
航空機による騒音は、道路交通騒音に比較してその被害を受けている人数は少ないが、より高い騒音レベルに達するため局地的に大きな問題となっている。なお、航空機騒音にさらされている人口の対全人口比をOECDの推計によってみると、航空輸送の発達したアメリカでは他の地域に比較して多数の人口が航空機騒音にさらされていることが示されている(第1-1-18表)。
これらの交通騒音について、OECDは、今後とも交通量の増大と、都市の無秩序な拡大とにより増大していくものと予測するとともに、夜間交通や、週末および休日の活動の増加によって時間的にも拡大していく傾向にあり、騒音対策の適切な実施がなければ今後とも交通騒音の被害が増大すると指摘している。