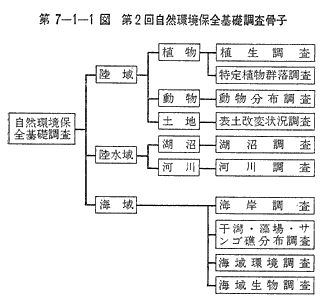
一部の都市部における緑化の減少をはじめとして、我が国における自然環境の変貌は最近著しいものがある。このように変貌していく自然環境を適切に保全するためにまず第一になすべきことは、自然環境の現状を的確には握し、その変化の方向を見すえることである。
このため、昭和48年度には「自然環境保全法」第5条に基づき第1回自然環境保全基礎調査を実施した。自然環境保全基礎調査は、我が国の自然環境の状況を、総合的、科学的には握するため、おおむね5年ごとに実施されるもので、一般に「緑の国勢調査」と呼ばれている。第1回調査に次いで、周到な計画のもとに53年度から第2回調査が開始された。まず、51年度より学識経験者で構成される検討会において調査項目、調査方法等が検討され、52年度末に調査要綱が策定された。その骨子は第7-1-1図のとおりである。このうち、53年度には4億228万円の予算で次の6項目の調査を実施し、残りの4項目の調査は54年度に、また、調査結果の集計解析は55年度に予定している。
(1) 特定植物群落調査
我が国における植物群落のうちで、原生林、湿原植物群落、高山植物群落、社寺林、武蔵野の雑木林のように郷土景観を代表する植物群落など、学術上重要なもの、保護を必要とするものなど全国で4,000を超える植物群落を選定し、その生育状況を調査した。
(2) 動物分布調査
我が国に生息する動物の生息状況をは握するための第一歩として、次の動物について分布域を調査した。
ア 哺乳類
シカ、クマ、ヒグマ、イノシシ、ニホンザル、キツネ、タヌキ、アナグマの8種の大型・中型哺乳類について、全国で1,600人を超える都道府県の鳥獣保護員・林務関係職員等の調査員が約5万人に対して面接による聞き込み調査を実施し、生息分布図を作成した。
イ 鳥類
我が国で繁殖する鳥類約240種について、2,000か所以上の調査区画で現地調査を実施し、資料による調査結果と併せて鳥類の繁殖状況をは握した。
ウ 両生類・は虫類
絶滅のおそれのある種、学術上重要な種、産卵場所の保護を必要とする種等の観点から選定したサンショウウオ、モリアオガエル、タワヤモリ、ウミガメ等計34種の両生類・は虫類について生息域、生息状況を調査した。
エ 淡水魚類
絶滅のおそれのある種、学術上重要な種等の観点から選定したミヤコタナゴ、イタセンパラ等のタナゴ類、イトヨ、ハリヨ、トミヨ等のトゲウオ類、イトウ、オショロコマ等計27種の淡水魚類の生息域、生息状況について調査した。
オ 昆虫類
絶滅のおそれのある種、学術上重要な種を都道府県ごとに、50〜100種選定し、その生息域をは握するとともに、ゲンジボタル、ギフチョウ、オオムラサキ、ハルゼミ、タガメ等地域の自然環境の指標となるような種10種について全国的な分布を調査した。
(3) 海岸調査
我が国の約3万kmに及ぶ海岸線について、海岸汀線の砂浜、岩礁、崖等の自然形態及び護岸等による改変状況、ごみ、廃油等による汚染状況等をは握するとともに、海岸陸域の土地利用状況、レクリエーション利用の状況等を調査した。
(4) 干潟・藻場・サンゴ礁分布調査
分布の位置、面積、ごみ、土砂堆積等による汚染の概要等をは握するとともに、消滅状況について調査した。
(5) 海域環境調査
生物の生息状況から見た我が国の沿岸域の現状をは握することを目的として、91に区分された海域ごとにプランクトン、底生生物、付着生物、大腸菌、赤潮の発生状況について既存資料を収集整理した。
(6) 海域生物調査
生物生産力の特に高い地域である海岸域における生物の生息状況及び生息環境をは握するため、潮上帯(飛沫帯)及び潮間帯に生息する生物の種類、湿重量等を調査した。調査地区は全国で102に及び春夏の年2回調査を実施した。