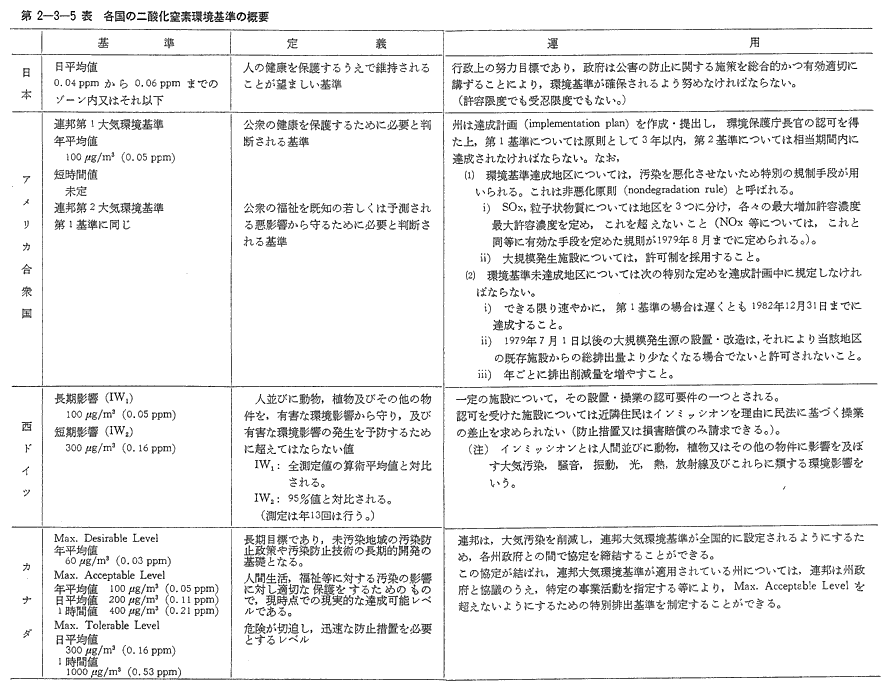
2 窒素酸化物対策
(1) 二酸化窒素に係る環境基準の改定等
? 新しい環境基準の概要
二酸化窒素に係る環境基準は、昭和53年7月11日に従来の「1時間値の1日平均値が0.02ppm以下であること」から「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること」に改定された。改定に至るまでの背景、手続き、理由等については既に第1部第2章第1節の3において詳説したところである。
? 新しい環境基準と国民の健康保護
新しい環境基準は中央公害対策審議会の二酸化窒素に係る判定条件等専門委員会(以下「専門委員会」という。)の提案した長期指針の年平均値0.02〜0.03ppmに相当し、同時にこれを維持した場合は、短期指針として示された1時間値0.1〜0.2ppmをもほぼ確保することができるものである。
この新環境基準に関し、その基礎となった専門委員会の指針を導くに当たって、?疫学データを総合判断の要素として採用したのは不適当であり、あるいは?疫学データのみに着目した統計解析では、年平均値の0.02〜0.03ppmという指針を導き出せないという、疫学データの採用に関しての新環境基準の科学的根拠に対する批判がある。
しかし、まず?については、二酸化窒素以外の大気汚染物質など他の要因も重なり合った中での健康影響を、しかも「せきとたん」という疾病以前の症状を指標として調査した疫学データは、二酸化窒素濃度と健康影響との関連を安全サイドに立って判断する手懸りになるものであり、専門委員会では疫学データのほかに、動物実験や人の志願者における研究結果をも踏まえて、総合的に判断して指針を提案したものである。そしてこの指針は、WHO(世界保健機構)が動物実験のデータをもとに、安全率を用いることによって示した指針にほぼ相当する値であり、国際的に見ても、最新、最善の科学的判断であると考えられる。
また、?については、上述のとおり、指針は各種のデータからの総合判断で出されたものであり、かつ、疫学データの調査解析に限ってもても、疫学データの制約条件を念頭に置きながら、医学的見地からの総合判断を加えた結果、少なくとも年平均値0.02〜0.03ppm以下の濃度では、二酸化窒素濃度と「せきとたん」の有症率との関連は観察されないと判断されたものである。
また、安全率についての議論は、既に総説で述べたところである。
以上のことから、専門委員会から提案された指針を最大限に尊重して定められた新環境基準は、十分な科学的根拠を有するものであり、「人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準」として、十分に国民の健康を保護することのできるものである。
なお、諸外国における環境基準については、国によって法律上の性格や運用の仕方、保護しようとする健康の水準などに相違があり、単純に数値を比較することはできないが、参考までに日本、アメリカ合衆国、西ドイツ及びカナダの二酸化窒素に係る環境基準の基準値、定義及び運用を示せば第2-3-5表のとおりである。
? 環境基準の運用
(i) 環境基準の達成・維持に当たっては、基準がゾーンで示されたことにかんがみ、二酸化窒素の濃度の水準に応じ、1日平均値が0.06ppmを超える地域(A地域)と1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域(B地域)とについて、それぞれ次のような努力目標が定められた。
まず、1日平均値が0.06ppmを超える地域(A地域)にあっては、原則として7年以内に、当該地域のすべての測定局において0.06ppmが達成されるよう努めるものとされている。
A地域における達成期間が改定の時点から原則として7年以内、すなわち60年までとされたのは、これまでの固定発生源及び移動発生源に対する規制の効果が顕著に現れるのは50年代の後半であり、0.06ppmを超える地域について0.06ppmを達成するには3年から5年という短期間では不可能であると考えられたことによるものである。
次に、1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域(B地域)にあっては、原則として、このゾーン内において、都市化、工業化にあまり変化が見られない場合は現状程度の水準を維持し、都市化、工業化が進む場合はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとされている。
B地域において、このような考え方が導入されたのは、専門委員会が提案した指針の下限と上限に相当する日平均値0.04ppmと0.06ppmとの間には、健康影響の観点からは差が付けられないものの、汚染濃度としては差がある以上、現実に汚染の防止が十分可能であるにもかかわらず安易に汚染の進行を容認することは、環境保全の一般理念に照らして適切でないと判断されたからである。
(ii) (i)の運用方針に従って対策を進めていくため、環境基準に基づく地域区分を行うこととしている。
この二酸化窒素に係る環境基準に基づく地域の区分は、大気汚染防止法施行令別表第3に規定する地域(K地域)の区分を参考に、52年度における1日平均値の年間98%値について、一般環境大気測定局のうち、上位3局の平均値が0.06ppmを超えるか、又は0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にあるかによって判定することを基本的考え方とし、更に地域の個別的具体的事情に即して十分検討を加え、総合的に判断し、決定するものである。
? 二酸化窒素等の測定法
二酸化窒素の判定条件等についての中央公害対策審議会答申(53年3月)においては、二酸化窒素の測定法について、ザルツマン法を現時点で最も実用性が高い測定法と評価するとともにi)最近の実験結果によればザルツマン係数(二酸化窒素の亜硝酸イオンへの転換係数)を2割程度高くする必要があること、ii)二酸化窒素と同時に測定することとされている一酸化窒素の測定の場合には酸化率(酸化剤による一酸化窒素の二酸化窒素への転換率)を補正する必要があること、が指摘された。これを受けて、二酸化窒素の測定法としては、新環境基準を定める環境庁告示において従来と同様ザルツマン法が採用されるとともに、i)二酸化窒素の測定をより正確に行うため、ザルツマン係数を0.72から0.84に改め、ii)一酸化窒素の酸化率を70%とすることとし、別途環境庁から都道府県あて通知された。
また、上記の答申においては、測定値の質的向上をめざすことが望ましいとの指摘もなされており、今後一層、測定器の保守管理の充実、測定データの影響要因の解析等に努めることとしている。
(2) 固定発生源対策
? 排出規制の現況等
ばい煙発生施設に対する窒素酸化物の排出基準は、48年8月に設定(第1次規制)され、50年12月(第2次規制)及び52年6月(第3次規制)に強化・拡充が行われた。第3次規制までの結果、規制対象施設数は約13,000施設、規制対象施設から排出される窒素酸化物量は全ばい煙発生施設からのそれの約73%となっており(第2-3-6表)、既設施設に係る排出量は50年時点と比べ約10%削減されたと考えられる。
しかしながら、第3次規制までで規制対象となっていない施設の中にも、ガラス溶融炉等環境濃度への寄与が無視できないものがあること、今後、燃料使用量が増加していくなかでできるだけ汚染の進行を抑制する必要があることなどから、未規制施設に対しても排出基準を設定することを内容とする第4次規制を行うこととし、現在、排出低減技術の開発状況、排出実態等を勘案しつつ、規制内容の詳細を検討しているところである。
? 窒素酸化物排出低減技術の開発状況
固定発生源から排出される窒素酸化物の低減技術としては、排煙脱硝技術、低NOx燃焼技術等がある。
(i) 排煙脱硝技術の開発状況は、まずLNG等の燃焼排ガスのようなクリーン排ガスについては、50年時点で実用化されていた。
次に重油燃焼排ガス程度のダーティ排ガスについては、52年時点で実用化の域に達しつつあるとされたが、53年には、解媒層の方式の改善、酸化硫安に関する対処法の進展等技術の信頼性が向上するとともに、無触媒法についてはすでに実用化され、無触媒・簡易脱硝法についても研究開発が進められ、各施設の実情に応じた選択を行えるようになりつつある。さらに、燃結炉排ガス等のよりダーティな排ガス等については、触媒方式によるパイロットプラント等の試験研究の成果が蓄積され、技術的に向上しつつある。
排煙脱硝の実用規模装置は、第2-3-7図に示すように、増加している。
(ii) 低NOx燃焼技術は、ばい煙発生施設本体に変更による二段燃焼、排ガス再循環、各種低NOxバーナーの使用等数多く開発されても適用例も多く、ほぼ熟成の域に達している。
(iii) 燃料から窒素分を除去することは技術的経済的に難しい点もあり、これを主目的とした装置はない。重油脱硫装置で硫黄分を除去する際に、少量ではあるが窒素分も除去され、脱硫後の低硫黄燃料をしようすることは窒素酸化物対策上も望ましい。
? 今後の固定発生源対策の検討状況等
今後は、ばい煙発生施設に係る全国一律の排出規制を進めるとともに、高濃度汚染の認められる地域については、新環境基準の確保を図るため、汚染の状況・構造、これまでの規制の効果等を踏まえて、総量規制等の地域差のある対策を講ずることとしている。
今後、固定発生源対策を計画的、合理的に進めていくために、53年度内においては、次のような検討が行われた。
(ア) 窒素酸化物汚染予測手法の確立等
窒素酸化物対策を効果的に実施していくためには、環境濃度に対する各種汚染源の寄与を明らかにする等汚染の構造をは握する必要があり、このため、窒素酸化物汚染予測手法の開発が進められている。
窒素酸化物拡散シミュレーションについては、硫黄酸化物拡散ミュレーションの場合とは異なった問題点が存在している。その第一は、自動車等の低煙源も環境濃度の寄与として大きな位置を占めることから、測定データの的確な評価、発生源データの一層の精密化を図るとともに、自動車から排出される窒素酸化物の挙動を説明できる拡散式の開発を含めた拡散モデルを確立する必要があることである。その第二は、発生源から排出された一酸化窒素(NO)の二酸化窒素(NO2)への変化を、目標値の設定の仕方を含めたシミュレーションモデルにおいて何らかの形で取り扱わねばならないことである。
(i) 窒素酸化物拡散モデル
工場煙突から排出される排ガスの拡散式としては、煙流断面中の拡散状態が鉛直・水平両方向とも正規分布を示すものと仮定する正規拡散式が用いられているが、拡散理論が大規模煙突からの排ガスを中心として発展してきたため、従来、自動車排ガスの拡散についても、工場煙突からの拡散式の延長上で論議されてきた実情にある。
これに対し、環境庁では、51年度から3か年にわたりエアトレーサーを用いた拡散実験を行った結果、道路沿道の拡散について鉛直方向及び水兵方向の濃度分布を従来の正規型拡散式で説明することは適切でないことを解明するとともに、これに代わって無風時、平行風時及び直角風時に対応する3種類の新しい拡散式を開発し、拡散モデルの精度の向上を図った。
(ii) 一酸化窒素から二酸化窒素への反応の取扱い
この問題については、従来、一酸化窒素の二酸化窒素への変化を光化学反応系の中の一つの反応として捉え、オゾン、炭火水素類、窒素酸化物、紫外線量等との相互の反応の反応速度論的な考察から、二酸化窒素の濃度を直接に求める方法が光化学オキシダントの予測手法の開発とあいまって検討されている。しかし、この方法については、オゾン、炭火水素類、紫外線量等に関する長期連続的なデータが得られにくいことから、関係各方面で実用化のために種々研究がなされているが、規制のための汚染予測手法としての実用化に当たっては、その適用の可能性について十分検討した上で適用する必要があり、このため、複雑な反応系の簡略化を行った上での半理論式の検討を進めた。
(イ) 総量規制の導入のための検討
二酸化窒素に係る新環境基準に照らせば、環境基準のゾーンの上限1日平均値0.06ppmを超えている地域について、原則として7年以内に、1日平均値0.06ppmを達成することが最も緊急度の高い課題である。この場合において、大気汚染防止法第5条の2に規定されている総量規制方式については、その直接の規制対象は固定発生源に限定されるものの、自動車等の発生源を含め、地域ごとの排出総量と環境濃度との関係をは握して作成される総量削減計画に基づき規制基準が設定される点で、一定の目標環境濃度を確保する対策方式として有効であり、かつ、個々のばい煙発生施設ではなく、一定規模以上の工場又は事業場(特定工場等)を単位とする排出許容量が設定される点で、事業者による効果的な対策の自由度が大きいという利点がある。このため、環境庁は、53年度において、総量規制に関する基準式等の検討を進めた。
(3) 自動車排出ガス対策
自動車から排出される窒素酸化物については、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に対しては48年度から、ディーゼル車に対しては49年度から、それぞれ規制が開始された。その後、乗用車については、50年度規制、51年度規制を経て、53年度には、47年10月の中央公害対策審議会の中間答申に示された当初目標値(窒素酸化物平均排出量0.25g/km)に沿った規則(53年度規制)が実施され、乗用車から排出される窒素酸化物は未規制時に比べ90%以上削減されることとなった。なお、53年度規制の輸入車への適用は56年4月からとされている。
また、ガソリン乗用車以外の車両(トラック、バス等)のうち、軽中量ガソリン車については50年度規制により、重量ガソリン車及びディーゼル車については52年度規制により、それぞれ規制が強化された。
トラック、バス等は、乗用車と比べ、技術的に排出ガスの低減が困難となっており、飛躍的な技術開発により極めて低レベルの規制実施が可能となった乗用車に比し、いまだ緩やかな規制の程度にとどまっている。すなわち、トラック等は、積載を目的として設計されるため、乗用車と異なり、排気量当たりの等価慣性重量及び車速当たりエンジン回転数が大きく、窒素酸化物の排出量が増加し、更にエンジンの配置が多様であるため、排気ガス対策に伴い発生する熱の処理が困難となるものもある。また、使用条件も一般に乗用車に比べ過酷であり、耐久性が要求される。これらの条件に加えて、運転性、燃料消費率、整備性の悪化等を最小限に抑える必要がある。また、ディーゼルエンジン車の場合は、ガソリンエンジンと基本的に燃焼方式が異なり、空気過剰率の範囲が広いこと、自己着火の場所が一定でなく数か所で同時に着火することが多いこと、混合気が不均一であり、ガソリンエンジンのように燃料が十分に気化されないこと等の相違点がある。これらの特性のため、ディーゼルエンジンにあっては、燃焼の過程を制御することにより排出ガスを低減させることが極めて困難となっている。
しかし、我が国の自動車保有構造の特徴の一つとして、他の先進諸国と比較してトラックの保有比率が極めて高いことが挙げられる。このためトラック等からの排出ガス量は、乗用車からの排出ガス量と比べ自動車排出ガス総量全体に占める割合も大きく、自動車の排出ガスに起因する大気汚染を防止するためには、これらのトラック等に対する一層の規制の強化が必要となっている。
このため約2年半の審議を経て、52年12月26日、中央公害対策審議会より自動車排出ガスの許容限度の長期設定方策について答申がなされた(第2-3-8表)。
答申においては、トラック、バス等の窒素酸化物に係る許容限度の強化の目標値が2段階に分けて示され、第1段階の目標値により規制は54年中、第2段階の目標値による規制は第1段階の規制実施の数年後、遅くとも50年代中に実施する必要があるとされた。この答申を踏まえ、53年1月30日第1段階の規制が54年規制として告示され、ガソリン車については54年1月、ディーゼル車については54年4月から適用されることとなっている。
答申で示された第2段階の目標値による規制については、これをできるだけ早期に、遅くとも50年代中に実施するため、自動車公害防止技術評価検討会を設け、自動車メーカーからのヒアリング等を行い、自動車排出ガス低減技術の開発状況の検討評価を進め、技術開発の促進を図ることとしている。(第2-3-9図)。
なお、トラック等に対する規制が大きな効果を現す時期は、54年規制のついては60年頃、第2段階の規制については60年代半ば頃になると見込まれている。
また、上記答申においては、大気汚染防止のための総合的な対策が必要であるとして、「交通の集中に伴う大気汚染が著しい都市において、個々の自動車に対する排出ガス規制に加えて、自動車交通総量の抑制と自動車交通流の円滑化を図る。」ための諸対策が提言されている。