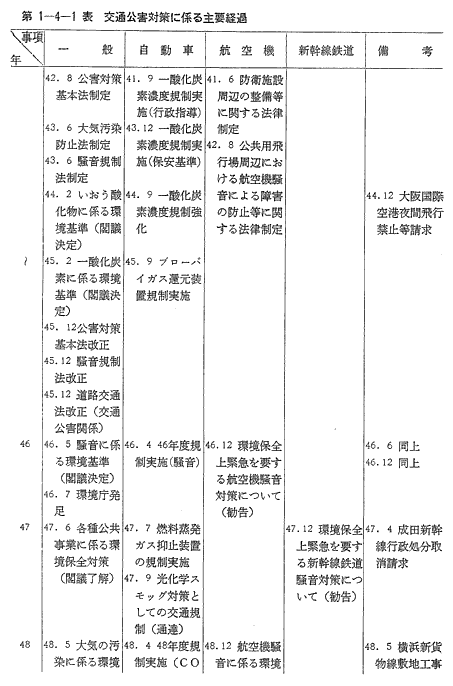
2 交通公害対策の総合的推進
(1) 交通公害対策に係る主要経過
経済社会の発展とともに公害が量的、質的に拡大し、激化し、複雑化してきた状況を踏まえて、42年に「公害対策基本法」が制定され、政府の総合的な公害対策が踏み出された。
今日まで、交通公害問題に対処するため、以下に概観するように交通機関別にそれぞれ所要の施策が講じられてきているところである(第1-4-1表)。
? 自動車交通公害対策
自動車排出ガス、自動車騒音を含む大気汚染及び騒音に関する諸施策を推進する上での行政上の目標として、公害対策基本法第9条の規定に基づき、45年に「一酸化炭素に係る環境基準」が、46年に「騒音に係る環境基準」が、48年には二酸化窒素、光化学オキシダント等について「大気の汚染に係る環境基準」が定められた。
また、43年には、自動車排出ガス対策をも盛り込んだ大気汚染の防止のための「大気汚染防止法」が制定された。自動車の排出ガス規制については、41年の一酸化炭素に対する濃度規制に始まり、その後ブローバイガス、燃料蒸発ガス等に対する規制を加えて逐次強化されたが、ガソリン車については48年から、ディーゼル車については49年から、一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物を規制する本格的な3物質規制が始められた。その後逐次規制が強化され、乗用車については53年度規制が、トラック等については54年規制が実施されている。
また、同じく43年に「騒音規制法」が制定されたが、45年には騒音規制法が改正され、自動車騒音の大きさの許容限度が同法の規定に基づいて設定されることとなった。これに伴い、46年に自動車騒音の大きさの許容限度が定常走行騒音、排気騒音及び加速走行騒音について設定された。その後51、52年には、自動車が市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音について、特に環境騒音に与える影響の大きい大型車及び大排気量の二輪車などに重点を置いて規制の強化が行われ、更に、54年に規制が強化されている。また、45年には、「道路交通法」の改正も行われ、交通公害の防止を図るための交通の規制に関する規定が設けられた。
その後、51年には「振動規制法」が制定され、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等の規定が設けられるなど関連法規の整備がなされてきている。
また、関係省庁において、交通流・量の管理、道路構造の改善等それぞれ所要の対策が進められている。
? 航空機騒音対策
航空機騒音に対処するため、48年に「航空機騒音に係る環境基準」が定められ、その達成・維持を図るため発生源対策、空港周辺対策等が実施されている。
公共用飛行場における騒音防止対策としては、飛行場周辺における航空機騒音の影響を軽減するために、42年「公共用飛行場周辺における航空機騒音により障害の防止等に関する法律」が制定されており、また、機材改良の一つとして50年10月に「航空法」の一部改正により「騒音基準適合証明」が制度化され、ジェット機について、その騒音が一定の基準以下となるよう規制されている。更に、空港周辺における住宅等の建築制限を含む土地利用制度を確率するため、53年に「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」が制定された。なお、自衛隊等の航空機騒音についても、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」等により対策が推進されている。
? 新幹線鉄道騒音振動対策
新幹線鉄道騒音に対処するため、50年に「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」が定められた。
環境基準の達成のため、51年に音源対策及び障害防止対策等を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」が閣議了解されており、振動対策と併せて対策が推進されている。
(2) 交通公害対策の総合的推進
以上のように、各々の交通機関別に、騒音、振動及び大気汚染因子に着目して、発生源対策、周辺対策等が講じられているところであるが、未だ必ずしも十分な成果を収めていない状況にある。自動車交通公害対策については、自動車構造の改善、交通管理、道路構造の改善等の対策が関係省庁において進められているものの、各々の対策の積み重ねのみによっては必ずしも十分な効果を挙げているとはいえず、今後、更に自動車交通量の増大等が予想される中で、大都市地域等における大量公共輸送機関の整備によるこれへの転換の促進、バイパス等の整備による道路機能の分化及び沿道土地利用の適正化を含む諸施策を充実強化するとともに、これらを有機的に組み合せつつ総合的に推進していく必要がある。
また、航空機騒音対策、新幹線鉄道騒音振動対策については、諸施策を充実強化し、今後とも総合的に推進していく必要がある。更に、これに加えて、環境保全の観点から、望ましい都市構造や交通体系の検討を含め広範な施策の検討を積極的に推進していく必要がある。
このようなことから、環境庁は、53年10月、大気保全局企画課に交通公害対策室を設置し、体制の強化を図ったところであり、関係省庁との連携をとりつつ、総合的な交通公害対策の樹立・推進を図ることとしている。