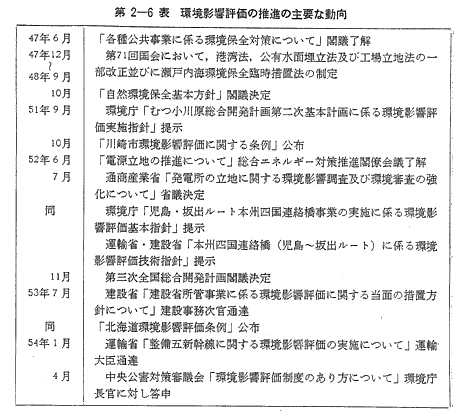
1 環境影響評価の定着化
(1) 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、公害の防止及び自然環境の保全について適切な配慮がなされることを期するため適切な環境影響評価を行うことの必要性は、今日広く認識されている。
政府においては、47年6月、「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解を行い、国の行政機関は所掌する公共事業について、事業実施主体に対し「あらかじめ、必要に応じ、その環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討等を含む調査研究」を行わしめ、その結果に基づいて所要の措置を採るよう指導することとした。
その後、48年の第71回国会において、港湾法、公有水面埋立法及び工場立地法の一部改正、瀬戸内海環境保全臨時措置法(53年の第84回国会において、瀬戸内海環境保全特別措置法と改称)の制定により、法令の整備がなされた。例えば、港湾法の一部改正により重要港湾の港湾計画については、計画の策定に際し環境に与える影響について事前に評価することとされた。また、公有水面埋立法の一部改正により、公有水面の埋立てについては、環境保全に対する配慮が免許基準として明文化され、環境影響評価が義務付けられた。
更に、48年10月、「自然環境保全基本方針」が閣議決定され、自然環境を破壊するおそれのある大規模な各種の開発に当たっては、事業主体が、必要に応じ、当該事業が自然環境に及ぼす影響の予測、代替案の比較等を含めた事前調査を行って、これを当該開発計画に反映し、住民の理解を得た上で開発事業を行うよう努めるべき旨述べられている。
(2) 最近の環境影響評価に関する動きを見ると、国及び地方公共団体において、大きな進展をみている。その主なものを例示すると、公共事業では、「建設省所管事業に係る環境影響評価に関する当面の措置方針について」(建設事務次官通達)に基づき、環境影響評価が実施され、整備五新幹線では、「整備五新幹線に関する環境影響評価の実施について」(運輸大臣通達)により、日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団に環境影響評価を行わせることとした。
公共事業意外でも、発電所の立地について、通商産業省は、「発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」の省議決定を行い、電気事業者等の環境影響調査及び通商産業省の環境審査について一層の強化が図られた。
一方、地方公共団体でも、川崎市が51年10月に「川崎市環境影響評価に関する条例」を、北海道が53年7月に「北海道環境影響評価条例」を定めたほか、54年3月において、宮城県、栃木県、三重県、兵庫県、岡山県、山口県、福岡県、沖縄県、名古屋市及び神戸市が環境影響評価に関する要綱等を定めている。
このようにして国における個別法、行政指導等や地方公共団体における条例、要綱等により、環境影響評価の制度等の整備への努力がなされてきたが、以上述べたことを含め、これまでの主な経緯をまとめると第2-6表のとおりである。