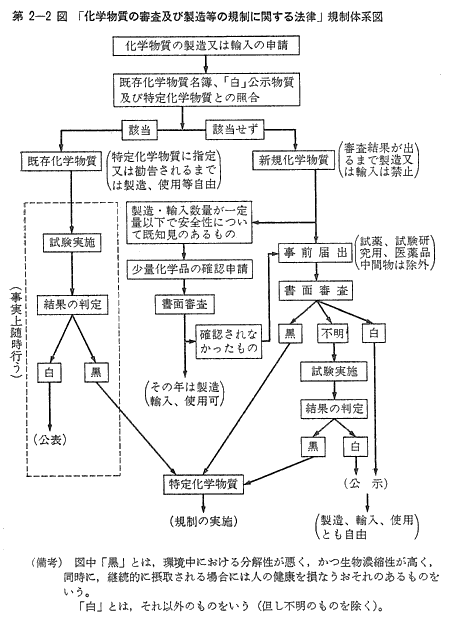
5 化学物質の安全対策
(1) 化学物質による環境汚染
人類の生活とその向上に寄与する化学物質は、年々新たに開発されており、その数は数万点にも及ぶといわれている。この多くの化学物質の中には有益性の反面で有害性を有するものがあり、古くから製造、使用、流通等の場での危険防止に注意が払われてきたが、環境の汚染という面は考慮が少なかった。化学物質の使用により又は使用後の廃棄を通じて、直接その物質が、又は廃棄の過程や環境中で変化した物質が環境を汚染し、直接的又は間接的に人類に脅威を与えるという新しい問題が発生したのは、化学物質利用の歴史の古さに比し極めて新しい。
41年スウェーデンにおいて鳥の組織中に含まれる未知物質がPCBであることが確認された。その後各国の研究の進展につれPCB汚染の世界的広がりが確認され、化学物質と環境という問題に対する世界的な関心の契機となった。
PCBは、昭和4年に商品化されて以来、「低毒性」の有用な化合物とされていた。しかし、PCBによる生物汚染は、問題とされた時には既に地球的規模にまで拡大しており、しかも、食物連鎖の終わりに位置する肉食性海鳥の繁殖に影響を与えていることが解明された。また、PCBは難分解性であり、その環境汚染がひとたび広がった場合、汚染のない環境の回復までには極めて長時間を要することが、研究の進展とともに明らかとなってきた。
そこで、従来、開発、生産、流通、使用についての法的規制を受けていなかった化学物質(主として工業薬品)を対象に、環境を経由しての人への影響の問題の検討が欧米各国においてほとんど同時に開始され、人以外の生物、現在及び将来の生態系への影響の問題も強い関心の対象になっている。
(2) 我が国における化学物質安全対策
ア 我が国では、48年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化学物質審査規正法」という。)が制定された。この法律は、難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質に対して、難分解性、生物濃縮性及び毒性(継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれ)があるかどうかを事前に審査すること、必要があれば所要の規制措置を採ること等を規定している。
既存化学物質については、その名簿の作成のみを定めており、その安全性の確認は国が行い、必要があれば特定化学物質に指定することとしている。このため、通商産業省が化学物質の分解性、生物濃縮性の調査研究を、厚生省が動物実験によるその毒性に関する調査研究を行っている(第2-2図)。
イ また環境庁は、49年以来、化学物質審査規正法に規定される化学物質等を含め、広く有害物質を探査するという立場から、環境調査等化学物質に関する各種調査研究を進めている。しかし、これまでの調査の対象は特に問題があるとみられている物質に限られており、従来の調査体制では膨大な数の化学物質について環境安全性の確認を短時間に行うことは困難であることが明らかになってきた。そのため、51年度から準備を進めてきた化学物質環境安全性総点検体系(第2-3図)に基づく調査を54年度から開始することとしている。
この体系は、1)数万点にも及ぶ化学物質について能率的合理的かつ必要最低限の費用で環境保全上の立場に立っての点検を行う 2)国際情報を本体系と有機的に結合する 3)調査結果に基づいて行政対策上必要とされる基礎資料を可能な限り整備しておく 4)要注意化学物質については長期の追跡調査を考慮する 5)国際社会における有害化学物質問題の先発国としての責務を配慮するという諸点に着目したものである。
(3) 化学物質審査規制の国際的動向
化学物質による環境汚染の問題に対処するため、我が国のほかアメリカ、スイス、スウェーデン、イギリス、カナダ、ノルウェー、フランスの諸国が何らかの規制を既に行っており、更に西ドイツ、オーストラリア等も法律制定の準備を進めている。
このような各国の動きとともに、各国の安全性の審査範囲や基準の相異による非関税障壁等の貿易問題及び別個の試験法に基づく安全性試験の重複実施による経済上の問題が生じてきた。更に、数万点以上といわれる既存化学物質に対する安全性の点検は一国ではなし得ないほどの膨大な時間と費用を要するという問題がある。経済協力開発機構(OECD)、世界保健機関(WHO)、国連環境計画(UNEP)等の国際機関は、これらの問題を解決するために、次のように種々の活発な活動を主宰するようになった。
OECDは、52年7月の「化学物質の人及び環境に対する影響を予測する手続及び必要事項に関するガイドライン」についての勧告を採択し、同勧告に伴う具体的活動として、53年からステップシステム(規制手法)に関するグループ等6専門家グループが設置され、54年末を目標に報告書の作成を行っており、我が国の専門家も積極的に参加している。このうち、物理化学的性質グループ及び分解性・蓄積性グループでは、我が国を含む諸国の試験研究機関の参加による各種試験手法の相互比較を行うこととなっている。
この他、OECDは、参加国の特別拠出金による計画として化学品の規制問題を取りあげることを決定した。この計画では、1)GLP(試験データの信頼性確保に関する研究所の要件)等4テーマについて検討が行われることとなった。
WHOでは、52年5年の総会で、化学物質の健康影響の評価の必要性についての決議が採択され、これを受けて、WHOは化学物質の健康への影響の評価計画を立案した。本計画は、従来から行われている有害物質等の環境保健クライテリア計画の拡大・強化を図るものである。
また、UNEPは、国際有害物質登録制度(IRPTC)により、化学物質に関する情報の収集、有害性に関する早期警報等を行っている。
このような各国の規制の動向及び各国際機関の各種作業の進行から、重複作業による加盟国の財政負担の増大等に関し全体的調整の必要性が生じ、53年4月、化学品問題を議題として、日本、アメリカ、西ドイツ等16か国並びにOECD、WHO等6国際機関によるストックホルム会議が開催され、作業の調整問題が討議された。この会議では、今後の重要作業課題として、下記6項目が合意されたほか、この分野の国際協力を行う機関として、緊急的対応についての検討については、既に活動の実績のあるOECDが、また、より長期的な活動については、WHOが、それぞれ最もふさわしい旨の意見の一致を見ている。
1) 安全性評価に必要なデータの内容と試験方法 2)GLP(信頼性確保に関する研究所の要件) 3)実質的な情報と行政施策に関する情報交換 4)情報の機密保持 5)化学物質規制の経済・貿易への影響の評価手法 6)国際的基本用語集
以上述べた多国間協力に加え、ヨーロッパ共同体諸国間の強調活動、二国間協力活動も次第に拡大する傾向にある。我が国としても日米環境保護協力協定に基づき米国との間で有害物質の識別の規制パネルが設置されており、51年以降毎年、専門家会合が開催され、情報交換や技術的事項の討論が行われている。
(4) 今後の課題
我が国は世界に先立ち化学物質問題に取り組み、化学物質審査規制法を制定し、新規化学物質の審査体制を確立し、既存化学物質の点検体制の整備を行いつつあり、今後環境面からの安全性の点検を進めていくこととしている。
また、新規化学物質の審査体制、安全性の確認技術等は各国からも注目されており、化学物質問題の先発国として、国際協力について大いに貢献していく必要がある。
更に、化学物質による環境汚染の問題は、単に人の健康への影響のみを安全性の判断尺度とするのではなく、広く生態系への影響も含めて環境への影響そのものを尺度とするよう検討する必要がある。