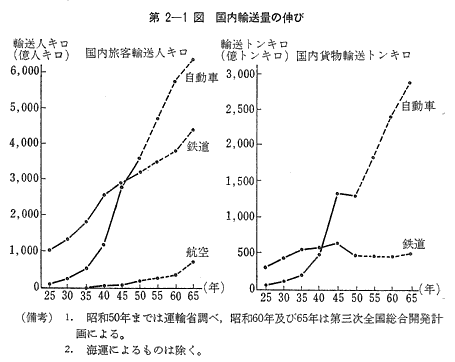
2 交通公害対策
近年、自動車、航空機、鉄道等の交通網の拡大、高速化等によって国民生活の利便性が高まった反面、これらの交通機関の運行に伴い発生する騒音、振動、大気汚染などの交通公害は、一般国道43号、東京都の環状7号線、大阪国際空港などの例に見られるように、各地で深刻な問題となっており、中には訴訟に至ったものも少なくない。
(1) 交通公害問題の背景
我が国において交通公害が深刻化している要因を考えてみると、まず、国土、特に平地の狭隘さから限られた土地に高密度の居住が行われ、また、都市への人口と産業の集中に伴って交通需要が都市地域に過度に集中したこと等が挙げられる。
また、戦後の経済成長の過程において輸送需要が高まり、交通施設及び交通網の整備、拡大ともあいまって旅客輸送量、貨物輸送量とも急激な増加を示したことも、もう一つの要因として挙げられる。
今後とも、国内輸送量は増加するものと予想されており、その中でも自動車輸送量は著しい増加が見込まれている(第2-1図)。
このような状況において、交通公害問題は、今や緊急にその解決を図るべき重要な課題となっている。
(2) 現行の交通公害対策の概要
交通公害は、自動車、航空機、鉄道等の交通機関の運行に伴って生ずるものであり、現在、各々の交通機関別に各種対策が講じられているが、それらは、?個別発生源から発生する排出ガス、騒音等を低減し、あるいはそれらの交通総量を抑制する等の発生源対策、?交通機関の実際の運行に伴い発生する公害を低減し、あるいはその伝播・拡散を防止するための道路、飛行場等の施設構造の改良、?交通公害による被害の発生を防止、又はそれらを軽減するための周辺対策として位置付けられる。
まず?の発生源対策としては、自動車に対する排出ガス、騒音の許容限度の設定に基づく自動車本体の改良、航空機の機材改良、新幹線鉄道の車両の改良が行われているほか、都市総合交通規制等の交通量抑制対策、交通管制システム等による交通流の円滑化等の対策が講じられている。
?の施設構造の改良としては、道路における路面改良、遮音壁、環境施設帯等の設置や、飛行場における滑走路の移転、防音林、防音堤の設置、新幹線鉄道における防音壁等の設置等の対策が講じられている。
?の周辺対策としては、民家、学校等の防音工事及び移転、緩衝緑地・緩衝建築物の整備等の対策が講じられている。
(3) 交通公害対策の推進
これまで、前述のように各交通機関別に、発生源対策、周辺対策等の各種施策が講じられてきたところであるが、未だ必ずしも十分な成果を挙げているとはいえない状況にある。自動車交通公害については、各般にわたる対策が関係省庁において進められているものの、各々の対策の積重ねのみによっては必ずしも十分な効果を挙げているとはいえず、今後、更に自動車交通量の増大等が予想される中で、諸施策を充実強化するとともに、これらを有機的に組み合わせつつ総合的に推進していく必要がある。また、航空機騒音対策、新幹線鉄道騒音対策についても、諸施策を充実強化し、今後とも総合的に推進していく必要がある。
更に、環境保全の観点から都市構造や交通体系のあるべき姿を見い出し、制度面の新たな施策も含め、総合的な対策を検討し、推進していく必要がある。
このような状況に対処するため、環境庁は、53年10月、大気保全局企画課に交通公害対策室を設置し、長期的な展望の下に、関係省庁と連携をとりつつ、総合的な交通公害対策の樹立、推進を図ることとなった。
(4) 交通公害と土地利用施策
今日、交通公害が深刻となっている大きな理由の一つは、交通施設及び交通網の整備と、住宅その他の建設とが交通公害防止の観点から必ずしも十分な整合が図られず、これらが近接して設置されていることに求められる。このため、今後、交通公害問題をより根本的に解決するためには、計画的な土地利用を実現することが重要である。
交通公害を防止するために必要とされる土地利用施策について考えると、まず、交通施設周辺における騒音、振動等の伝播を防止し、被害の発生を防ぐために、交通施設と周辺の土地利用が調和するよう各種施策を実施していくことが必要である。この場合、交通施設の周辺に一定の緩衝帯を設けて影響の軽減を図るため、緩衝緑地の設置、緩衝建造物の誘導等の対策を促進することが必要である。特に、道路においては、道路の交通の量と質及び地域とのかかわりの程度に応じて、道路の機能を地域間の通過交通のための道路と地域内の生活のための道路とに分化し、交通公害防止の観点から道路のあり方を再検討し、それに相応した整備を図ることにより、以上のような対策がより効果的に採り得ることとなろう。
また、現在、交通公害の防止を目的とした土地利用規制としては、航空機騒音について、53年4月の「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」の制定によって、特定空港周辺の一定地域内における住宅等の建築の制限等の措置が我が国で初めて制度化されている。
次に、一定の生産活動や日常生活を営む上で必要とされる交通総量の少ない都市構造を実現するための土地利用対策が必要である。その場合、物流需要発生型の施設等の配置いかんが都市内交通の量及び質に極めて大きな影響を及ぼすこととなることから、都市における物流機構の合理化を図るなど都市機能の再配置、再編成等を一層促進することが必要であろう。
更に、基本的には、交通施設に関する計画と地域開発計画あるいは地域の土地利用計画との整合を十分に図ることが重要であり、また、交通施設の建設に当たっては、良好な環境を維持するために、必要に応じ環境影響評価を実施し、地域環境との調和を保ちつつ適切に配置されるよう十分配慮することが必要である。