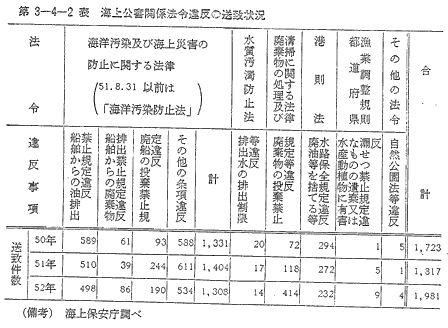
2 海洋汚染防止対策
(1) 監視・取締体制の整備
海上保安庁は、海洋汚染の防止を図るため52年度において引き続き、監視・取締り要因を増員するとともに、巡視船艇・航空機及び監視取締艇の整備増強、公害監視用VTR、分析測定機器等の各種資機材の整備強化を行い、監視・取締り体制を一層充実強化した。また、従来から船舶又は陸上から排出される油、廃棄物及び臨海工場からの排出水等についての監視・取締りを強力に実施してきたが、最近は違法行為が、悪質、巧妙化する傾向にあるため、監視・取締り手法の改善等を図るとともに、全国的あるいは地域的な一斉取締りを実施するなど法令違反の摘発に努めている。
また、船舶の燃料油取扱い作業中における漏油事故が多発しているため、「船舶による漏油事故防止推進期間」を設けて、全国一斉の臨船指導及び関係会社等に対する指導を行うとともに、漏油事故防止体制の実態調査を行い、事故多発の原因を解明し、事故防止体制の改善に努めている。
最近3か年における海上公害関係法令違反の送致状況は、第3-4-2表に示すとおりであり、52年は1,981件で、51年に比べ164件増加している。このうち、船舶あるいは陸上等からの油及び廃棄物の排出等悪質な事犯は1,442件で、全体の72.8%を占めている。
(2) 海洋汚染の未然防止対策
ア 船舶による海洋汚染の防止対策
船舶による海洋汚染の防止については「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」により、油及び廃棄物の排出の規制及びそれを確保するための油水分離装置等の備付け義務、廃棄物排出船の登録制度等必要な措置が講じられているが、近年、タンカーからの油流出による海洋汚染は国際的に重要な問題となっており、このため1973年に、海洋汚染防止に必要な船体構造、設備要件を定め、政府が責任をもって定期的な検査を実施すること等を内容とした海洋汚染防止条約が採択された。
我が国としても、このような国際的動向に対応してこれらの海洋汚染防止対策を早期に実施できるよう鋭意技術的諸問題の検討を行っているところである。その後、1977年3月に米国大統領は、タンカーの安全及び汚染防止の強化に関する声明を発表した。IMCO(政府間海事協議機関)では、これを受けてタンカーの構造・設備基準等の強化について数回の検討を重ね、1978年2月に開催された国際会議において「1973年海洋汚染防止条約の1978年議定書」が採択された。本議定書により、一定のタンカーにSBT(専用バラストタンク)、COW(原油洗浄方式)、CBT(クリーンバラストタンク)等を義務付けることとなり、タンカーの構造・設備基準が更に強化されることとなった。本議定書は、先の条約の内容を一部改訂し、これと一体となった条約であることから、我が国としても、本議定書を早期に批准、国内法化するために、IMCOにおける技術的問題点の検討に積極的に参加するとともに、国内体制の整備を行っているところである。
イ 廃油処理施設の整備
船舶内において生ずる油性バラスト等大量の廃油を処理する廃油処理施設は、47年度までに整備を完了し、52年度においては51年度に引き続き排水基準の強化に伴い改良が必要となる施設等の整備を行った。
操業中の廃油処理施設は、53年1月5日現在、港湾管理者、民間事業者等の管理するものを併せて81港130か所である。
(3) 海洋汚染の防除対策
ア 海洋汚染防除体制の整備
海上保安庁は、タンカー等の船舶及び沿岸の石油関係施設から油が流出した場合に対処するため、52年度においては、東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海を管轄する第三管区(横浜)、第四管区(名古屋)、第五管区(神戸)、第六管区(広島)、第七管区(門司)の各海上保安本部に海上防災専門官を配置するとともに、油防除艇、油回収装置、オイルフェンス等の整備を図り、海洋汚染防除体制の充実強化に努めた。
また、従来から全国の主要港湾に設置されている「流出油災害対策協議会」等の指導・育成を図るとともに全国各地において、官民合同の大規模流出油事故対策訓練を実施した。
更に、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、51年10月設立された海上災害防止センターの指導・育成を図っており、52年4月、瀬戸内海で相次いで発生したアストロレオ号衝突・炎上事故、あまりりす衝突・油流出事故等に際しては、同センターに指示し、流出油の防除のための措置の実施に当たらせた。なお、消防庁においては、海域に接する石油コンビナート等特別防災区域について陸上から海域への流出油事故に対処するため、地方公共団体及び特定事業者に対して「石油コンビナート等災害防止法」等に基づきオイルフェンス展張船等の海上防災資機材等の整備拡充を図るよう指導した。
イ 港湾環境保全対策
港湾公害防止対策事業として、52年度において、東京港、四日市港、水島港等14港の汚泥しゅんせつ事業等を行った。更に、東京港、大阪港等35港において廃棄物埋立護岸及び港湾等において発生する海洋性廃棄物を処理するための海洋性廃棄物処理施設を整備し、また、港湾区域内の清掃のための清掃船の建造及び港湾区域内にある持主不明の沈廃船の処理を実施した。
ウ 一般海域の保全対策
運輸省は52年度においては48年度以降に建造した油回収船3隻及び清掃船6隻を用いて、東京湾、大阪湾及び瀬戸内海における浮遊油の回収並びに浮遊ごみの清掃を実施するとともに、52年度から2か年計画で伊勢湾の清掃船1隻及び東京湾、瀬戸内海の油回収船各1隻の建造に着手した。
また51年度から3か年の計画で油回収機能を備えた大型自航ポンプしゅんせつ船を建造中である。
このほか、51年度に引き続き東京湾、大阪湾及び瀬戸内海の海底に堆積している汚泥の処理等についての基礎的調査を実施した。
(4) 海洋汚染防止技術の研究開発
運輸省では船舶からの海洋汚染を防止するため、IMCOの1973年海洋汚染防止条約で船舶に設置義務が課せられることになる機器のうち、ビルジ用ろ過装置附属の油分警報設備を51年度より引き続き開発中である。また、閉鎖性海域に浮遊する希薄油分等の回収を目的として50年度より開発を進めてきた油汚染浄化装置については最終年度として海上実験を実施した。
更に、大量の油流出事故に対応できる高性能のオイルフェンス及び油回収装置についての研究開発を進めている。
また、海洋の浄化技術として、伊勢湾等における海水交換と汚染物質の希釈拡散機構等を解明するための水埋模型実験、汚泥しゅんせつ技術の開発等を行った。