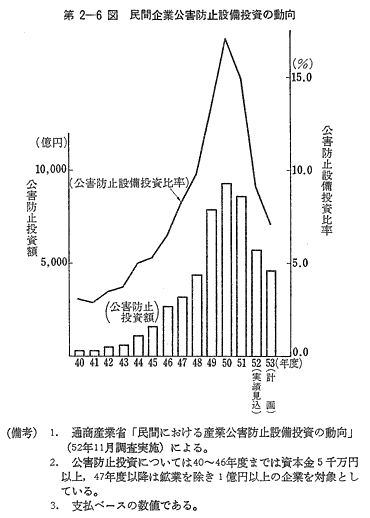
1 環境改善の費用と効果
(1) 環境改善費用の動向
我が国の環境対策の大きな特徴の一つに、過去の高度成長の過程で加速度的に進行する環境汚染とそれによる深刻な健康被害に対処するため、40年代半ば以降の10年足らずの間に、強力な対策が集中的に採られてきたことがある。このため、水銀などの有害物質による水質の汚染や、硫黄酸化物による大気汚染など、幾つかの分野で、著しい改善がもたらされた。しかし、このように、著しい効果を挙げることができた背景には、それなりに莫大な費用が必要とされてきたことも見逃せないことである。
我が国の民間企業における公害防止投資の推移を通商産業省調査によって見ると、調査対象企業の公害防止投資額は40年代の後半に急速に増加し、45年度の1,637億円から50年度には5.7倍の9,286億円へ、全設備投資に占める割合も5.3%から17.1%までに上昇している(第2-6図)。しかし、50年度をピークとして、民間企業の公害防止投資は51年度以降急激な減少を示しており、51年度には前年度比8%減、52年度には33%減の見込みであり、不確定要素は多いが53年度計画においても20%減少の見込みである。この間、調査対象企業の全設備投資額は緩やかながらも増加していることから、全設備投資に占める公害防止投資の割合も低下し、52年度には9.1%となっている。
40年代を通して一貫して公害防止投資が拡大してきたことは、急速な公害規制の強化に対応するための企業努力を反映したものであるが、このような莫大な投資が個別産業はともかく、マクロ経済的には深刻な影響を与えなかったのは、我が国経済が高度成長期にありその影響を吸収しえたためであると考えられる。
一方、ここ2年ほど民間企業の公害防止投資がこのように落ち込んでいる背景としては、一つには基礎資材産業を中心とする産業活動の低迷が考えられる。鉄鋼、化学、石油などの基礎資材産業では不況の中で大きな遊休設備を抱えているため、新規の設備投資がほとんど見られず、これに付設する公害防止設備に対する投資需要も落ち込んでいる。また、硫黄酸化物対策に見られるように、民間企業の公害規制に対する対応が50年度までに一応の水準に達したことも大きな要因として挙げられよう。
なお、公害防止投資は減少の傾向を見せているものの、公害防止資本ストックは拡大し続けており、このことにより維持管理費等公害防止費用は年々増大していると推測される。
52年度における特徴を業種別に見ると、ほとんどの業種において公害防止投資額は減少を示している。このなかで、火力発電及び鉄鋼の2業種は、公害防止投資額全体の過半を占め、51年度には伸びを示したが、52年度にはそれぞれ前年度比22%減、41%減と減少を見せている。
また、公害防止投資を施設種類別に見ると、大気汚染防止施設の割合が52年度で59%と依然過半を占めているが、その割合は近年低下しつつある。また、水質汚濁防止施設の割合も16%まで低下している。これに対して、騒音・振動防止施設、産業廃棄物処理施設、及び公害防止関連施設の割合が漸増している(第2-7図)。
次に、公共部門の公害防止のための費用の動向を国の予算及び財政投融資計画について見てみよう(第2-8図)。
国の環境保全関係予算は、53年度においては前年度比38%増と大きな伸びを示し、8,678億円となっている。国の予算(一般会計と特別会計の純計)に占める割合も、1.4%へと上昇し、これまでの最高となった。なかでも公害防止関係公共事業等関係予算の伸びは前年度比43%に達し、特に下水道事業費は前年度比53%増の5,147億円が計上されている。
一方、公害防止事業団、日本開発銀行など国の財政投融資対象機関の公害対策関係事業費は、前年度比8%増の1兆2,031億円と低い伸びとなっている。これは、民間企業の公害防止対策を対象としたこれら機関の融資枠が、実際の資金需要に合わせて減額されているためであり、これに対して、地方公共団体が下水道事業等を行うために発行する地方債の引受には前年度比31%増の9,244億円が計上されている。
以上のような最近における民間部門と公共部門の対照は公害防止措置の生産・受注動向にも明瞭に現れている。公害防止措置生産実績(日本産業機械工業会調べ)を見ると、国内民間部門向け生産は49年度の4,506億円をピークに51年度には3,780億円にまで減少しているのに対し、官公需要は51年度には前年度比26%増の3,007億円へと着実に伸び、公害防止装置生産全体の43%を占めるに至っている(第2-9図)。最近における受注状況ではこの傾向が一層顕著に現れており、52年度における受注実績では民需1,238億円に対し官公需2,944億円と全受注の67%を都市ごみ処理装置や下水処理装置を中心とする官公需要が占めている。
最近における民間企業の公害防止投資の急激な落込みと公共部門の着実な伸びは、我が国の環境保全対策が、単に産業公害防止にとどまらず、下水道の整備、都市ごみ処理設備の整備など生活関連の公共投資の増大を通してより幅の広い、国民の生活環境改善の方向へと展開しつつあることを示唆している。
(2) 硫黄酸化物対策の効果
我が国の環境汚染が全体として改善しつつある背景に、民間企業を中心とする公害防止の努力があったことはいうまでもない。その典型を硫黄酸化物による大気汚染問題に見ることができる。
硫黄酸化物対策としては早くから排出口における濃度規制が行われていたが、本格的な規制は43年の「大気汚染防止法」の制定とそれに基づくK値規制に始まる。これ以降ほぼ毎年規制が強化され、49年には「大気汚染防止法」が改正されて総量規制が導入されている。
このような規制の進展とともに、37年以来低硫黄化のための技術開発、エネルギー供給計画が推進され、輸入原油の低硫黄化、低硫黄重油の輸入の増大が図られる一方、40年代に入ってからは石油精製段階で重油の硫黄分を除去する重油脱硫装置が完成、普及し、また、40年代後半には排ガスから硫黄酸化物を除去する排煙脱硫装置が急速に普及を遂げた。
我が国における硫黄酸化物の環境濃度はこのような対策の結果、著しい改善を見せ、全国の大気汚染測定局における環境基準達成率は51年度には88%に達している。ここでは、これまでに民間部門が中心となって行ってきた硫黄酸化物対策が、硫黄酸化物の大気中への排出量の削減にいかに寄与してきたかを見よう(第2-10図)。
硫黄酸化物は燃料中の硫黄分が酸化されることによって発生し、その発生量は燃料消費量と燃料の硫黄含有率によって決まる。燃料消費量は不況による落込みがあったものの、51年度には45年度を1〜2割上回っており、潜在的な発生量は増加しているが、国内出荷重油の硫黄含有率が45年度の1.93%から51年度の1.41%へと低下していることに見られるように燃料の低硫黄化が実際の発生量の減少をもたらしている。これに加えて48年度から51年度にかけては、排煙脱硫が急速に普及し、大気中への硫黄酸化物排出量は51年度には45年度の6割を切るところまで減少するという著しい成果が見られている。
硫黄酸化物対策を民間部門の対応という視点から見てみると、各種の手段が何時も一様に適用されてきた訳ではないことが分る。輸入原油の低硫黄化が大きな役割を果たしたのは48年度までであり、その後は低硫黄原油と高硫黄原油の価格差が拡大したことから精製用輸入原重油の硫黄含有率は逆に若干上昇した。重油脱硫については比較的着実に硫黄分の除去に対する寄与度を高めているが、最近で排煙脱硫の普及などにより低硫黄重油の需要が低迷しており、その能力が十分発揮されていない。これに対して、排煙脱硫は、硫黄酸化物の捕集効率が9割程度にまで向上され、高硫黄重油を燃料として使用しても低硫黄燃料へ燃料転換したのと同じ効果が得られることから、燃料の低硫黄化にとって替わるものとして49年度以降急速にウエイトが上昇している。
このように民間部門においては、硫黄酸化物の排出削減のために、時々の状況に応じて最適な費用効率を生む手段の組合せが選択され、実施されてきたことがうかがえるが、重油脱硫と排煙脱硫に対する二重投資といった問題があることも否めず、また、短期的に見ても、49、50年度のように経済活動が低迷した時期に公害防止施設の設置が急速に進んだことが、企業の固定費負担を一層増大させることとなったなど、硫黄酸化物対策の大きな進展も、企業にとっては決して容易な道ではなかったといえる。
(3) 窒素酸化物対策の効果
窒素酸化物による大気汚染対策は、硫黄酸化物対策より10年遅れ、48年から始まったものであるが、それ以降の対策によってもはかばかしい改善が見られていない。
窒素酸化物には、物の燃焼に伴って大気中の窒素が酸化されてできるもの(Thermal NOx)と燃料中に含まれる各種窒素化合物が酸化されてできるもの(FuelNOx)とがあるが、物の燃焼過程において必ず発生するものであるため、重油等の燃料中の硫黄分に起因して発生する硫黄酸化物に比べてその発生源は多岐にわたる。発生源としては、工場、事業場における各種燃焼施設のような固定発生源と自動車のような移動発生源が主要なものであるが、一般家庭や飲食店等における暖房、厨房用の小型燃焼装置のような群小発生源も考慮する必要がある(第2-11図参照)。
窒素酸化物の環境濃度は、一般に大都市地域で最も高く、コンビナート地域では大都市及びその周辺地域に比較して低い濃度となっている。これは、煙突の高さといった発生源の違いなどによる影響のほか、窒素酸化物の排出量構成における移動発生源のウエイトが無視できないことが考えられる。
そこで、全国の窒素酸化物排出量の部門構成を51年度について試算してみると、第2-12図のように自動車が全体の4割近くを占めている。
もちろん、これは一つの試算であり、また鉱工業部門の生産活動が低迷している時点についてのものであるため、この比率を固定的に考えることはできないが、同じ大気汚染物質でも、硫黄酸化物と違い窒素酸化物の場合、環境汚染の改善のためには、鉱工業や電力などに対する固定発生源対策と同時に、自動車などに対する移動発生源対策を総合的に進める必要があることが分る。
なお、この試算では固定発生源のうち、鉱工業、電力以外のその他産業及び家計からの排出量は全体の1割に満たず、排出量構成に占めるウエイトは小さいといえるが、環境濃度への寄与においては無視できない場合もある。
次に全国の窒素酸化物の総排出量の推移を試算してみると、第2-13図のように、48年度から51年度にかけて潜在発生量が増加しているにもかかわらず、大気中への排出量は減少している。潜在発生量の増加は、工場等固定発生源については不況による燃料消費量の落込みが見られている一方、移動発生源について自動車の総走行量が増えているためである。自動車の総走行量は、大都市地域においては既に40年代後半から頭打ちとなっているが、全国的には増加しており、自家用乗用車について見ると48年度の1,450億kmから51年度には1,682億kmへと16%増えている。
このような潜在発生量の増加に対し、実際の大気中への排出量を減少させているのは、48年度以降の窒素酸化物対策である。移動発生源対策としては48年度規制以降、規制の拡大、強化が毎年度実施され、乗用車に係る53年度規制においては未規制時に比較して92%という削減率が達成されている。しかし、自動車の場合、既に使用過程にあるものの排出量を削減することが困難であり、規制対象が主として新車に限定されているところから、これまでの規制による効果は、今後車の代替が進むにつれ、更に現れてくると考えられる。
次に固定発生源対策としては、48年に大型施設を対象とする第1次規制、50年に対象施設の拡大等を内容とする第2次規制が実施され、その後も52年に既設大型施設の基準強化、規制対象施設の規模の範囲の拡大、規制対象施設の種類の拡大、新設施設の基準強化を内容とする第3次規制が実施されている。これまでのところ、固定発生源における窒素酸化物対策としては、LNGを燃料とするようなクリーン排ガスに対して高い除去率を可能とする排煙脱硝技術が既に実用化されているほか、ダーティ排ガスに対しても技術の信頼性は向上している。しかし、全国一律の対策としては、当面低NOx燃焼技術の適用が主体となろう。この場合、既設施設にあってはボイラー等の改造のため施設全体を停止しなければならない場合もあり、これまでの規制においては既設施設に限って2ないし3年の猶予期間を設けている。したがってこれまでのところ、固定発生源についても規制の効果が十分に現われていない段階にある。第3次までの規制の効果が十分に現れるのは55年度になってであり、固定発生源からの窒素酸化物排出量はこれらの規制によって55年時点の潜在排出量の約30%が削減されることが見込まれている。
このように、窒素酸化物対策については、その歴史が浅いことから、現在、これまでの規制の効果が十分現れていない段階にあるが、汚染の大幅な改善を図る上で、トラック、バスをはじめとする移動発生源からの窒素酸化物の低減技術の開発や都市における交通量の削減対策を一層進めるとともに、固定発生源における排煙脱硝装置については焼結炉等よりダーティな排ガスに対する排煙脱硝の技術の信頼性の一層の向上を図っていくことが重要な課題となっている。
(4) 水質汚濁対策の効果
水質汚濁対策としては、33年の「水質保全法」及び「工場排水規制法」の制定以来、問題水域を個々に指定して工場排水の規制が実施されてきたが、45年に「水質汚濁防止法」が制定され、全公共用水域を対象とする一律の排水基準が設定されることとなった。46年に定められた基準値は、BODに関しては日間平均120ppmとされ、工場排水による汚濁負荷量を未処理時に比べ6割程度削減するものであった。工場排水の場合、業種によっては原水の水質が数千ppmといった高いものもあり、スクリーニング、沈降分離、浮上分離という固液分離等の1次処理を行うことから対策が始まったため、初期においては急速に汚濁除去率を向上させることが比較的容易であったといえる。また、51年6月には、排水処理技術等から見て一般基準を満足することが困難な業種に限り適用されてきた暫定基準の期限が切れ、一部を除いてこれらの業種にも一般基準が適用されることになった。
一方、地方自治体においては、全国一律の基準だけでは環境基準を達成することが困難な水域について条例でより厳しい上乗せ基準を設定できることになっており、現在、この上乗せ規制は全都道府県で実施されている。その内容も、より厳しい基準値の設定だけでなく、規制対象施設の規模の範囲の拡大や規制対象業種の拡大も行われている。
更に、48年には「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が施工され、産業排水に係るCOD汚濁負荷量を47年当時の2分の1に削減するため、上乗せ基準の設定、強化等が行われてきた。
このような規制の強化によって、瀬戸内海地域では、同法施行の日から3年が経過した51年11月の時点において産業排水汚濁負荷量調査を実施した結果、瀬戸内海関係府県全体で見ると、割当負荷量673トン/日に対し、459.5トン/日に減少しているなど、一般に産業排水による汚濁負荷量は着実に減少していると考えられる。
こうしたなかで、近年問題として残されているのが人口の集中した地域における生活排水における水質汚濁である。生活排水による水質汚濁は、都市化の進行に伴う農業用水の汚染や都市内中小河川における悪臭などに見られるように、下水道整備の立ち遅れにより未処理排水が水域に排出されることによって生じるものが代表的である。生活排水による水質汚濁を防ぐ上で、都市における下水道の整備が重要であることはいうまでもなく、近年その整備を急速に進めるための努力が払われてきているが、下水道施設のストックが絶対的に不足していたため、これまでのところその整備が十分に進んでおらず51年度末で総人口の24%をカバーしているにすぎない現状にある。
我が国における主要な公共用水域である東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海について、その流域地域全体の汚濁負荷量を発生源別に推定してみると、生活排水と産業排水との割合が東京湾及び伊勢湾ではほぼ同等であり、瀬戸内海では生活排水が産業排水の約7割と考えられる。もちろん、個々の河川や海域を見た場合には水域地域の都市化の状況や下水道の整備状況、また工場の立地状況などにより生活廃水と産業排水の割合はまちまちであり、それぞれの状況に応じた対策が必要であるが、これからの水質汚濁対策としては、産業排水対策と生活排水対策の両者を総合的に推進する必要性が一層強まっているといえよう。
下水道の整備については、既に第4次下水道の整備五箇年計画に基づき55年度末に下水道普及率を40%に引き上げることを目途に下水道整備事業が推進されているところであるが、水質汚濁防止の観点から下水道普及率を向上させ未整備地域から大量に発生する汚濁負荷の減少に努めるとともに、必要に応じ下水処理の高度化を図る必要がある。現在行われておる下水処理は活性汚泥法等生物処理によりBOD20ppm程度に処理されている。しかし、閉鎖性水域、都市河川等では急速砂ろ過等による三次処理の導入等が必要な水域があり、今後、下水道の整備の促進とともに下水処理の高度化を推進する必要がある。
また、それとともに、用水原単位の低減や浄化用水の導入による河川流量の回復も重要な課題である。工業用水については淡水使用量に占める回収水の割合が50年には67.0%に達するなど取水量の伸びが著しく鈍化しているが、家庭を中心とする上水道等給水量は水洗便所の普及などにより増加を続けている(第2-14表)。
このため、大量の河川水が上流において取水され、河川の希釈作用、自浄作用を損う結果を生じている。水利用の合理化は、今後の水需給の観点から重要であるばかりでなく、地盤沈下や水質汚濁など公害防止の上からも、これを推進することが重要となっている。