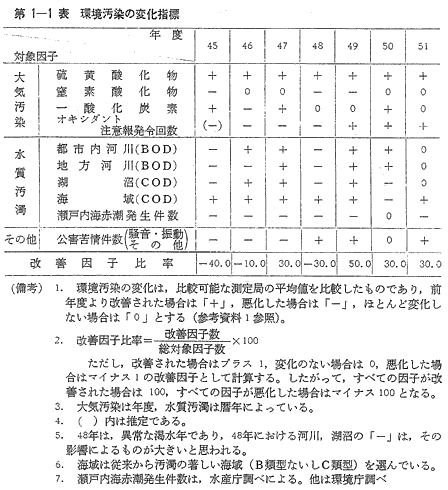
我が国は世界で最も厳しい公害を経験した国の1つであるが、これまでの公害対策の結果が次第に現れてきたことや経済活動の停滞から、環境汚染は、最近全体として改善傾向にあり、51年度においても環境汚染の変化の指標に見るように、改善ないし横ばい状態を示す指標が大半で総合的に判断して改善傾向が続いているといえよう(第1-1表)。
そこで個々の汚染について簡単に見ると、まず大気汚染に関しては、硫黄酸化物、一酸化炭素による汚染は50年度より51年度は改善し、環境基準を達成している地点もかなり多くなっている。これに対し、自動車や工場等から排出される窒素酸化物は48年以降、規制により多くの地点で汚染の悪化は阻止できたものの、望ましい環境基準を達成している地域はまだ極めて少ない状況にある。
第2に水質汚濁については、カドミウム、シアンなどの有害物質(健康項目)による汚濁は著しく改善され、ほとんどの水域で問題のない状況にあるのに対し、生活環境項目のうち代表的な有機汚濁指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)又はCOD(化学的酸素要求量)指標について見ると、総体としては改善傾向にあるものの望ましい水質環境に達していない水域が数多く残されている。
このほか、地域によっては富栄養化現象、温排水、濁水、河川等の酸性化等の問題もあり、水質汚濁の態様は複雑化、多様化する傾向が見られる。
第3に、その他の公害について見ると、まず騒音・振動については第1-2図のとおり、52年においても公害に関する苦情のうちで最も多数を占めており、対策の遅れが目立っている。特に自動車騒音については環境基準を満たす地点は未だ極めて少なく、航空機、新幹線に対する対策もようやく緒についたにすぎない。
地盤沈下は、東京、大阪などのかつて沈下が著しかった大都市地域では一応収まってはいるものの、大都市近郊、農業地帯の一部で依然として相当程度の沈下が現に進んでいる等の問題がある。
土壌汚染は、農用地においては対策事業の実施等により汚染の進行は防止されているが、最近は工場跡地等市街地の汚染が新たな問題となっている。
廃棄物は、生活様式の高度化、経済活動の進展等に伴ってその発生量は量的には膨大なものとなり、質的にも多様化している。したがって、これに対し、適正な処理を更に推進するため、今後とも対策の充実が要請されている。