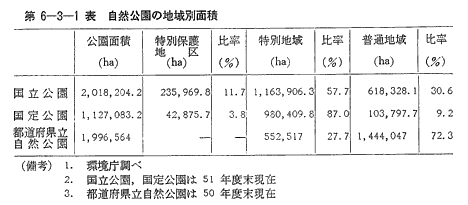
2 自然公園における自然保護
(1) 自然公園内における行為規制
自然公園の優れた風致景観を保護するため、自然公園内に特別地域、特別保護地区及び海中公園地区(都道府県自然公園の場合は特別地域のみ)を指定し(第6-3-1表参照)、当該地域地区内における風致景観を損なうおそれのある一定の行為は、環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととされている。また、普通地域においても一定の改変行為を都道府県知事に届け出させ、必要な規制を加えることができることとされている。
国立公園及び国定公園の特別保護地区、特別地域及び海中公園地区内における各種行為については「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査方針」の適用により、保護の適正化と事務処理の円滑化に努めている。
国立公園内の特別地域及び特別保護地区における工作物の新・改・増築、鉱物の掘採、土石の採取等の行為の環境庁長官に対する許可申請件数は第6-3-2表のとおりである。
(2) 管理体制の強化
国立公園内における風致景観を保護管理するとともに、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、阿寒、十和田八幡平、日光等主要な10公園に国立公園管理事務所を設置するとともにその他の地区に単独で駐在する国立公園管理員を配置している。51年度末現在の国立公園管理員定数は89人である。
(3) 国立公園湖沼水質調査
自然公園内の湖沼は、近年、利用者や施設の増加とともに水質の悪化も進みつつあるため、環境庁長官が指定する湖沼においては、湖沼への排水を規制することになっており、各湖沼の水質の現況をは握するため46年度から湖沼水質の現況調査を行っている。
51年度においては、倶多楽湖(支笏洞爺国立公園)、不動池(霧島屋久国立公園)等の各湖沼について、所要の調査を行った。
(4) 自然公園におけるごみ処理体制
近年、自然公園は利用シーズンには過剰利用の状況を呈しており、主要利用地域においては、空きかん等による汚染が目立ってきている。
これらのごみは、地理的特性からその収集と終末処理が極めて困難であり、単に美観のみならず悪臭などの汚染を引き起こすことがある。
国立公園内の総理府所管の集団施設地区とその周辺の美化については、従来から国立公園内集団施設地区等美化清掃事業を関係都道府県の協力の下に実施してきた。
また、それらの地域以外の自然公園の地域においても日常生活圏の地域から遠隔地にあること及び数市町村にまたがる場合が多いこと等により、その清掃活動に円滑さを欠いている。そこで特に利用者の多い主要な地域の美化清掃を積極的に推進するため、民間を主とした現地の美化清掃団体の組織の強化を図るとともに、団体が行う清掃活動について補助を行っている。
51年度においては、総理府所管の集団施設地区の清掃を直轄事業で行い、それ以外の重要な地区については清掃活動費補助金を交付して国立公園内の清掃活動の一層の充実を図った。
(5) 自然公園内における自動車利用の適正化対策
近年、自然公園内の優れた自然環境を有する地域への自動車の乗り入れが増大したことにより、自然公園の保護と利用の両面にわたり種々の支障が生じてきている。
例えば、自然保護の面では、道路の拡幅、駐車場の拡張等による地形、植生の改変、道路外への不法な乗り入れによる植生の破壊、排気ガス汚染等による植生の衰弱、夜間の通行による動物の殺傷、生息環境の悪化等の種々の問題が生じている。
また、自然公園の利用の面では、多くの車の侵入により静穏な環境や安全な利用が損なわれたり、交通渋滞により計画的、効果的な公園利用に支障を来す等の種々の問題が生じ、その対策が各方向から要請されている。
このため、環境庁では、国立公園内における自動車利用の適正化対策を講ずることとし、十和田八幡平国立公園奥入瀬地区、日光国立公園尾瀬地区、中部山岳国立公園の上高地地区、立山地区及び乗鞍地区並びに富士箱根伊豆国立公園の富士山地区をモデル地区として選定し、警察等関係機関の協力の下にマイカーのこれらの地区への乗り入れの適正化を図ったが、51年度においてもこれらの地区について前年度に引き続き適正化対策を実施した。
各地区における自動車利用の適正化対策は、関係機関の協力を得ながら国立公園管理事務所、地元関係機関及び関係団体で組織されている対策協議会で各地区の特性に応じた適正化方針が協議され、「道路交通法」に基づく交通規制や代替バス輸送などの対策が関係各機関により講じられている。
各地区における適正化対策の概要は次のとおりである。
十和田八幡平国立公園奥入瀬地区においては、国道102号線の夏期及び紅葉期の車利用に対処するため渋滞箇所において交通整理及び駐車禁止を行ったほか植生保護及び歩道利用者の安全、快適な利用確保のため、林内及び歩道への車両侵入防止施設を設置した。
日光国立公園尾瀬地区においては、群馬県三平峠口の大清水ですべての車両をストップし、大清水以奥は徒歩利用とした。また、富士見峠口、鳩待峠口もそれぞれ対策を実施した。一方、福島県がわのルートでは、特に車利用の著しいいわゆる「ミズバショウシーズン」に、沼山峠駐車場が、満車になる時点で御池で規制を開始し、代替輸送バスを運行させた。
富士箱根伊豆国立公園富士山地区においては、スバルライン終点、五合目駐車場の利用状況に応じ、入口ゲートで乗り入れる台数を規制し、また車止め等の施設を設けることにより、駐車場以外の地区への車両の乗り入れを禁止した。
中部山岳国立公園上高地地区においては50年7月から8月の最盛期の1か月間、中の湯から上高地へのバス、タクシー等を除く車両の乗り入れを禁止するとともに、夜間はすべての車両の乗り入れを禁止するという画期的な措置を講じたが、51年度もこれに倣った規制を行った。
また、乗鞍地区においては、乗鞍スカイラインの鶴ヶ池、畳平を中心に夜8時から翌朝3時30分まで通行を禁止したほか、終点部の公共駐車場以外における駐車禁止、園路への乗り入れ禁止などを実施した。
立山地区においては、山ろく桂台において美女平、室堂方面へは、定期バス及び観光バスに限り乗り入れを認めた。
以上の対策は三年目を迎え次第に自動車利用適正化対策の趣旨の浸透及び事前の広報の効果が現れ、マイカー利用者が減少し、踏圧、盗採などによる自然植生の破壊の減少、野生鳥獣の生息環境の破壊の排除、宿泊地周辺の静穏の維持、歩行者の安全確保、快適な利用の維持など直接的な効果が見られた。
(6) 特殊植物等の保全事業
国立公園等内に生育している貴重な植物等でその保護を生育環境の保全と一体として行う必要のあるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、尾瀬湿原(日光国立公園)、大瀬崎ビャクシン樹林、箱根仙石原湿原植物群落(富士箱根伊豆国立公園)、池ノ原ミヤマキリシマ群落(雲仙天草国立公園)について植生復元、環境等調査、病虫害防除に要する経費を県市町に対し補助した。
(7) オニヒトデ駆除事業
国立公園、国定公園の海中のサンゴ礁景観を保護するため、オニヒトデが異常発生している吉野熊野国立公園、足櫂宇和海国立公園、西表国立公園、奄美群島国立公園等の海中公園地区についてオニヒトデの駆除に要する経費を関係県に対し補助した。