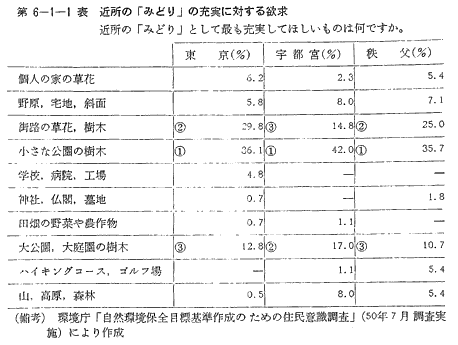
2 緑の保全目標の検討
自然環境保全行政を長期的観点に立って計画的に推進していくため、環境保全長期計画の一環として自然環境保全長期計画を策定することとし、自然環境保全審議会自然環境部会において、具体的な検討がなされているところであるが、特に都市地域における自然環境の保全の目標を策定するための検討の一環として、50年度には大都市(東京都)、中都市(宇都宮市)、小都市(秩父市)に住む4,500人の住民を対象に、そのために必要な基礎資料を得ることを目的に「みどり」に対する住民の意向を調査した。
調査の結果によれば、まず、東京、宇都宮、秩父の3都市とも、近年自然環境が悪くなっているという人が全体の約半数を占めているが、近所の「みどり」の量については、東京では「みどりが少ない」と思っている人が多い(45%)のに対し、宇都宮、秩父では「みどりが多い」と思っている人が多く(それぞれ全体の62%、72%)、また近所の「みどり」に対する満足度について見れば、東京では、「不満」派が「満足」派を上回るのに対し、宇都宮、秩父では「満足」派が過半数を占めている。
次に、充実してほしい近所の「みどり」としては第6-1-1表のように各地域とも「小さな公園の樹木」を第1位に挙げており、身近な緑の充実を望んでいることが示されている。
そして、「みどり」に対する要求水準については、どの地域でも7割前後の人が、「比較的良好な緑の多い住宅地」(ランク3)を住宅地の最低基準に選んでいる(第6-1-1図参照)。
更に、最低基準はあったほうがよいかどうかという問いに対しては、7割以上の人が「あったほうがよい」と答えており、「みどり」の量が少ないと感じている人ほど最低基準の必要性を強く感じている。また、住宅地の「みどり」は、現在の「みどり」の何倍あればよいかという問いに対する答えは、第6-1-2図に示すとおりであり、その平均は、それぞれ東京では「4.2倍」、宇都宮では「2.0倍」、秩父では「1.9倍」となっている。
なお、「みどり」の重要な機能については、3地域とも50%以上の人が?酸素を供給し、空気を浄化すること、?季節感を与えたり、人の心に落ち着きと安らぎを与えることを挙げている。
「みどり」の保護については、「個人の樹木を切ることについても最小限の制限をすべきだ」という人が各地域とも6割以上に及んであり、また「みどり」の環境を良くするために区(市)民税負担を増やしてもよいと考えている人が全体の6割を超えており、なかでも「1〜2%ぐらいなら増えてもよい」とする人が最も多く、東京では34.7%、宇都宮では44.4%、秩父では41.9%をそれぞれ占めている。
このように、都市地域の住民の間では、緑そのものの重要性及び緑を増加させることの必要性に対する認識が一般的になっており、緑の保全目標の策定の必要性が強く認識された。