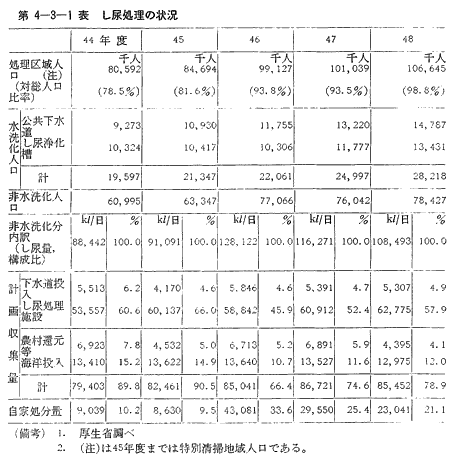
1 廃棄物処理の現況
廃棄物は、主として地域住民の日常生活に伴って生じる一般廃棄物と、企業等の事業活動に伴って生じる産業廃棄物とに大別される。
(1) 一般廃棄物
一般廃棄物については、市町村が処理計画を定め、これに基づいて市町村及び市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が処理しているが、一般廃棄物のうち、まずし尿の処理状況について見ると、第4-3-1表に掲げるとおりである。し尿の処理方法のうち、公共下水道及びし尿浄化槽によって処理する方法と、収集したし尿をし尿処理施設及び下水道の終末処理場で処理する方法とを併せてし尿の衛生的処理と呼んでおり、48年度におけるし尿の衛生的処理率(衛生的処理人口/計画処理区域人口)は72.6%である。
国民の生活意識の多様化、高度化とともに、生活環境の改善も進められ、水洗化人口は逐年増加しているが、なかでも下水道未普及地域におけるし尿浄化槽の設置数の増加には著しいものがある。しかし、し尿浄化槽は、その管理が不十分なときは、放流水の水質の悪化を来し、公共用水域を汚染するおそれがあるため、その設置者に対し、し尿浄化槽に関する知識の普及を図り、併せてし尿浄化槽清掃業者の資質の向上を図る等所要の措置を講ずる必要がある。
次にごみ処理の状況は、第4-3-2表に掲げるとおりである。可燃性ごみは原則として焼却により安定化、減量化を図ったのち、埋立処分しているが、このためのごみ処理施設は49年度末において全国で1,645基設置されている。また、不燃性ごみについては、圧縮、破砕した後埋立処分している。
最近においては、テレビ、冷蔵庫等家庭電気製品を中心とした粗大ごみや、廃プラスチック類等の排出量の増大が市町村の清掃事業において大きな問題となっている。
(2) 産業廃棄物
企業等の事業活動に伴って生じる産業廃棄物は、多種多様な性状を呈し、その排出量は膨大な量に上ると推定されている。
産業廃棄物の処理については、事業者が自ら行うことを原則としており、このため事業者は、排出の状況に応じた適正な処理を行わなければならない。しかし、現実にはその処理は必ずしも十分とは認め難く、処理基準に違反した不適正な処理や不法投棄が後を断たない状況にある。
また、狭小な国土の中で、これら膨大な量に上る産業廃棄物の埋立処分の場所を確保することは次第に困難となっており、事業者は原材料等の合理的使用、産業廃棄物の再生利用等を図り、排出する産業廃棄物の減量化に努めることが必要となっている。
事業者は、都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託することもできることになっているが、51年2月1日現在における産業廃棄物処理業者数の許可件数は全国で10,682件である。
このほか、事業者責任を前提とした上で、これを補完するものとして、地方公共団体の出資に基づき、あるいは、地方公共団体と企業等の共同出資により、産業廃棄物処理公社等が設立されている事例も見受けられ、50年11月1日現在、10府県において実施に移されている。なお、設置届のあった産業廃棄物処理施設は50年5月1日現在において4,097基となっており、これは49年3月末に比べて937基の増加となっている。