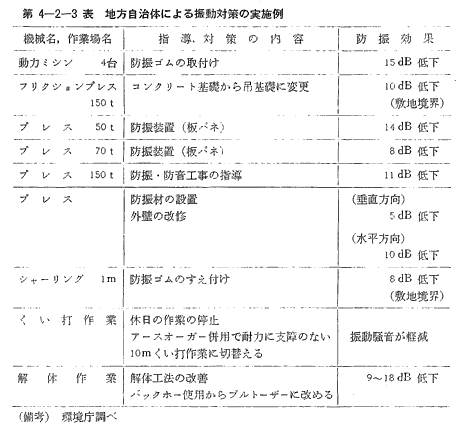
2 振動の防止対策
振動公害については、振動特性、地質、家屋構造等との関連について解明すべき点が多く残されている。個々の振動防止対策としては、次のような対策が行われているが、今後は、発生源対策のほか、振動の伝幡、減衰特性や家屋防振構造等を勘案して、周辺対策を含めた総合的な都市計画・土地利用を検討する必要がある。
? 工場施設では、防振装置(空気バネ、金属バネ等)、防振材(ゴム等)の取付け、基礎の改善(吊構造・重量化等)等が行われており、その効果も確認されている。
? 建設振動については、振動を発生する建設機械の改良と併せて低振動工法の開発が多くなっている。また、防振材の取付け等の対策を行っている。
? 道路交通振動については、最近、防振性のある舗装材料の開発、防振溝等の研究が進められているが、一般的には路面の損傷、凹凸か所の補修、舗装の打替えにより対応されている。また、道路交通振動の発生は重量車両によるものがほとんどであることから、道路の改良と併せて、交通規制による手法も引き続き検討する必要がある。
? 新幹線鉄道振動については、軌道、高架構造物の重量化、路盤構造の改善等の対策が考えられており、種々の研究、実験が進められている。
なお、地方自治体で行っている工場、建設作業における防振対策の実施例は、第4-2-3表のとおりである。
振動により生活環境が損なわれることを防止するため、昭和51年3月、「振動規制法案」が国会に提出された。その大綱は、次のとおりである。
? 工場及び事業場振動
都道府県知事は、住居の集合している地域等住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定し、指定地域における著しい振動を発生する特定施設を設置する工場及び事業場について、指定地域の土地利用状況に応じて、環境庁長官の定めた範囲内で規制基準を定め、所要の規制を行うこととする。このため、これらの工場及び事業場における特定施設の設置について、事前届出制をとるほか、規制基準に適合しない振動を発生することにより周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、改善等の勧告及び命令を行うことができることとしている。
? 建設工事に伴う振動
指定地域内において行われる著しい振動を発生する特定の建設作業については事前届出制をとるほか、都道府県知事は、一定の基準に適合しない振動を発生することにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、振動の防止の方法等に関し、改善等の勧告及び命令を行うことができることとしている。
? 道路交通振動
都道府県知事は、指定地域内における道路交通振動が所定の限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のため舗装、維持又は修繕の措置を採るべきことを要請し、あるいは都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を採るべきことを要請するものとしている。
? その他
以上のほか、市町村長に対する事務委任について定めるとともに、振動規制の実効を期する見地から、振動防止に関する国の援助、研究の推進等について所要の規定を設けている。
一方、中央公害対策審議会から、「振動規制を行うに当たっての規制基準値、測定方法等及び環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について当面の措置を講ずる場合のよるべき指針について」51年3月6日に答申があった。
これを踏まえ規制基準値、測定方法等については、振動規制法における政令、府令等の内容として検討を進めることとしている。
また、新幹線鉄道振動については、51年3月12日に環境庁長官から運輸大臣に「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」勧告を行った。
この勧告は、新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが70dBを超える地域について緊急に振動源及び障害防止対策等を講ずること、及び病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置することを内容としている。