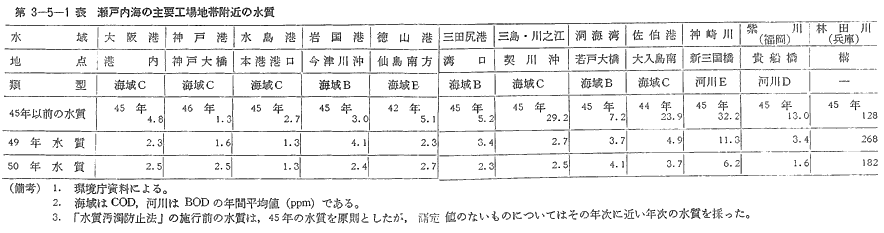
1 瀬戸内海の汚濁の現況
瀬戸内海においては、工業用地の造成に適した遠浅の海岸が多いこと、2千万人以上の沿岸人口を擁した内湾として工場の立地条件に恵まれていたこと、昭和30年以降工業化の推進による所得の増大を目指して、工業誘致の気運が極めて強かったこと等により、高度経済成長の時期を通じてコンビナートの形成を中心に重化学工業化が推進されてきた。これに伴い、工場排水等の増大により、瀬戸内海の水質が悪化してきた。「水質汚濁防止法」が46年6月に施行されたことに伴い、瀬戸内海においても同法に基づき主要な工場地帯周辺水域及び都市周辺水域に上乗せ排水基準が設定され、監視取締体制も整備されてきた。この結果、第3-5-1表のとおり主要な工場地帯地先海域のうち水質が改善されてきているものも多くなってきている。また、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が48年11月2日に施行され、51年11月までに段階的に産業排水に係るCOD汚濁負荷量を47年当時の2分の1にするため、上乗せ排水基準の設定又は強化の措置が採られているので、工場地帯地先海域等にあっては今後も水質の改善が期待されているところである。
ところで、環境基準の監視調査の結果を見ると、第3-5-2表のとおり、有害物質が環境基準値を超えて検出される割合は、全国的に改善が進み、49年度において0.20%まで低減しているが、瀬戸内海においては、47年0.21%、48年0.22%、49年0.14%と全国平均に比べ低い水準で推移している。また、瀬戸内海に流入する河川のBOD並びに海域のCODの環境基準の達成状況は、河川のBODにあっては、47年度の64%から異常な渇水年であった48年度の58%に低下したが、49年度には70%に増加し、46年以降最高の達成状況を示している。類型別に見るとAA類型、C類型においては達成状況はむしろ低下している。
海域のCODにあっては、46年度の70%から47年度の83%に増加して以来、48年度80%、49年度82%となっており、類型別に見ると49年度はA、B、C各類型で46年以降いずれも最高の達成状況を示している。
また、47年以降実施している瀬戸内海総合調査の結果からCOD濃度ごとの面積比率の変化を見ると、47年以降49年まで減少していた1ppm以下の面積比率が50年は増加し、47年以降10%台で推移していた3.1ppm以上の漁業に不適当な水域は50年は5.3%とかなり低い面積比率となっており、水質が改善された状況が認められる(第3-5-3表参照)。
このように、瀬戸内海のCODで表わされる水質は工場地帯の地先海域において水質が改善されており、総合調査の結果からも50年になり水質が改善された状況が認められるが、水質の年次変化等もあり、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づく排水規制の強化等の措置の効果を確認するためには、今後の水質を見守る必要がある。
なお、瀬戸内海の赤潮発生確認件数を見ると、第3-5-4表のとおり、被害を伴う赤潮の発生確認件数の比率が低下しているものの、その発生確認件数が年々増加しており、監視通報体制の整備による増加を差し引いても依然として瀬戸内海の一部で富栄養化が進行しているものと見られる。
また、瀬戸内海におけるタンカーの事故、廃油類の不法投棄等に起因する油による海洋汚染の発生確認件数は、47年以降500件から800件台で推移しており瀬戸内海の油汚染問題は定常化している。特に、49年12月に水島コンビナート地区において発生した石油タンクの事故により流出した油は、瀬戸内海の水島灘一帯、播磨灘西部から紀伊水道にまで拡散し、漁業等に重大な被害を与えた。広範な調査の結果、事故後約3か月経過した時点では水質はおおむね事故前の状態に回復していたこと等が判明したが、生態系に悪影響を及ぼす等のいわゆる後遺症が残ることも懸念され、50年度も引き続き調査を実施したところである。
このように瀬戸内海においては、有機物による二次的な汚濁及び突発的な事故による油汚染等の水質汚濁問題が継続しており、今後も更に施策の強化を図っていく必要がある。