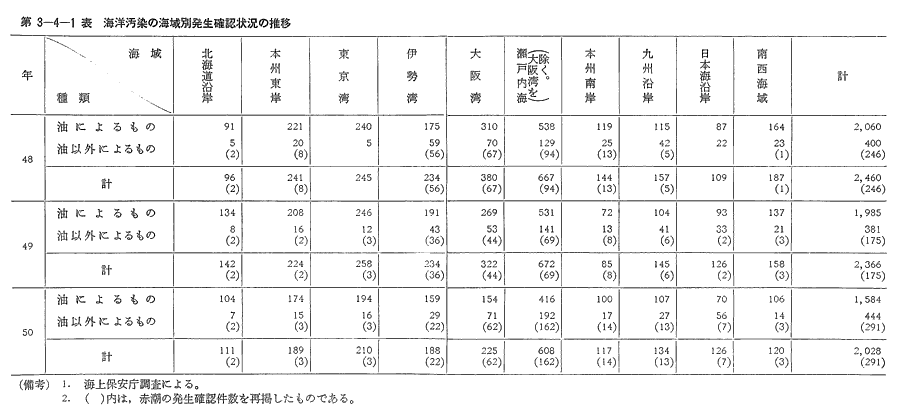
1 海洋汚染の現況
(1) 港湾
港湾やその周辺海域は、その水質及び底質が漸次改善の方向に向かっているところもあるが、河川を通じ、又は直接流入する工場又は事業場からの排水及び生活排水等によって汚染されている。
(2) 日本近海
環境庁においては、50年度において日本近海海域における総合的な汚染の調査及び研究を行った。すなわち、日本周辺を流れる海流を横断するように、日本沿岸から廃棄物投棄海域の中心を通る5測定線を設け、これらの測定線上の合計75測定点において、水質についてはCOD、SS、栄養塩類、重金属、PCB、油分等を、底質については強熱減量、硫化物、重金属、PCB、油分等を、プランクトンについてはクロロフィル等を調査した。
また、海上保安庁は、海洋環境保全のための科学的調査を実施しており、引き続き50年度においても日本周辺海域及び汚染の著しい主要な湾における海水又は海底たい積物中の油分、COD、PCB及び重金属の調査を実施した。日本周辺海域における表層海水中の石油濃度は、50年度調査結果で平均数ppb程度を示していた。また、「海洋汚染防止法」に定める排出海域に投棄された産業廃棄物の漏えい拡散機構を解明するため、同海域における深層海流の測定及び海底地形の調査を実施した。これまでの調査では、自然レベルと比較して、排出海域であっても特に汚染が進行しているとは認められていない。
更に、海上保安庁は、廃油ボールによる汚染の実態をは握するため、49年7月から50年6月までの間、漂流、漂着等の実態調査を実施した。この結果、48年の調査に比べ、一部の地域で若干減少傾向の見られるところもあるが、沖縄諸島から南九州、伊豆諸島に至る太平洋岸の漂着は、依然として多く相対的に恒常化しつつあるといえる。
最近3か年間に海上保安庁が我が国周辺海域において確認した汚染の発生件数の状況は、第3-4-1表に示すとおりであり、50年は2,028件で、49年に比べ338件減少している。これは、海上保安庁が巡視船艇、航空機の連携による監視取締り、汚染防止指導等を強力に実施したことにより、関係者に海上公害防止に対する意識が浸透しつつあることなどによるものと考えられる。50年における汚染発生確認状況を種類別にみると、油によるものが全体の約78%を占め圧倒的に多く、またこれを海域別に見ると、例年海洋汚染が多発している東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海(大阪湾を含む。)において、全体の約61%に当たる1,231件が発生している。
更に、これを原因別に見ると、全体の約48%に当たる971件が船舶あるいは沿岸の陸上から不法投棄されたものやその疑いのあるもの、バルブ操作の誤り等器具類等の取扱い不注意によるものなど人為的なものである。
なお、「海洋汚染防止法」の規定に基づいて、廃棄物排出船の所有者等が海上保安庁長官に報告した結果によると、49年に日本周辺海域に投棄された廃棄物は、廃酸、廃アルカリ等の廃棄物が約653万トン、し尿等の一般廃棄物が約525万トン、しゅんせつ作業等に伴い生ずる水底土砂等が約5,317万トン、合計約6,495万トンとなっている。
(3) その他の海域
気象庁は、47年度から日本周辺及び西太平洋海域の全般的汚染(海洋バックグランド汚染)状態の定期観測を実施しているが、沿岸域においては遠洋海域に比べ、比較的高い水銀、カドミウムが認められた。また、COD、アンモニア、有機リン、重金属等は、海流系と密接な関連を有し、これらの値が南半球においてよりも北半球において大きかった。