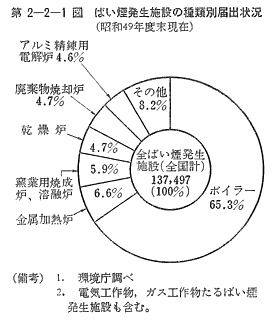
1 固定発生源の状況
(1) ばい煙発生施設・粉じん発生施設の状況
「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙(硫黄酸化物、ばいじん及びカドミウム、窒素酸化物等の有害物質をいう。)を排出する施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に対しては排出規制が、土石の堆積場等粉じんを発生する施設(以下「粉じん発生施設」という。)に対しては飛散防止のための施設の構造等の規制が行われている。これらの施設を設置し、又は変更しようとする者は、都道府県知事(「大気汚染防止法施行令」第13条第1項第1号に定める市にあっては市長。以下本節の1において同じ。)に届出を行うことになっている。近年におけるこれらの施設の設置状況を見ると第2-2-1表のとおりであり、毎年度相当数の増加が見られる。また、ばい煙発生施設の種類別届出状況は第2-2-1図に示すとおりである(詳しくは参考資料5参照)。
(2) 取締り指導状況
ばい煙発生施設は排出基準を、粉じん発生施設は構造使用管理基準を遵守しなければならない。都道府県知事は、これらの施設の監督等のために、工場、事業場に立入検査を行ったり、必要な報告を徴収したりすることができることになっている。これらの施設のうち電気工作物又はガス工作物に当たるもの以外のものについては、基準違反がある場合には、都道府県知事は、改善命令や基準適合命令等の行政処分を行うことができる(電気工作物又はガス工作物に当たるものについては、「電気事業法」又は「ガス事業法」に基づき所要の措置を命ずることになっている。)。なお、ばい煙発生施設については、基準違反に対し直罰が適用される。
昭和49年度における都道府県知事による取締り指導状況は第2-2-2表のとおりであり、法に基づかない行政指導が大きなウエイトを占めている。
都道府県は「大気汚染防止法」第4条の規定に基づき、ばいじん及び有害物質について、条例で、国の排出基準より厳しい排出基準を設定できることになっている。これを行っているところは、50年12月末現在で20都道府県である。このうち、ばいじんについて設定しているのは6、有害物質について設定しているのは16であり(2県は両方について設定している。)、窒素酸化物について上乗せ基準を設定しているところはない。