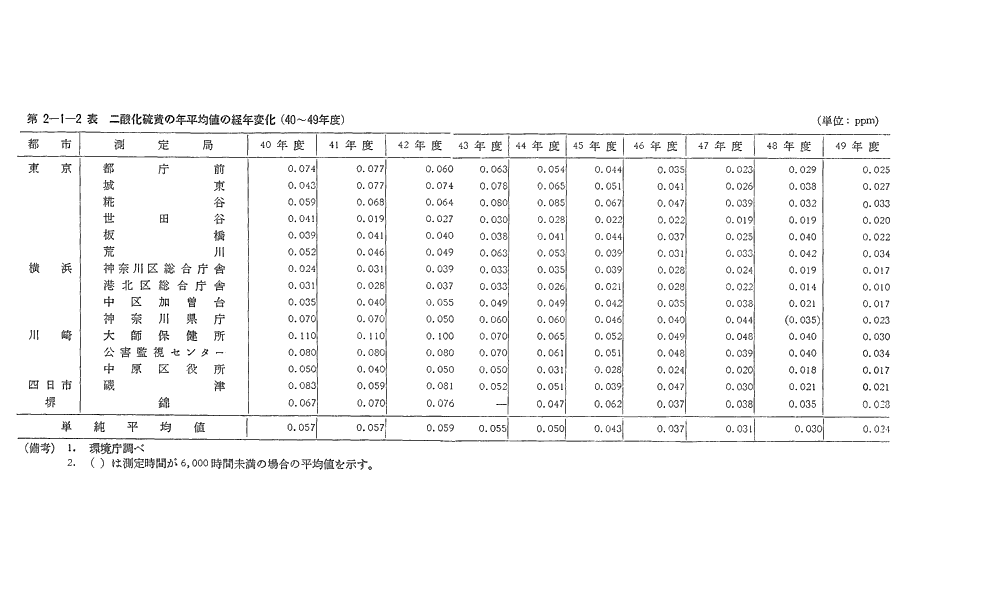
2 汚染物質別の大気汚染状況
(1) 二酸化硫黄
大気汚染物質の中で代表的な汚染物質である二酸化硫黄は、その大部分が化石燃料の燃焼に伴って発生する。化石燃料としては、石油、石炭等があるが、全国的には、石油等に重油の燃焼に伴う二酸化硫黄の発生が圧倒的な部分を占めている。
? 年平均値の推移
40年度以前に測定を開始して以来、測定場所を変更せずに毎年継続して測定を行っている15測定局の経年変化は第2-1-2表に示すとおりである。四日市市の磯津や川崎大師等をはじめとするこれらの測定局は、40年代の前半においては代表的な二酸化硫黄汚染地域であった地域に設置されているものである。49年度におけるこれらの測定局の年平均値はピーク時の3〜4分の1に減少しており汚染の改善が著しい。また、これらの測定局における40年度から49年度までの年度別平均値の単純平均値を見ると第2-1-3図に示すように43年度以降は汚染が着実に減少し、49年度においても引き続き改善の方向にある。
また、48年度と49年度の2年間連続して有効測定時間以上測定している893測定局における年平均値の増減状況を示すと第2-1-3表のとおりである。
前年度に比較して二酸化硫黄濃度が増加している測定局は25局(3%)にすぎない。しかもこれらの測定局は各地域に散在しており、特定の都道府県における汚染の増加は見られない。
また、減少している測定局は209局(23%)であり、地域的には神奈川、愛知、大阪、岡山、山口の各府県において著しい汚染の減少が見られる。
? 環境基準の達成状況の推移と現状
環境基準は、1時間値及び1日平均値によって定められているので時間又は日について環境基準適否の評価が可能になっている。しかし、当該地域の大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断する上からは、年間にわたる測定結果を長期的に観察した上で評価を行うことが必要なので、長期的な評価を次のようにして行うこととしている。すなわち、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値(例えば365日分の測定値がある場合は高い方から7日分を除いた8日目の1日平均値)が0.04ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準の長期的評価に適合するものとしている。
長期的評価に基づく環境基準の達成状況の推移は第2-1-4表のとおりである。年々増加してきた測定局の中には、汚染の進行していない地域に設置されたものも含まれているので、この表からは直ちに環境基準達成都市が多くなったとはいえないが、49年度における環境基準を達成した都市及び測定局の総数に対する割合は48年度に比べて都市、測定局とも20%前後増加している。
49年度において二酸化硫黄の測定を行った全国の測定局のうち年間測定時間が有効測定時間以上測定している測定局は406都市、1,125測定局である。このうち49年度に新たに長期的評価による環境基準を達成した都市は49都市である。また、長期的評価による環境基準を達成しなかった都市は150都市である。
しかしながら、第2-1-5表に示す二酸化硫黄年平均値上位20測定局をはじめとして、環境基準未達成の測定局は約30%ある。これらの地域、特に従来から高濃度汚染の地域については、改善が見られるものの依然として高濃度汚染が続いており、総量規制の実施並びに排出規制(K値)の強化を必要とする状況にある。
(2) 二酸化窒素
二酸化窒素による大気汚染は、物の燃焼に起因して発生するものが主体と考えられる。その場合、直接発生するものは、ほとんどが一酸化窒素であるが、これが大気中で酸化されて二酸化窒素に変化する。
大気汚染の発生源として二酸化硫黄の場合には工場等を主に考慮してきたが、二酸化窒素の場合には、このほか自動車等の移動発生源や都市における各種商業施設や一般家庭における暖房等の群小発生源も考慮する必要がある。一般に自治体による大気汚染常時監視測定局は、学校、保健所、公民館、役所等の公共施設に設置されることが多く、これらは多くの場合道路から比較的近い位置にある。このため、これらの測定局における測定値は、近傍の道路からの自動車排出ガスの影響を程度の差こそあれ受けるものと考えられる。しかし、道路との関係のみでは説明が困難である場合もあり、測定値の評価に当たっては、測定局と道路あるいは群小煙源との位置関係を調べた上で、局地的な影響をどの程度受けているか慎重に検討する必要がある。
二酸化窒素について継続して測定を行っている測定局の経年変化を第2-1-6表に示した。
これらの測定局のうち43年度から継続して測定している6測定局について経年的に単純年平均値をとり、図示すると第2-1-4図のようになる。また、45年度からデータの得られた10局を加えた16局につき同様に経年変化を図示すると第2-1-5図のようになる。
6局平均では49年度は48年度から横ばい状態で推移している。しかし、43年度から49年度までの7年間について見れば、年平均で0.011ppmの増加が見られる。また、16局平均について見ると48年度から横ばい状態を示している。しかし、45年度から49年度までの5年間について見れば年平均値で0.005ppmの増加が見られる。
次に、46年度から継続して測定を行っている39都市61測定局について単純年平均値の変化を見ると、次のとおりである。
46年度 0.026ppm
47年度 0.027ppm
48年度 0.029ppm
49年度 0.028ppm
また、48年度と49年度の2年間連続して有効測定時間以上測定している245測定局における年平均値の増減状況を示すと第2-1-7表のとおりである。
49年度において二酸化窒素の測定を行った全国の測定局のうち、年間を通じて有効測定時間以上測定している測定局は、249都市448測定局である。
このうち長期的評価による環境基準を達成した測定局は25局である。これらの内訳は、北海道伊達市有珠潮香園、壮瞥町古川果樹園及び三重県大安町大安中学校の3局が48年度に引き続き環境基準を維持し、11局が49年度新設された測定局で、9局は、48年度は有効測定時間に達していない測定局である。
しかし、測定時間内で長期的評価を試みれば9局はいずれも環境基準を達成していたものである。残る2局、鳥取県鳥取衛研と石川県金沢市大気監視センターは、48年度は環境基準を達成していなかったが、49年度には達成した局である。
また、大気汚染の程度を見るために、二酸化窒素の環境基準を5年以内に達成するものとする地域(5年達成地域)と5年以内に中間目標(環境基準を年間総日数の60%以上維持)を達成し、8年以内に環境基準を達成するものとする地域(8年達成地域)とにおける環境基準の不適合率を見ると、中間目標を達成しているものは、8年達成地域で26局(14.0%)、また、5年達成地域で中間目標のレベルに達しているものは、149局(56.8%)となっている(参考資料4参照)。
なお、一酸化窒素について、46年度より継続して測定している27測定局における年平均値の単純年平均値の推移は次のとおりであり、4年間の推移で見る限りでは、一酸化窒素の濃度は減少傾向にある。
46年度 0.029ppm
47年度 0.027ppm
48年度 0.025ppm
49年度 0.024ppm
自動車排出ガス測定局における二酸化窒素濃度及び一酸化窒素濃度について、40年以前に測定を開始して以来、毎年継続して測定を行っている都内3測定局の経年変化は、後掲第2-2-21表に示すとおりである。
これを見ると、一酸化窒素、二酸化窒素のいずれもが、49年、50年は減少している。
(3) 一酸化炭素
一酸化炭素の主な発生源は、自動車からの排出ガスである。したがって、その汚染の程度をは握するには、交通量の激しい道路際における一酸化炭素濃度の推移を見ることが必要である。例えば、都内3か所の道路際の測定局における一酸化炭素濃度は後掲第2-2-21表のとおり40年以降漸増したが、45年には初めて減少し、それ以後は漸減傾向にある。43年度から継続測定している一般環境大気測定局は、東京、大阪の国設測定局であり、その測定値の推移は第2-1-8表のとおり、両測定局とも49年度は48年度に比べほぼ横ばいといえよう。
次に、48年度と49年度にわたり継続して有効測定時間以上測定している69測定局における年平均値の増減状況を見ると、第2-1-9表のとおりであり、全般的には一般環境中における一酸化炭素濃度の減少傾向が見られる。
なお、49年度一酸化炭素測定データのうち、有効測定時間以上測定している測定局は71都市99測定局あるが、これらの測定局について長期的評価による環境基準達成状況を見るとすべての測定局が達成している。
(4) オキシダント
オキシダントの発生は、気象条件に大きく左右されるため、高濃度のオキシダントの発生状況は年によりばらつきを示しているが、注意報発令濃度である1時間値が0.15ppmを超えた日数の経年変化を見ると第2-1-10表のとおりである(注意報の発令回数等については、第2節4光化学大気汚染対策を参照)。
(5) 炭化水素
炭化水素は、光化学反応による大気汚染の起因物質の1つとして重要な物質であり、近年になって注目されている物質である。発生源を大別すれば自然現象によるものと化石燃料又は有機溶媒等の生産、消費過程で生ずる場合に分けられる。前者については、そのほとんどがメタンであり、大気中に1.2〜1.6ppm存在するといわれている。後者については、炭化水素の種類及び使用状況の多様性から排出状況は多岐にわたっている。測定される炭化水素は各種のガス状炭化水素類であるためその量はメタン又はプロパン等に換算して表示される。全国的な汚染状況を概観するにはデータが十分でないが、参考として44年度以前から継続して測定を行っている測定局における年平均値の推移について見ると第2-1-11表に示すように横ばいである。
(6) 浮遊粒子状物質
浮遊粉じんのうち粒径10μ以下の粒子は沈降速度が小さく、大気中に比較的長期間滞留し、気道又は肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼすことから10μ以下の粒子を対象として浮遊粒子状物質に係る環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下)が設定されている。
浮遊粒子状物質の測定は、ろ過捕集による重量濃度を基準としてこれと直線的関係が得られる光散乱法を相対濃度測定法として行うことになっており、評価に際しては重量濃度測定値と光散乱法による測定値との比を用いて光散乱法による相対濃度計の指示値を重量濃度へ換算することとしている。しかしながら、重量濃度測定並びにデータ処理体制が整備の途上であるため、49年度においては都道府県からの報告中、6,000時間以上相対濃度測定を行い、かつ、四季を通じて重量濃度測定を行って重量濃度への換算がなされた11都府県の46都市88測定局のデータのみについて整理を行った。このうち、環境基準の長期的評価を達成している測定局は16局であり、それらの年平均値は0.028〜0.042mg/m
3
の間にあり、未達成局62局の年平均値は0.28〜0.138mg/m
3
の間に分布している。
88測定局における年平均値の分布は、第2-1-12表に示すとおりであり、この表からは年平均値が0.04mg/m3を超えると環境基準の長期的評価を達成する可能性が少なくなることが示されている。
なお、浮遊粉じん中の金属成分中の分析については国設大気測定局において、ハイボリューム・エアー・サンプラーにより捕集したものを原子吸光法により行っている。分析項目はバナジウム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、カドミウム、鉛である。過去5年間継続して分析を行っている東京、川崎、大阪、尼崎等9測定局における5年間の汚染傾向を概観すると、全般的に横ばいないし減少傾向にある。なお、大気中鉛濃度の推移は第2-1-6図のとおりである。
(7) 降下ばいじん
降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち重力により又は雨によって降下するばい煙、粉じん等である。
測定は、採取装置を用いて1か月間試料を採取し、その重量の秤量によって行う。測定結果は、t/km
2
/月で示される。年平均値は月間降下ばいじん量を平均したものである。
49年度に測定が行われた1,654地点中10t/km
2
/月以上を示した地点数は206地点(12.5%)うち、20t/km
2
/月以上を示した地点は41地点(2.5%)、30t/km
2
/月以上を示した地点は17地点(1%)となっている。
20t/km
2
/月以上を示した測定地点は、セメント、石灰、鉄鋼関係の産業のある都市に多く見られる。
45年度から継続して測定を行っている766測定地点について、降下ばいじん量の年平均値の推移を示すと第2-1-13表のとおりである。5年間で10t/km2/月以上の測定地点数が著しく減少しており、汚染の改善がうかがえる。
(8) 世界の主要都市の汚染物質濃度
なお、諸外国においては、我が国のようには必ずしも測定網が整備されていないが、世界の主要都市の大気汚染状況を参考までに示すと第2-1-14表、第2-1-15表のとおりである。
これを見ると、各国によって測定方法に違いがあり、また同じ測定原理を採用していても測定の細部については異なっており、更に調査した測定局の数に著しい差があり、単純に国際比較を行うことは困難であるが、我が国の汚染が諸外国と比較して特に悪い状況であるとはいえない。