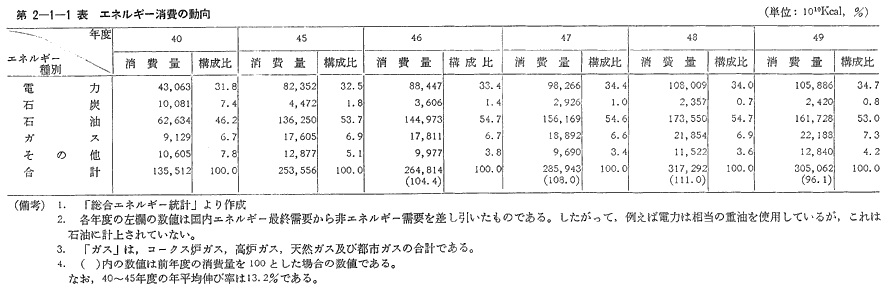
1 最近における大気汚染の特徴
(1) エネルギー消費及び発生源等の動向
大気汚染と密接な関係のあるエネルギー消費の最近における推移は、第2-1-1表のとおりである。昭和40年度から45年度にかけては、年平均13.2%の伸び率で増加してきたが、46年度以降伸び率は若干低下し、49年度は逆にマイナスに転じている。
固定発生源であるばい煙発生施設、粉じん発生施設の届出数を見ると、後掲第2-2-1表のとおり、いずれも毎年度増加が見られる。
また、自動車について見ると、保有台数は毎年度著しく増大している(第2-1-1図)が、走行台キロで見ると49年度は逆に減少している(第2-1-2図)。
以上の動向を踏まえ、発生源(固定及び移動)からの汚染物質の負荷量を大胆な仮定の下に推計すると、硫黄酸化物は、硫黄分に換算して、42年度は約200万トン、45年度は約260万トンであったが、47年度には42年度に比べて石油消費量が倍増したにもかかわらず、重油脱硫をはじめとする燃料の低硫黄化、排煙脱硫等の対策の効果によって約220万トンに減少している。一方、窒素酸化物の負荷量が、二酸化窒素に換算して42年度の約150万トン、45年度の約200万トンから47年度には約230万トンと増大している。
(2) 最近における大気汚染の状況
まず、硫黄酸化物については、43年度以降着実に改善が進み、49年度においては約7割の測定局が環境基準を達成するに至っている。
ばいじん、一酸化炭素についても改善が進んでおり、特に、一酸化炭素については一般生活環境における測定結果では全測定局で環境基準を達成しており、著しい改善を示している。
一方、窒素酸化物については、悪化の傾向は止まり、一部では改善の兆しが見られるものの、いまだ顕著な改善傾向が見られるまでには至っていない。窒素酸化物を原因物質の一つとする光化学大気汚染については、注意報の発令回数で見ると48年をピークに減少しているが、関東では改善の傾向は見られない。窒素酸化物とともに光化学大気汚染の原因物質である炭化水素については、自動車排出ガス規制の強化によって、自動車排出ガス測定局では改善されているが、一般環境大気測定局では改善は見られていない。