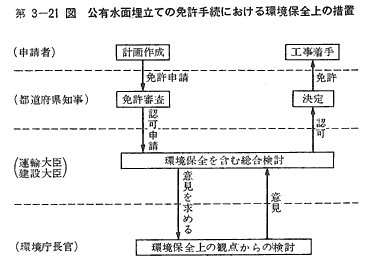
2 環境影響評価の制度等の体制の整備
前述のような住民の動向に対処し、環境悪化を未然に防止するため、各種の開発行為等環境に著しい影響を与えるおそれのあるものについては、それが環境に与える影響を事前に予測し、環境への影響をあらかじめチェックする環境影響評価の制度等の体制の整備を図らなければならない。
我が国においては、昭和30年代後半頃には既に大都市において大気汚染や地盤沈下等による生活環境の悪化が深刻化してきたほか、コンビナート周辺地域では、公害による住民の健康被害が発生する例も見られることとなったこともあり、前述のように地域住民の側にコンビナートの進出等地域開発に反対する動きが生じてきた。その背景として、一般に従来の地域開発等においては、地域の地理的特性、自然条件等のバックデータの不足、環境汚染物質による環境影響と環境受容能力に関する調査不足等多くの要因から、様々な環境問題を引き起こしたことが考えられる。
このような状況にかんがみ40年には、今後大規模な開発が予定される地域については、事前調査を計画的に実施していくこととされた。
これは、現在では「工場立地法」に基づき通商産業省で産業公害総合事前調査として大規模工業開発地域等において実施されており、立地企業の指導、地方公共団体の地域開発計画策定のための基礎資料の提供等公害の未然防止のための施策に資している。
また、道路、港湾の建設等公共事業の実施についても、環境に与える影響を事前に十分チェックしておくことの必要性の認識が高まり、47年6月には、各種公共事業に係る環境保全対策についての閣議了解が行われ、国又は政府関係機関等は、道路、港湾、公有水面埋立等の各種公共事業の実施に当たっては、計画の立案、工事の実施等に際し、公害の発生、自然環境の破壊等環境保全上重大な支障をもたらすことのないよう今後一層留意するとともに、当該公共事業の実施主体に対しあらかじめ必要に応じ環境に及ぼす影響の内容や程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討等を含む調査研究を行わせ、その結果を徴し、所要の措置を採らせる等の措置を行う旨決定された。
これに基づき、運輸省、建設省及び農林省等においては、それぞれ所管公共事業の実施に当たって、各種環境影響調査を一層拡充、強化するとともに、公共事業の実施に係る環境影響評価手法の開発等に努めている。
更に、48年の第71回国会においては、開発等に伴う環境影響についてのチェックの徹底化を図るため、以下に述べるような関係法令の制定、改正が行われた。
まず、河川、海域、湖沼等の埋立てを行うに際しての免許申請手続等を規定した「公有水面埋立法」を一部改正し、埋立免許を付与する場合の条件に埋立てが国土利用上適正かつ合理的であること、環境保全及び災害防止につき十分配慮したものであることを加える等の措置を講じるとともに、埋立免許の申請があった場合、埋立工事内容等を記載した申請書及び関係図書を3週間公衆の縦覧に供し、これに対して埋立てに関する利害関係者は意見書を都道府県知事に提出できることとしたことが挙げられる。このほか埋立面積が50haを超えるもの及び環境保全上特別の配慮を要するものについては、主務大臣(建設大臣又は運輸大臣)が認可をするに際して環境保全上の観点から環境庁長官の意見を求めることとしている(第3-21図参照)。
また、瀬戸内海地域について、環境の一層の悪化を防止し、環境を保全するため「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が制定された。同法では、工場又は事業場が汚水又は廃液を排出する特定の施設の許可を申請する際、当該施設による排出水によって予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲等についての事前調査に基づく評価報告書を提出することが義務付けられている。
ここでは、環境影響評価報告書は3週間公衆の縦覧に供され、これに対して利害関係を有する者は意見書を提出できることとなっている。
このほか、「工場立地法」を一部改正し、大規模な工場又は事業場の設置が集中して行われると予想される地区及びその周辺地域については、工場立地に伴う公害の防止に関する調査を実施し、その結果等に基づき工場立地に伴う生産施設、緑地、環境施設の敷地面積に対する割合等を示す準則を公表することとされた。なお、本調査は、先に述べた産業公害総合事前調査として実施されているものである。更に、通商産業大臣が指定する地区内において同法で規定する特定工場の新設等を行う場合に届出を行う際、大気又は水質に係る公害の原因となる物質の最大排出予定量並びに予定量を超えないこととするための燃料及び原材料の使用に関する計画等についても資料の提出を義務付けることとした。これに対し、当該特定工場からの汚染物質の排出が、周辺特定工場からの汚染物質の排出と重合して公害防止に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、国は、同法で規定する特定工場の設置場所について勧告等ができることとなっている。
なお、このほか、河川計画、港湾計画、土地利用基本計画における開発保全整備計画等環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業、計画等について環境保全の観点から検討が行われており、その数もかなりに上っている(第3-22表参照)。
このように、我が国においては、各種公共事業、大規模開発等の事業の実施に際しては、それが環境に及ぼす影響についての予測及び評価が従来より行われている状況にあるが、制度面から見れば、現状においては、法令により環境影響評価の実施を義務付けている分野は一部に限られており、その場合も評価手順等が十分整備されていないものもあるほか、予測及び評価の結果について、地域住民、専門家等の意向をは握する体制も必ずしも十分でない。
環境影響評価を実施するに当たり、必要に応じ、環境に対する地域住民等の知見を聴取するとともに、環境について、地域住民等がどのようなニーズを有しているかを知ることも重要であると考えられる。
中央公害対策審議会では、このことにかんがみ、同審議会環境影響評価制度専門委員会において、諸外国の制度の研究、我が国における事例の研究、各界の意見聴取等を行いつつ検討を重ねた結果、50年12月に「環境影響評価制度のあり方」について検討結果の取りまとめが行われた。
目下、この取りまとめを中心に、同審議会環境影響評価部会において、更に検討が続けられているところである。
以上のほか、環境影響評価の制度等の体制の整備を図るため、次のような点について施策を推進していく必要がある。
第1は、環境影響の予測方法の研究開発の一層の推進である。環境影響評価を効果的に行うためには、特に、地域開発、空港や道路の建設等の公共事業、発電所の新増設等事業の種類や事業の実施地域の特質等に応じて、今後とも予測手法について研究開発を一層強力に推進し、その確立、精度向上に努めることが基本的に重要である。
第2には環境影響評価に必要な諸データの整備の一層の拡充である。より正確な環境影響の予測には基礎的データの収集整備の拡充強化及びその管理の徹底を図っていくことが必要である。このためには、環境測定機器の整備の拡充、測定技術の開発、更には環境測定に携わる人材の育成等の施策を一層積極的に促進していく必要がある。
第3に、開発等の実施主体に環境影響を予測・評価し得る能力と機能が十分に備わっていない場合には、予測・評価能力を補完するための対応が要請される。このため、環境影響評価を実施する主体のレベルの向上を図るとともに、量的確保に努めることが必要である。