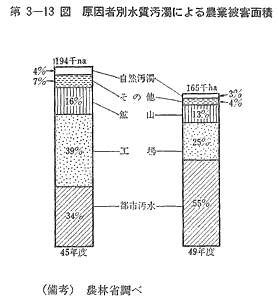
1 物的被害の現状
公害による物的被害の態様は多様である。ここでは、被害の種類を大きく農業被害、漁業被害及びその他の被害に分けて、それぞれについてその状況を概観してみよう。
(1) 農業被害
公害による農業被害は、水質汚濁、土壌汚染、大気汚染、騒音、地盤沈下などの様々な原因から生じている。
水質汚濁(土壌汚染を含む)による農業被害の大部分は水稲の減収として現われるが、その状況は第3-13図に示すとおりである。
これによると、49年度に水質汚濁による農業被害を受けた面積は165千haであり、45年度と比較して約15%の減少となっている。これを原因者別に見ると、都市汚水によるものが92千haで最も大きく、全被害面積の55%に達しており、工場排水がこれに次ぎ、その被害面積は全体の25%に当たる41千haとなっている。45年度と比較すると、都市汚水による被害面積が41%増加したのに対し、工場排水による被害面積は47%の減少となっている。45年度に被害を受けた地域のうちで、農用地が他に転用された面積13千haを除き、49年度に被害が解消した面積は78千haであったが、その要因を見ると、公害防除特別土地改良事業、災害復旧事業、鉱毒対策事業等公共事業によるものが60%、汚濁原因者の処置によるものが33%となっている。
他方、45年度以降新たに被害が発生した面積は62千haであるが、その69%は都市汚水によるものであり、これは既成都市の拡大と農村地域の都市化が急速に進んだ反面、公共下水道施設等の整備が遅れていることによる影響が大きいと見られる。
土壌汚染によるカドミウム汚染米(米中のカドミウム濃度が1ppmを超えるもの)被害は、毎年約千トン前後に上る。
汚染米の発生が特に多いのは、秋田県及び山形県を中心とする東北地方と富山県を中心とする北陸地方であり、これらの地域における汚染米発生の原因は、主として鉱山から永年にわたって排出されたカドミウムが土中に蓄積され、米に吸収されたことによるものである。鉱山の中には、既に事業を行っていないものもあり、これら休廃止鉱山が汚染源となっている場合には、被害者の救済に関し問題となることが多い。汚染米の原因者としては、鉱山のほか特定の工場なども挙げられる。
大気汚染による農業被害としては、ばい煙、硫黄酸化物、光化学スモッグ、ふっ素等による農作物の生育阻害、病変、枯死等がある。これらの被害の中には、岡山県水島地区においてコンビナートからの硫黄酸化物により大量のい草が先枯れした例に見られるように、多額の被害が発生した事例もあるが、多くの場合、被害は比較的軽微であり、被害の及ぶ地域も限られている。また、農作物の生育には多くの要因が作用していることから、公害による被害があっても因果関係を明らかにしにくいために、被害として顕在化しないことも多いと見られる。
汚染源としては、特定の工場、事業場等が確認し得る場合が大部分であるが、国道沿いの砂じんによる被害のように原因者が不特定多数のものもある。
騒音による被害としては、牛鶏等の発育阻害や産卵能力の低下等の例がある。地盤沈下による被害としては、排水不良、農業用施設の損傷等の例が挙げられている。
(2) 漁業被害
近年、油濁、赤潮、水銀、PCB等による漁場の汚染が生じ、多額の漁業被害が発生しているが、これらは、油濁や赤潮に典型的に見られるような突発的に発生した水質汚濁による被害と、多年にわたって排出された水銀、PCB等の有害物質が魚介類に蓄積する場合のような被害とに分けられる。
49年度において突発的漁業被害は、都道府県からの報告によると、全国で471件発生したが、そのうち被害が明らかになっているものの総額は、第3-14図に見るように、約285億円と見込まれている。
まず、油濁による被害をみると、49年度の被害額は、約260億円と最も多いが、この中には、水島事故による被害額214億円が含まれている。45年度から49年度までの5年間の突発的な油濁による漁業被害(ただし、水島事故分を除く。)は、総件数で360件、被害額は110億円である。これを原因者別に見ると、第3-15図に示すとおり、発生件数では、タンカー等の船舶によるものが34%、陸上の事業場等によるものが19%、原因者不明が47%であり、被害額では、船舶によるものが66%、陸上施設によるものが8%で、これら原因者が明らかになっているものは、通常当事者間の示談等により解決されているが、原因者不明のものも26%を占めており、被害者救済の観点から問題となっている。
また、海面及び内水面に分けると、被害額の99%は海面で発生しており、内水面での被害は、ごくわずかである。海面での被害は全国的に発生しているが、特に東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海で多発している。
油濁被害としては、このような突発的なもののほか、長期にわたる汚染により油分が魚介類に蓄積され、油臭を生じるような被害もかなり発生しているが、このような被害は、一定の限られた海域で発生し、その原因者も明らかである場合が多い。
油濁による漁業被害の内容は、油の付着による魚介藻類や養殖中ののりの商品価値のそう失又は低下、漁船、漁具等の汚染、漁場の汚染による休漁、漁場の清掃又は防除等多様である。
次に、赤潮による漁業被害は、養殖漁業において特に打撃が大きい。第3-14図で被害額の推移を見ると、47年度は、瀬戸内海東部海域で養殖はまちが大量にへい死したため、74億円にも上ったが、48年度は6億円、49年度は1億円となっている。赤潮は、窒素、リン等の栄養塩類による海水の富栄養化を基礎とし、物理的化学的諸条件が重なって起こるものといわれているが、その発生機構は、科学的になお十分には解明されていない。
また、水銀、PCB等による魚介類の汚染問題は、48年において、いわゆる第3水俣病問題の発生を契機に深刻化し、消費者の不安感によって魚介類の需要が著しく減退したため、漁業者のみならず、水産加工業者や流通業者にも大きな打撃を与えた。
(3) その他の被害
農業及び漁業のほか、一般の生活部門においても種々の公害による様々な被害が発生している。
大気汚染による物的被害としては、屋根の腐食による修繕費、ばい煙によるクリーニング代、スモッグ等で暗くなるための電気代などの増加が挙げられている。このような被害は、特定の汚染源をは握できることもあるが、多くの場合、不特定多数の事業場等からの排出による広域的な大気汚染によるものであり、また、被害の程度も軽微なものが多く、その被害が大気汚染によって引き起こされたものかどうかも必ずしも明りょうでないなど、被害として顕在化しないものが多いと思われる。
騒音による物的被害としては、建築物の防音工事、空調等に要する経費が、また振動による被害としては、建築物、建具等のひび割れ、損傷、耐用期間の短縮などが挙げられる。騒音又は振動の発生源は、建築作業場、工場、新幹線や飛行機などの交通機関等、汚染源が特定される場合が多い。
地盤沈下による被害としては、一般の建築物の破損又はぜい弱化、排水不良等のほか、堤防、護岸、港湾施設、道路、埋設物等公共施設の破損や沈下が挙げられる。建設工事のための地盤の掘削によって引き起こされるもののように原因行為と沈下との因果関係が明りょうに認められるものもあるが、多くは地下水のくみ上げ等により起こされ、地域的にも広範囲に及び、時間的にも長い期間にわたって徐々に現れる性質のものであるため、因果関係の認定が著しく困難である。
以上のように、公害による物的被害は、農業、漁業等の生産部門とその他の生活部門において、多種多様にわたっている。まず、被害の程度を見ると、生業被害の中には、油濁、赤潮等による漁業被害やカドミウム汚染米のように被害者の生活の基礎を脅かすようなものがある一方、一般生活被害の中には、クリーニング代の増加など軽微なものも多い。次に、原因者の特定可能性を見ると、個々の原因者が特定できるもの、グループとしてとらえることが可能なものがある一方、原因者が全く不明であったり、科学的に原因が十分解明されていないため原因者グループをとらえることが難しいものもある。また、原因者が特定できる場合であっても、既に存在しなくなっていたり、賠償のための資力がないものもある。