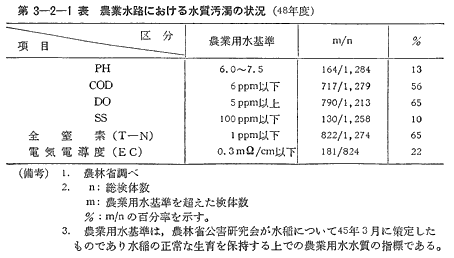
3 農業被害
(1) 農業被害の現況
農業用水の汚濁は、近年の社会、経済の発展に伴う工業化及び都市化地域の拡大、更に生活様式の高度化により、量的にも質的にも悪化の傾向を強め、これによる農業被害がますます増加している。すなわち、農業用水の汚濁は、農作物への直接被害のほか、土壌の理化学性の悪化による土地生産性の低下及び農村環境の悪化をもたらし、農業生産の安定及び環境保全の両面から重要な問題となっている。
水質汚濁による農業被害の現状は、昭和44年度及び45年度に実施した調査によると、全国で被害地区は約1,500地区、被害面積が我が国水田面積の約5.7%に相当する約19万4千haであり、汚濁源別に見ると工場排水が全体の39%、都市排水が34%となっている。
また、水質汚濁により農業被害が発生している地区について、水質汚濁の概況をは握するため、46年度から都道府県に助成して農業用水水質調査を実施してきたが、48年度調査結果によると、第3-2-1表のとおり、全窒素、COD、DOが多くの地区で農業用水基準を超えていた。
(2) 被害発生の態様と汚濁の形態
水質汚濁による農業被害の発生態様は、その汚濁物質の種類及び程度により異なるほか、農作物の種類、品種、生育時期、肥培管理の方法等によっても異なり、更に.農作物が土壌を媒体として生産されるため、その実態を正確には握することは容易ではない。
一般には、パルプ工場、でん粉工場等の排水及び都市排水に含まれる有機物や窒素の過剰等により、土壌の理化学性の悪化、水稲の過繁茂倒伏等が生じ、収量の低下・不安定化、品質の悪化等の被害が発生する。また、化学工場や鉱山の無機排水の水素イオン濃度及び有害金属によっても、被害が発生している。
農業用の汚濁の形態は、河川及び湖沼へ流入した排水が農業用水路へ流入することによる場合が34%、農業用水路、ため池等へ直接流入することによる場合が32%、両者の複合の場合が33%となっている。