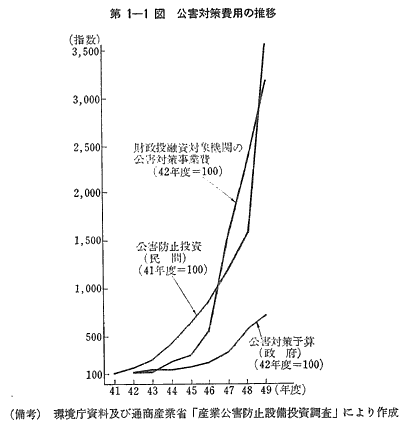
3 環境庁の設置と環境行政の進展(昭和40年代後期)
第3の時期は環境庁の設置以降の時期である。
(1) 環境庁の発足
40年代の半ばには前述のような公害法制の整備が進む一方、公害行政を総合的に実施する行政主体の設置が望まれるに至った。その当時、諸外国においても1967年にはスエーデン、1970年にはアメリカ、イギリス、1971年にはフランスがそれぞれ環境担当省庁を設置する等、環境の保全という見地から行政を推進するための省庁の設置が相次いで進められた。こうして、我が国においても、46年には、これまで各省庁において個別的に行われてきた環境行政を調整し、総合的、積極的に推進すべく環境庁が設けられるとともに、環境庁の附属機関として国立公害研究所及び公害研修所の設置が決定され、環境科学研究の推進及び地方公共団体の公害担当職員等の養成訓練の推進が図られることとなった。
(2) 環境保全関連予算の増加と企業の公害防止設備投資の増加
公害国会を通じて体系的に整備された公害行政は、この時期に入ると、逐次強化され、国の公害対策関係予算は49年度には3,036億円と44年度に比べ5年間で5倍強となり、また、規制の実効を確保するための立入検査件数は、48年度において、大気関係では7万4千施設、水質関係では4万8千件に上っている。また、企業においても、規制の強化に対応して公害防止のための努力が強められ、企業の公害防止投資は飛躍的な増加を示し、資本金1億円以上の1,356社の49年度の投資実績見込額(49年9月調査)は1兆188億円で44年度の9.5倍となった(第1-1図参照)。
(3) 環境問題の多様化等
以上のような対策の進展を反映して、硫黄酸化物、一酸化炭素による大気汚染や地方の大河川における水質の汚濁等一部の汚染因子については改善の傾向が見えてきたが、一方、窒素酸化物や光化学スモッグ等による大気汚染が深刻化し、水質汚濁についても大都市内及びその近郊河川の汚濁はなお著しい。このほか内湾や湖沼において富栄養化といった問題が進行しつつある。また、48年には熊本大学水俣病研究班の発表を契機に水銀等による蓄積性汚染が広域化しているのではないかということが問題となった(いわゆる「第3水俣病問題」)。
更に、PCBに代表される難分解性の化学物質を使用した製品やプラスチックのような製品が、いったん消費者の手に渡りその後の使用あるいは廃棄の過程を通じて環境の汚染をもたらすという新しいタイプの汚染現象が問題化しており、また、企業や家庭から生ずる廃棄物についても46年には約8億トンが排出される等その量が膨大化してきており、その適正な処理は環境保全上重要な問題となってきている。
このほか、従来、主として民間の企業活動から発生する汚染が問題とされたのに加えて、飛行場・道路等の建設、公有水面の埋立て、ごみ処理施設・し尿処理施設等の設置や航空機、新幹線等公共的な事業に伴う汚染の問題についても強い関心が払われるようになった。高速輸送機関等を巡り差止めを求める訴訟が提起されていることは、その典型的な表れである。こうして、環境問題は、これまでの規制手法のみでは十分に対応しきれない複雑化の様相を示している。
このような環境汚染の進行は、国民の認識にも大きな変化を与え、これまでの高度経済成長に伴うマイナス面が増加するにつれ、経済成長に対する肯定的評価が減少してきている。総理府の世論調査によれは、経済成長に否定的評価をする層が46年の14%から49年には24%と増加し、49年には否定的評価が肯定的評価を上回るに至った(第1-2図参照)。また、公害と自然破壊の深刻化は、人類が生存するうえでの必須の基盤としての生態系の維持の重要性を認識させるに至ったが、自然環境が重要とされる理由についての世論調査の結果を見ると、46年には自然の有する情緒的側面を強調するものが最も多かったのに対し、48年には生態系的側面を強調する意見が最も多くなっている(第1-3図参照)。これらは、国民の間に、これまでの量的な拡大を中心とする経済成長のあり方に対する疑問が広まるとともに、人類の生存は自然との共存なくしてはあり得ないとする新しい価値観が生まれてきていることを示すものといえよう。
以上のような国民の環境問題に対する認識の変化を背景に40年代半ばには環境破療に反対する住民運動も著しい高まりを見せてきた。公害に関する住民団体数を見ると、45年には、292団体であったものが49年には1,249団体と4倍以上にも達している。
また、イタイイタイ病、新潟水俣病、四日市ぜん息、熊本水俣病を巡るいわゆる四大公害裁判は46年から48年にかけて相次いで判決が言い渡され、いずれも患者側が勝訴したが、その内容は、因果関係の判定方法に疫学的方法を採用するとともに、企業に対し、人の生命及び健康に係る被害を未然に防止すべき高度の注意義務を明確にし、その不法行為責任を認めるものであり、企業は立地に際し事前にその影響を総合的に調査研究すべきであるとされた。
(4) 環境行政の新たな展開
このような状況に対応し、環境行政は、環境庁設置後新たな展開を見せることとなった。
ア 健康被害救済の強化
47年には大気汚染及び水質汚濁について、いわゆる無過失責任法を制定するとともに、48年には民事的解決が困難と見られる健康被害者の速やかな救済を図るために、「公害健康被害補償法」が制定され、訴訟に待つことなく補償給付を受けることのできる制度が確立された。
イ 環境汚染の未然防止の充実
また、環境行政は、環境汚染の未然防止を図るために事前的対応策の充実にも努めてきている。
産業公害を未然に防止するため、大気と水質について総合的な調査を実施する産業公害総合事前調査は40年から行われてきていたが、47年には、各種公共事業の実施に伴う環境保全上の問題を引き起こすことのないよう、これらの事業を進めるに当たり事前に環境に対する影響を調査し、評価する環境影響評価を行う旨の閣議了解がなされ、その後この了解に従って環境影響評価を必要に応じ実施するとともに、その手法についても調査研究が進められてきた。また、48年には「瀬戸内海環境保全臨時措置法」の制定や「公有水面埋立法」の改正等により、瀬戸内海沿岸に立地する工場の特定施設の許可や埋立免許の申請等に当たっては、環境影響評価が義務付けられることとなるとともに、「工場立地法」の制定によって産業公害総合事前調査が法的に裏付けられることとなった。
一方、PCB使用製品が広く利用され、その消費、廃棄を通じ環境を汚染し、難分解性、蓄積性のゆえに、食物連鎖を通じて魚介煩に濃縮されてきたというPCB問題の教訓を踏まえて、48年には新規の化学物質について難分解性の性状を有し、環境を汚染し人の健康を害するおそれがないかどうかを事前に検査し、製造、輸入、使用等の規制を行う「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定され、既存の化学物質についても環境保全上万全を期すべく、49年度より環境中における追跡調査が開始されている。
なお、48年には、いわゆる第3水俣病問題等を契機として、環境庁長官を議長とする水銀等汚染対策推進会議が設置され、その決定に基づき、水銀、PCBの全国環境調査の実施、健康調査の実施、苛性ソーダ工場のクローズドシステム化、隔膜法への転換、漁獲自主規制の指導、被害漁業者及び関連中小企業者に対する長期低利融資等の措置が採られた。なお、有明海、徳山湾沿岸の漁民等の健康調査の結果、過去に水俣湾で海上生活をしていた1名を除き、現時点では水俣病と診断できる患者は見いだせないと判断された。
ウ 環境基準の設定強化等
46年に航空機、鉄道を除く一般的な騒音に係る環境基準、48年には航空機騒音に係る環境基準が設定され、大気汚染についても、48年に二酸化硫黄に係る環境基準の強化と二酸化窒素、光化学オキシダントに係る環境基準の設定が行われた。なお、硫黄酸化物については抜本的な汚染の改善を図るため、総量規制方式が導入されることとなり、49年6月に「大気汚染防止法」が改正された。
エ 環境関連社会資本の整備
環境保全のための社会資本の整備についても、46年には、第3次下水道整備5箇年計画が策定され、事業規模が第2次計画に比ベ2.8倍に増加するとともに、47年には都市公園等整備5箇年計画が策定された。
オ 自然環境の保全
環境庁の発足は、公害問題と自然保護問題を併せて広く環境問題としてとらえ、有機的に環境保全行政を推進しようとする動きの表れでもあった。公害問題の解決のためには、生態系の保護としての自然環境の保全を図ることが不可欠であるとの認識の下に、自然保護行政が環境行政の中に位置付けられることとなった。
自然保護問題が初めて公に論議されたのは明治44年になされた衆議院における国設大公園設置の建議並びに貴族院における史蹟及び天然記念物保存に関する建議についてである。しかし、これらが行政施策として具体化されるにほかなりの時日を要し、自然保護法制が最初に制定されたのは、大正8年の珍しい湿源や稀少となった雷鳥等の野生鳥獣の保護のための「史跡名勝天然紀念物保護法」の制定であった。また、昭和6年には、アメリカのナショナル・パークの制度に範をとった「国立公園法」が制定され、これらが日本における自然保護行政の源流といえよう。
「国立公園法」に基づき、昭和9年に瀬戸内海、雲仙、霧島が初めて国立公園に指定されたが、この制度は、景観という側面から自然をとらえてその保護を行うとともに、併せて適正な利用の推進を図ることをねらったものであった。国立公園の指定はその後も推進されたが、昭和30年代に入ると、単に国立公園のみならずそれに準ずる優れた風景地についても保護利用を図ることが必要であるとの声が高まり、これを受けて、32年に「国立公園法」の改正が行われ、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種の自然公園を制度化した「自然公園法」が制定された。こうして我が国の風景地についてそれぞれの特性に応じた適正な保護と利用の推進が図られることとなり、自然公園制度の確立を見た。
30年代以降を通じて国立公園の利用者数は著しい上昇を示し、48年においては実に3億4千万人を数え30年の7倍に上った(第1-4図参照)が、利用者数の増加に伴い、近年では公園内の広場、道路等がごみ等によって汚されたり、増加する宿泊施設から排出される汚水等によって湖沼や湿源の水質が汚染される等の自然環境の破壊が問題となってきている。また、都市地域では汚染や都市化に伴い、身近な緑が失われ、トンボ等の昆虫や野鳥が減少し、その他の地域でも別荘、ゴルフ場の造成や観光道路の開発等による自然の破壊が進む等全国的な規模での自然破壊が進行していった。
こうしたなかで、46年の日光国立公園尾瀬地区の道路建設問題に見られるように自然保護運動が高まりを見せ、自然保護団体数は47年には700団体を超え、自然破壊行為に対して告発を行うケースも見られるに至った。49年6月には自然保護憲章制定国民会議の論議を経て「自然保護憲章」が制定されたが、諸外国において、同様な性格を有するものとしては西独の「緑の憲章」が存在するのみであり、我が国の自然環境破壊の現状にかんがみ、市民の自発的意志によって制定されたこの憲章は高く評価されよう。また、地方公共団体においても、自然を保護するための各種規制を織り込んだ条例が相次いで制定されている。
こうして、昭和40年代の後半には、公害問題と併せて、自然環境についても、その破壊が今や放置し得ない段階に達しているとの認識が強まり、国においてもこれまでの優れた景観地の保護という見地を超えて全国の自然環境を積極的に保護保全するための基本法の策定を進め、47年に「自然環境保全法」が制定された。これにより、生態系の保持という新しい角度から、各種の自然環境保全のための施策が「自然環境保全法」を中心に総合的に推進されることとなり、48年には「自然環境保全法」に基づく自然環境の保全に当たっての政府の基本的構想である「自然環境保全基本方針」 が閣議決定され、自然が豊かな人間生活の不可欠な要素であるとの認識の下に我が国の自然環境保全のあり方が示された。また、都市における自然の保護については、従来からの風致地区制度、歴史的風土保存区域制度等に加え、48年には「都市緑地保全法」が制定され、都市における緑地の保全及び緑化の推進のための制度が整備された。
カ 国際協力
環境問題に関する国際的な関心も1970年以降大きな高まりを見せてきている。
この背景には、太平洋等の海洋に油、プラスチック等の廃棄物が漂い、ライン川等の国際河川の汚濁が進み、北欧では他国の工業地帯で排出された亜硫酸ガス等のために酸性の雨が降ることに見られるような大気、河川、海洋における環境汚染の世界的な進行があったことや、ローマクラブの「成長の限界」のレポートに見られるように、環境問題を広く人口、資源、人類の発展との関連からとらえようとする動きがあったといえよう。
1970年7月にOECD(経済協力開発機構)に環境委員会が設立され、先進工業国間での環境問題解決のための国際協力が進められることとなり、また、日米間においても、同年10月に行われた「公害に関する日米会議」の結果、環境問題に関する閣僚レベルの定期的会合が開催されることとなった。
更に、1972年6月には、4年にわたる準備期間を経て、ストックホルムにおいて国連人間環境会議が世界114か国の参加の下に開催されるに至った。この会議は、発展途上国をも含めた世界各国が「かけがえのない地球」を守るべく環境問題を人類共通の課題として対処しようと集まったグローバルなレベルでの最初の会議であり、「人間環境宣言」及び109の勧告が採択された。宣言においては、「我々は歴史の転回点に到達した。今や、我々は世界中で、環境への影響に一層の思慮深い注意を払いながら、行動しなければならない。」と述べられており、人間環境の擁護が、世界の平和、経済社会の発展と並んで人類にとっての至上の目標の1つとして追求されるべきことが国際的に合意された。OECDの環境委員会においても活発な活動が行われ、1972年5月の理事会では汚染者負担の原則(PPP)と環境基準の国際的調和を主たる内容とする「環境政策の国際経済的側面に関するガイディング・プリンシプル」が採択された。
また、1974年11月にはOECD環境担当閣僚会議がパリにおいて開催され、「環境政策に関する宣言」及び10項目にわたる「行動計画」が採択され、環境の改善のためエネルギー問題、土地利用、都市問題等を含めた総合的な政策を促進していくことについて、加盟諸国の決意が表明された。
更に、自然保護の面では、日本の野鳥の約80%が渡り鳥であることから、国際協力を通じてその保護を図ろうとする努力が払われ、47年の「日米渡り鳥条約」を最初に、日ソ、日豪間で協定が調印されたことが特筆される。
以上のような国際協力の進展の反面、日本のタンカーによる油汚染の問題、タイのメナム川汚濁問題に見られる海外進出企業による公害問題や、国連海洋法会議等における環境汚染に関する開発途上国からの先進工業国に対する批判等環境を巡る国際的な摩擦も強まっており、我が国としても国際的な視野に立って豊かな人間環境を確立すべく、積極的に行動していくべき局面に達しているといえよう。