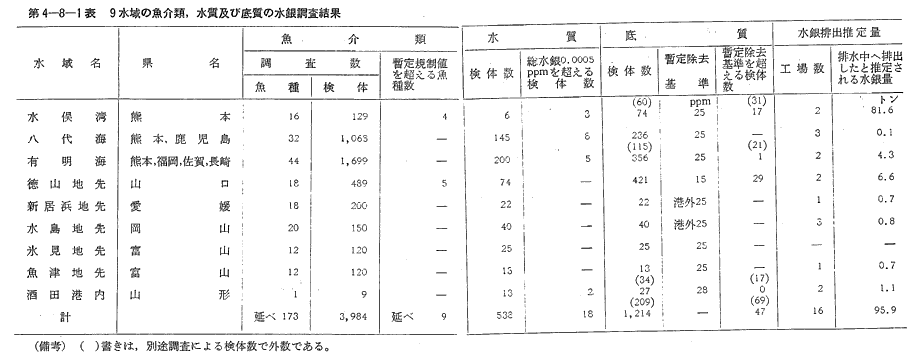
1 水銀汚染
(1) 経緯
48年5月22日、かねてから熊本県が熊本大学医学部10年後の水俣病研究班に委託していた研究の報告がなされ、有明海周辺に八代海と汚染源を異にする水俣病が発生している疑いがあることが指摘され、水銀による汚染が広域化していることが問題となった。
政府は、これを契機に水銀等汚染問題について、関係各省庁の有機的な連携のもとに早急に解決を図るため、環境庁長官を議長として関係省庁の局長級からなる水銀等汚染対策推進会議の設置を48年6月12日の閣議で決定し、以後3回にわたって会議を開き、その都度、各種の対策を決定し、これを強力に推進してきた。すなわち、第1回の会議においては、魚介類の安全基準の設定、工場に対する点検、規制、漁民等に対する救済、ヘドロ除去対策、環境調査及び健康調査の実施等を決めた。魚介類の水銀の暫定的基準が定められたことに伴って開かれた第2回会議では緊急に調査を要する9水域(水俣湾、八代海、有明海、徳山地先、新居浜地先、水島地先、氷見地先、魚津地先、酒田港内)をあげて、これら水域に係る魚の産地市場の監視、水銀使用工場の点検、クローズドシステム化の繰上げ等を決めた。また、9水域の環境調査結果評価の後開かれた第3回会議においては、今後も環境調査等を継続していくこと等を決定した。
(2) 水銀汚染対策
ア 魚介類の水銀の暫定的基準の設定及び監視体制の強化
水俣病が、水銀を含んだ魚介類を摂食することにより発生するものであることにより、魚介類の安全性に対する国民の不安が高まった。
このため厚生省は魚介類の水銀に関する専門家会議を設置し、検討を重ねた結果、48年6月24日「魚介類の水銀の暫定的基準」について意見を得た。この意見に基づきメチル水銀の暫定的摂取限度を成人1週間当たり0.17mgとし、魚介類の水銀の暫定的規制値として、総水銀0.4ppm、かつメチル水銀0.3ppmと定めた(この暫定的規制値の適用に当たっては同一魚種について体長に応じ3〜10尾を1検体として測定することとしている)。
この基準に従って、各都道府県の流通市場における検査体制の強化を図り、緊急に調査を行うこととされた9水域の産地市場を重点に検査を行い、48年7月、8月及び11月にその結果を発表した。これによると、漁業の行われていない水俣湾、徳山地先を除く7水域の産地市場の取扱魚の水銀濃度はいずれも規制値以下であり、流通市場においては一部魚種について規制値を超えるものがあったが、これらについては入荷を停止する等の措置が講じられた。
イ 環境調査の実施
? 概況
環境調査については、これまでの各種の調査で高濃度に水銀を含有した魚介類が発見された水域や水銀取扱工場及び水銀鉱山の周辺水域等について全国的に魚介類、水質及び底質の調査を行った。特に9水域については、48年11月までにその調査結果がとりまとめられ公表された。なお、その他の水域については調査結果を取りまとめ中である。また、有明・八代海域については、潮流、潮位、水温、塩分等の実地調査をはじめとする海象調査を実施した。
以下9水域の調査結果についてその概要を述べる。
? 魚介類
まず、魚介類調査は、第4-8-1表のとおり延べ173魚種、総検体数3,984について行われた。このうち水俣湾の16魚種中4魚種、徳山湾の18魚種中5魚種が暫定的規制値を超えていた(「暫定的規制値を超える場合」とは、同一魚種について原則として10検体、最低5検体の魚介類の総水銀含有量の平均値が0.4ppmを超え、かつ、メチル水銀含有量の平均値が0.3ppmを超えるものをいう)。これらの9魚種については、漁獲自主規制を行うほか、これら水域の底質の除去及び水銀含有廃棄物の適正な処理等の環境浄化対策を早急に行う必要があるとされた。その他の魚種は、暫定的規制値を下回っているので、漁獲、販売、食用しても安全であると判断された。
ただし、魚介類が暫定的規制値を下回っている水域にあっても底質中の水銀含有量に問題があり、底質除去等の浄化対策を必要とするとされた地域(酒田港内)については、今回調査できなかった魚種も含めて引き続き調査監視を行うこととされた。
なお、魚介類の魚種別平均総水銀濃度の分布をみると、0.10ppm未満が75%、0.10〜0.20ppmが16%、0.20〜0.30ppmが6%、0.30〜0.40ppmが1%、0.04ppmを超えるものが2%となっている。
? 水質
水質調査は、538検体について行われた。総水銀については、現行JIS法による検出限界値(0.0005ppm)を超えたものは総検体数の3.3%、18検体であったが、全体として問題はないものと判断された。
その理由は、0.0005ppmを超えるものは主として底質中の水銀含有量の高い水域で検出されていることから、底質中の水銀が溶出したものもあろうが、むしろ水銀を含有する底質がけん濁したものや水銀を濃縮したプランクトン等を測定したことにもよるものであろうと推察されるためである。
? 底質
河川及び海域等の水底に蓄積した有害物質の除去基準については、総水銀について中央公害対策審議会の答申を得て定められ、48年8月31日に「水銀を含む底質の暫定的除去基準」として各都道府県に通知された。
底質調査は、1,214検体について行われた。その結果、水域ごとに定められる底質の暫定除去基準値を超えるものが47検体(全体の3.9%)あり、水俣湾のほぼ全域、徳山湾内及び酒田港内の一部のほか、有明海、富山湾の流入河川等の関連水域の一部においても検出された。これら水域の底質については、早急に除去対策等を講ずる必要がある。
以上の調査結果に基づき、魚介類の継続的な監視並びに底質の暫定除去基準値を超える底質の除去対策を早急に行うとともに排水及び廃棄物の適正な処理を行うこととした。
ウ 健康調査の実施
? 概況
48年5月有明海に面する熊本県有明海において、水俣病様患者が10人見出され、「現在の魚類メチル水銀含有量からの発症は考えにくいが、疫学的調査から有明地区の患者を有機水銀中毒症とみうるとすれば、過去の発症とみるとしても、これは第2の新潟水俣病に次いで、第3の水俣病となり、その意義は重大である」との熊本大学報告書が発表され、また、徳山湾においても水俣病様患者が6人見出されると指摘された。
このため、国は、有明海沿岸の福岡、佐賀、長崎、熊本4県及び徳山湾を抱える山口県と協議して沿岸住民約9万7千人を対象に健康調査を実施することとなった。
? 健康調査方式の設定
この健康調査は、第一次、第二次の検診によってスクリーニングを行い、第三次検診として精密な専門医による各科診察を行うという方法で実施している。
有明海及び徳山湾の健康調査は、49年に入って第三次検診を実施中であるが、3月末までには各県とも最終評価を行う予定で進めているところである。
? 健康調査の結果判定
問題の発端となった有明海の10人のうち2人については、48年8月17日水銀汚染調査委員会健康調査分科会において検討を行った結果「現時点では水俣病ではない」とされた。
また、徳山湾沿岸において水俣病といわれた6人のうち3人についても山口大学において水俣病ではないとされた。有明町の残り8人及び山口大学でボーダーラインにあるとされた徳山湾沿岸の3人について同分科会において検討することとしている。
なお、健康調査の結果各県において判定の行われ得ない者については、その県の要請に応じて、同分科会が同様に検討することとしており、佐賀県及び福岡県に係る者については、49年3月23日に検討が行われ「有機水銀中毒患者はいなかった」とされた。
エ 研究の推進
48年度における水俣病の研究については、環境保全総合調査研究促進調整費約3,800万円をもって、「メチル水銀の発生機序に関する研究」、「メチル水銀の生体内代謝に関する研究」、「水俣病の治療方法に関する研究」「長期微量摂取の人体影響に関する研究」、「検診方法の確立に関する研究」の5課題についての研究を行うこととし、全国の水銀関係研究者から成る研究班を組織して、この研究班にこれらの研究を委託した。
オ 汚でい処理対策の実施
港湾に堆積している水銀を含む汚でいの処理については、「公害防止事業費事業者負担法」及び「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に定める諸条件が整ったものに対して、47年度から港湾公害防止対策事業として国庫補助を実施しており、48年度は、北九州(洞海湾地区)、大牟田の2港において水銀を含む汚でいの処理に着手した。
水銀含有汚でいの処理に当っては、汚でいの拡散による二次公害を防止する必要があるとともに除去作業が完了するまでの間、定期的監視を継続することが重要であり、今後事業の実施に当たってはこの点について十分配慮する必要がある。
カ 水銀使用工場の排出規制
水銀使用工場の排出規制については、9水域の苛性ソーダ工場については通商産業省の指導により48年9月末、その他の地域の苛性ソーダ工場については48年12月末までにクローズドシステム化を完了した。
なお、隔膜法への転換については50年9月までに所要設備能力の3分の2について終了し、残りについても原則として52年度末までに終了しうるよう引き続き指導していくこととしている。
キ 被害救済対策の実施
水銀等による魚介類の汚染に係る被害漁業者及び関連中小企業者等に対する救済措置としては、水銀等汚染対策推進会議の決定に基づき緊急に長期低利の融資措置をとったが、この措置は第71回国会において制定された「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法」により制度化された。これに基づき、48年12月末までに、漁業者等に約165億円、鮮魚商等に約81億円の貸付けが行われた。また、特別事情を有するまぐろ漁業者及びはまち養殖業者についても別途の措置により長期低利の融資を行うこととし、49年1月末までに約74億円の貸付けが行われた。
ク 漁獲自主規制措置の指導等
魚介類調査の結果に基づき、水俣湾内及び徳山湾内については、暫定的規制値を超えた魚介類について、水域及び魚種を限定して漁獲自主規制措置をとるよう指導したほか、水俣湾については、汚染魚が湾外に回遊しないよう網仕切りを設け、また、徳山湾についても同様の措置をとることを検討している。