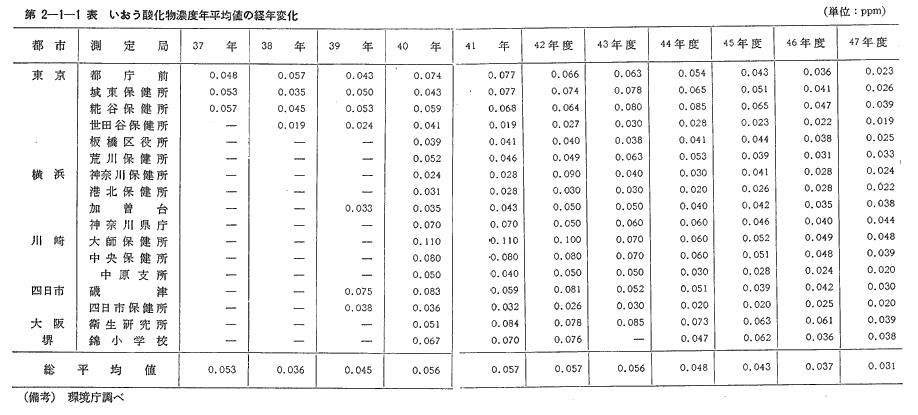
2 汚染物質別の大気汚染状況
(1) 二酸化いおう
ア 汚染状況の推移
大気汚染のなかで代表的な汚染物質である二酸化いおうは、その大部分が化石燃料の燃焼に伴って発生する。化石燃料として石油、石炭等があるが、全国的な見地からは、使用料が膨大な石油の燃焼に伴う二酸化いおうの発生が圧倒的な部分を占めており、我が国における二酸化いおうによる大気汚染の主たる源は石油等に重油中に含まれるいおう分の燃焼酸化に求めることができる。
しかしながら、近年における我が国の重油消費量の増加にもかかわらず、二酸化いおうの濃度は、41〜42年度をピークに減少の傾向を示してきている。特に従来、汚染の著しかった東京、川崎、大阪等大都市地域及び四日市では明らかに減少傾向を示している。(第2-1-1表参照)。これは、大気汚染防止法による規制の強化とこれに対応する低いおう原・重油の輸入量の増大、重油脱硫の実施等の燃料の低いおう化対策及び高煙突化、排煙脱硫等の発生源の設備改善等が徐々に成果を示してきたことによるものである。
このように汚染が改善されているとはいえ、48年5月の改定後の環境基準からみると、全国的になお汚染状況は継続しており、川崎市、名古屋市、大阪市及び周辺都市等の一部地域においては、いまだに48年5月に改定される前の環境基準(以下「旧環境基準」という。)に適合しない高濃度汚染を示している地域があるので、今後更に施策の強化を図っていく必要がある。
? 旧環境基準適否の推移
旧環境基準に基づいて、二酸化いおうによる大気汚染状況の推移を都市別・測定局別にみると第2-1-2表のとおりである。測定局の急激な増加にもかかわらず、旧環境基準不適合都市及び旧環境基準不適合測定局の数は45年をピークにして年々減少しており、特に47年度には大幅な減少がみられる。
? 年平均値の推移
40年に測定を開始して以来、測定場所を変更せず、毎年継続して測定を行っている測定局は17局である。これらの測定局は純然たる工業地域に設置されていたものではないが、いずれも多数の二酸化いおう発生源がある我が国の代表的な汚染地域である大都市に設置されているものである。また、二酸化いおう自動測定局が普及しだした42年度から継続測定を行っている測定局は61局である。
これらについて年度別年平均値の単純平均値をとると第2-1-1図及び2-1-2図のとおりであって、二酸化いおう濃度は年々減少傾向にある。
また、46年度と47年度の2年間継続測定を行ってきた448測定局における測定結果をもとに各測定局の年平均値の増減状況をみても第2-1-3表のとおり改善傾向がうかがわれる。
イ 汚染の現況
47年度において二酸化いおうの測定を行った全国の測定局のうち年間測定時間が6,000時間以上に達した測定局は、248都市、685測定局である。
? 旧環境基準に適合する都市
47年度において、地域内のすべての測定局が二酸化いおうの旧環境基準に適合している都市は236都市である。このうち、前年度は旧環境基準に不適合であったが、47年度に新たに適合することとなった都市は次の21都市である。
青森八戸岩手釜石秋田秋田埼玉草加、戸田東京特別区富山富山、高岡静岡清水愛知東海、一宮三重四日市京都京都大阪吹田、守口、東大阪兵庫尼崎岡山笠岡山口岩国、宇部福岡大牟田
(備考) 環境庁調べ
? 旧環境基準に適合しない都市
地域内の全測定局のうち、旧環境基準に適合していない測定局をもつ都市は12都市であり、全測定局所在都市の5%を占めている。
旧環境基準不適合の都市は次のとおりである。
福島磐梯町(1/2)栃木足尾町(1/1)千葉千葉(1/18)神奈川横浜(1/11)、川崎(3/8)静岡富士(1/7)愛知名古屋(2/14)、刈谷(1/1)大阪大阪(1/13)、豊中(1/2)岡山備前(1/4)福岡北九州(1/11)
(備考)
1. 環境庁調べ
2. ( )内の分母は地域内測定局数、分子は旧環境基準に不適合測定局数を示す。
3. 市町村のうち、市については名称のみ、町村については名称の次に町・村とつけてある。
上記の諸都市のうち、足尾、千葉、豊中、備前は、地域内の新設の測定局が旧環境基準に不適合になったものである。他の都市はすべて前年度に引き続き不適合な都市であり、47年度初めて不適合となった都市はない。
? 環境基準による評価
48年5月に改定された環境基準(以下「環境基準」という。)は1時間値及び1日平均値によって定められているので時間又は日について環境基準適否の評価が可能になっている。しかしながら当該地域の大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するうえからは、年間にわたる測定結果を長期的に観察したうえで評価を行うことが必要であるので、長期的な評価を次のようにして行うこととした。すなわち、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値(例えば365日分の測定値がある場合は高い方から7日分を除いた8日目の1日平均値)が0.04ppmを超えずかつ年間を通じての1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準の長期的評価に適合するものとした。以上の方法で評価した結果を整理すると、第2-1-4表に示すように、およそ3分の2の測定局、都市が不適合と評価される。このように改定後の環境基準は旧環境基準に比べてはるかに厳しいレベルにあり、これを達成するためには今後とも一層の規制の強化を行う必要がある。
環境基準に適合する75都市は次のとおりである。
北海道札幌、旭川、苫小牧、釧路、伊達宮城利府町、塩釜、七ヶ浜町、多賀城秋田天王町山形酒田茨城鹿島町栃木足利、葛生、真岡、栃木埼玉三郷、和光、熊谷千葉柏、銚子、佐原、小見川町東京立川神奈川小田原、秦野、伊勢原新潟豊栄、聖籠村富山新湊石川金沢、津幡町、小松、加賀、七尾福井丸岡町、芦原町、三国町、春江町、金津町、坂井町長野長野、松本静岡清水町、芝川町愛知豊田、小牧、御津町、田原町三重尾鷲京都向日、八幡町、福知山兵庫竜野、稲美町、香寺町和歌山野上町鳥取鳥取島根松江岡山総社、御津町、船穂町山口小野田、下関徳島北島、阿南高知高知福岡苅田町佐賀唐津、有田町長崎大村、吉井町大分臼杵、佐賀関町鹿児島川内
(備考) 環境庁調べ
また、1日平均値及び1時間平均値について47年度中に一度も環境基準値を超えなかった場合を第2-1-5表に示す。
年度を通じて環境基準値を一度も超えなかった35都市は次のとおりである。
北海道伊達宮城多賀城、七ヶ浜町、利府町秋田天王町山形酒田栃木足利、葛生町、真岡、栃木神奈川小田原、秦野新潟豊栄石川金沢、小松、七尾、津幡町福井芦原町、金津町、三国町、坂井町、丸岡町長野長野愛知御津町京都向日、福知山兵庫竜野和歌山野上町鳥取鳥取徳島北島佐賀唐津、有田町長崎吉井町、大村鹿児島川内
(備考) 環境庁調べ
(2) 窒素酸化物
窒素酸化物は一般に一酸化窒素(NO)及び二酸化窒素(NO2)の総称であって、窒素酸化物の環境測定は、一酸化窒素と二酸化窒素をそれぞれ測定し、その測定値を合計したものを窒素酸化物(NO+NO2)として算出している。
ア 汚染状況の推移
窒素酸化物は、物の燃焼に伴って大気中の窒素が酸化されたものが大部分であり、燃焼条件によってその発生量は大きく変化するが、通常、燃焼時200〜2,000ppmの発生は避けられないとされている。したがって、従来年々約10%の石油消費量の増加等の燃料消費量の増加に伴い、窒素酸化物による大気汚染は進行する傾向にあったものと考えられるが、この経過を経年的には握することは、データ収集面での制約があって困難である。しかし、今までに得られた二酸化窒素及び一酸化窒素の測定結果について経年変化を追ってみると、第2-1-6表、第2-1-7表、第2-1-8表のとおりである。
二酸化窒素について、43年度から毎年測定している7測定局について年平均値の単純平均値をとり図示すると第2-1-3図のようになる。また同様に、45年度からデータの得られた11局を加えた18局で経年変化を図示すると第2-1-4図のようになる。
これらの測定局はいずれも大気汚染が著しい地域内にあり、第2-1-3図にみるように年次的に漸増的傾向にある。46年度のデータは45年度のデータと大差なく、汚染も頭打ちにきたのではないかと当時考えられたが、47年度データは増加している。しかし、データが少ないため、川崎、大阪の測定局における急激な濃度増加が平均値に大きく響いた結果ともいえる。
一方、第2-1-4図によって、45年度からの継続測定局18局について各年度における年平均値の単純平均値の経年変化をみると、各年度ともおおむね同じ平均値となり、この場合は頭打ちの傾向がみられる。
46年度と47年度の両年度にわたり同一測定点で得られた23都市33測定局における年平均値の単純平均値をみると、46年度0.0258ppmに比べ47年度は0.0246ppmで、二酸化窒素の値は横ばいを示している。したがって、これらの結果だけでいうならば、二酸化窒素の汚染濃度は45年度頃から増加していないといえる。もちろんエネルギー消費の増加によって、発生総量は当然増加してきていると考えられるから、この環境濃度の横ばいは、測定地点環境の横ばいであって、二酸化いおうのように発生総量の低減化に基づく減少あるいは横ばいとは意味を異にする。
二酸化窒素汚染の広域化等については、データが十分でないのでまだ明確な判断はできない。
イ 汚染の現況
47年度二酸化窒素測定データを有効測定値が得られた全国72都市105測定局の分について整理すると、環境基準の長期的評価に適合した測定局は松江市(国設測定局)1局のみである。
(3) 一酸化炭素
ア 汚染の推移
一酸化炭素による大気汚染の主たる発生源は、自動車の排出ガスである。したがって、その汚染の程度をは握するには、交通量の激しい道路際において一酸化炭素濃度を測定し、その経過をみることが必要である。例えば、都内3か所の道路際の測定局における一酸化炭素濃度は第2-1-9表のとおり39年以来漸増したが、45年には初めて減少し、それ以後は漸減傾向にあることは、自動車排出ガス規制効果が反映しているとも考えられる。
一方、43年度から継続測定を行っている一般生活環境における測定局は、大阪、東京の国設2局である。その測定値の経年変化は第2-1-10表のとおりである。
東京は44年度から減少傾向を示している。一方、大阪は前年度に比べ47年度データが高いが、これは測定局前の道路が大幅拡張され大阪後背地を結ぶ一大幹線道路となった影響とみられる。
同様のことを46,47年度継続して測定を行った4測定局について比較すると、第2-1-11表のとおりである。
これらの結果は、一酸化炭素濃度の下降を示している。
イ 汚染の現況
47年度一酸化炭素測定データのうち、有効測定時間に達している25都市38測定局について環境基準値との関係をみると次のようになる。
環境基準値を一度も超えなかった都市は次の17都市である。
北海道札幌宮城仙台神奈川横浜、逗子、藤沢、厚木、大和、相模原、座間、秦野、伊勢原愛知知立大阪吹田、大阪奈良奈良岡山笠岡、船穂町
環境基準値を少なくとも一回以上超えた都市は次の8都市である。
秋田秋田(1/1)埼玉川口(1/1)東京特別区(1/8)神奈川川崎(1/8)、三浦(1/1)、鎌倉(1/1)愛知一宮(1/1)山口宇部(1/1)
上記の都市のうち、1日平均値の最高値が10ppm以下であって、1時間値の8時間平均値が20ppmを超えていた都市は、神奈川県の鎌倉、川崎、三浦の3都市である。
(備考)
1. 環境庁調べ
2. ( )内の分母は地域内測定局数、分子は環境基準を超えた測定局数を示す。
(4) オキシダント
オキシダントは、光化学反応による大気汚染の状態を示す一つの指標として近年非常に注目されてきている。第2-1-12表は、古くから測定を行っている測定局の年平均値の推移である。
次に45年度から47年度まで継続して測定している測定局の年平均値の経年変化をみると第2-1-13表のとおりである。
(5) 炭化水素
炭化水素は、光化学反応による大気汚染の起因物質の一つとして重要な物質であり、近年になって特に注目されている物質である。
測定値は、各種のガス状炭化水素類を含んだデータであり、その値をいかなる量で示すか我が国ではまだ公式の約束はない。示し方として、ガソリン成分に近いという形でヘキサン(C6H14)に換算する方式、又はプロパン(C3H8)に換算する方式があるが、このほかメタンに換算する方式(カーボン換算ともいう。)も近年多くなってきている。
ここでは、プロパン換算する方式を採用している。
全国的な汚染状況を概観するのにはデータは十分でない。参考として、44年度以前から継続して測定を行っている測定局における年平均値の経年変化についてみると第2-1-14表に示すようにおおむね横ばいで推移してきている。