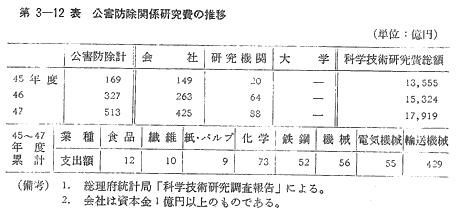
1 公害防止技術研究の現段階
総理府が毎年行っている科学技術研究調査報告によると、我が国の公害防止関係の研究費は、第3-12表のとおり、47年度において総額513億円となり、45年度に比べ約3倍の規模となった。同期間における研究費全体の伸びが30%であったことからみて、この規模の拡大は極めて大幅なものであり、公害行政の進展や国民の認識の高まりを背景に、公害防止の研究に対する努力の跡をうかがわせるものである。
このうち、民間企業による研究費が約8割を占め、国、地方公共団体等の研究機関によるものが約2割となっている。公害防止技術の研究が直接的には当面の汚染の防除を目指している以上、そのための実用化研究が主体となり、民間企業の比重が大きいことは、いわば当然であるが、民間企業の研究費を主要業種別にみると、第3-12表下欄のとおりである。
一般に機械工業の研究支出規模が大きいのは、同産業が公害防止機器の生産を行っていることから当然のことといえるが、特に輸送機械工業の支出規模が著しく大きいのは製造段階の汚染防止よりも、むしろ商品である自動車等の使用に対する公害規制の強化と今後の運輸交通公害対策に対応した動きとみることができよう。もちろん、公害防止技術研究の態様は複雑多様であり、これらの関係を一概に規定することはできないが、今後とも、特に大気、水等の環境資源を大量に消費する業種は、汚染防除のための研究投資を更に促進する必要があろう。
また、公害防止技術の取入れに対する民間企業の努力を海外からの技術導入状況によってみると、第3-13表のとおりであり、その件数は逐年増加し、47年度には90件を数えるに至っている。主な導入技術の種類をみると、ここ8年間の累計では、水質汚濁対策、いおう酸化物対策、はいじん対策の関係技術で全体のほぼ8割を占めているが、近年、自動車排出ガスの対策技術の導入件数もかなりの比重をもつに至っており、ここでも規制強化に対応して民間企業が技術の向上を図っている姿が現れている。
自主開発若しくは海外技術の取入れによって防止技術は次第に向上しているものとみられるが、このことは、これら技術を体化した民間公害防止投資の動向からもうかがわれる。製造業、鉱業、電気・ガス事業の全業種の公害防止投資額(支払ベース)は、48年度(実績見込み)で4,500億円を超えるものとみられ、全設備投資に占める割合は、第3-14図にみるように9.8%程度と見込まれている。この規模は、3年前の45年度の約3倍に当たるものであり、また公害防止投資比率も第3-15図に示すアメリカとの比較においても高い水準に達している。
公害防止技術の研究開発において国が担当すべき分野は、そのプロジェクトが国家的に重要であり、かつ、民間が行うには技術開発のリスクが大きく、その規模も大規模で総合的な研究開発を要するものであるが、これを環境庁に一括計上された国の試験研究機関の試験研究費の中からみてみよう。環境庁一括計上経費は、47年度45テーマ、13億4千万円だったものが48年度には84テーマ、22億9百万円と著しい増加をみているが、48年度84テーマのうち、公害防止技術の研究に関するものはほぼ4割を占めるものとみられる。これらの研究中、無公害自動車の開発、排水処理の高度化及び廃棄物の処理と資源化技術等の研究については、関係試験研究機関の間における組織的協力体制の下に総合研究プロジェクトとして重点的に研究が推進されている。
通商産業省の大型プロジェクトの研究制度によっても、電気自動車の研究開発、高温還元ガス利用による直接製鉄、自動車総合管制技術開発等無公害化を指向した大型の技術開発が現在進められている。また、最近、その重要性を増してきた無公害エネルギーの開発を目指して、太陽エネルギー等の利用に関する研究もサンシャイン計画として推進されている。更に、民間における窒素酸化物防除技術やその他の公害防止技術の研究開発に対する国の助成も重要技術研究開発費補助制度によって行われている。
以上のような国、民間の研究努力により、公害防止技術の開発は近年着実に推進されてきたが、その開発に際し、公害規制の実施強化が大きなモメントとなってきた。四日市市における大気汚染問題を契機とし、いおう酸化物の規制を望む世論の高まりを背景に、規制の実施を可能とする技術を実現するべく国の大型プロジェクトとして脱硫技術開発の研究が41年度から4か年計画としてスタートした。
こうした技術の背景があって、44年の環境基準の設定及び低いおう化対策の実施をみた。研究開発の成果は有効に実用プラントに活用され、47年の通商産業省のアンケート調査によると、我が国の排煙脱硫装置は85基と、まだ十分とはいえないものの世界に例をみない程の多数に達している。
これら脱硫技術の大半は、原理的には海外からの技術導入に頼っているが、その導入技術の実用化を可能にしたのは、上記研究開発による我が国の技術であった。
また、自動車排出ガス中の有害成分を50年度から大幅に低減するという方針に対応し、自動車業界を中心として同規制に適合する低公害エンジンを含む排出ガス対策技術の開発が進められ、既に市販されている自動車もあることは評価に値しよう。自動車については、更に省資源という新課題に対応するため、燃料効率の向上に関する研究も進められる段階にまで至っている。このほか、水質汚濁防止技術の分野においても、有機汚濁物質を含む排水を高度に処理する技術が実用化の域に達し、また、有害金属除去技術についても電解法、イオン交換法、逆浸透法等を中心に実用化研究に入りつつあるのも、水質汚濁の規制強化を背景としたものであることは明らかであろう。また、富栄養化を防止するため、排水中から窒素等を除去するための努力が続けられている。
以上みてきたような公害防止技術の研究開発の現状を踏まえ、今後更に重点的に推進すべき研究開発の分野は、次のようなものとなろう。
第1は、固定発生源から排出される窒素酸化物の防除技術の開発である。48年5月、国の窒素酸化物に係る環境基準が定められ、ボイラー等の固定燃焼装置に対する排出規制も開始されることとなった。これに対応して脱硝技術の開発が進められている。国のレベルでは、基礎的な分野を中心に研究が進められており、国立試験研究機関の試験研究費をみると、47年度の9,900万円から48年度には2億5,200万円へと増加している。また、民間においても、電力、化学等多くの部門で接触還元法等種々の方法による技術開発に努力が払われている。窒素酸化物は、いおう酸化物が燃料中のいおう分燃焼によって酸化物として排出されるのと異なり、空気中の窒素が燃焼装置内での燃焼により酸化物として生成されるものであるため、効率的な燃焼を行うほど量が増大する傾向がある。したがって、窒素酸化物の抑制は、反面で燃焼効率を低下させるという複雑な要素を内包し、この相反する条件を同時に満足する技術の開発には、国民間あげて努力を傾注する必要がある。
第2は、排水高度処理技術の研究開発を更に推進することである。先にみたように、既に有機性排水の高度処理等実用化研究の段階に入ったものもあるが、費用、効果も踏まえて経済性のある技術の開発も重要である。また、高度処理は、追加的に多量のエネルギーを消費し、最終廃薬物も多量に生成することとなるので、極力、少量のエネルギー消費で効率的に高度の質を確保する方向の新しい技術開発に取り組んでいかなければならない。
第3は、最終廃棄物処理と再資源化技術の開発である。公害防止技術の普及に伴って有害物質を含む最終廃棄物の量は、著しく増加しており、例えば、48年度において全国で発生する産業排水処理に伴う最終汚でい量は1日500トンと推定されている(厚生省推定)。これらの汚でいや一般都市廃棄物については最終的には無害化して環境に還元したり、若しくは汚でい中の有害物を回収再利用する技術が開発されることが必要である。既に廃プラスチック等合成高分子材料の再生による利用、熱分解によるガス化及び油化処理等の技術開発並びに都市系廃棄物からの総合資源化処理技術システムの開発は一部実用化の段階に達しているが、産業汚でい等有害物質を微量含有する廃棄物の処理と資源化については、なお一層の努力が要請されている。
第4は、無公害生産技術特にクローズドプロセス技術の開発である。一たん発生した汚染物質を完全に除去することは非常に困難であり、たとえ完全に除去されたとしても、高度の処理に高額のコストがかかっては費用、効果の面からみて問題があろう。最近における水銀問題を契機にソーダ工業の製法を水銀電極による電解法から隔膜法に転換する例があるが、そのほかのほとんどの生産プロセスにおいても新しい無公害技術の開発が求められている。
特に、無公害生産技術の一環としての汚染物質を環境中に放出せず、閉鎖されたシステムの中に封鎖するクローズドプロセス技術については、各種生産技術の分野でその開発の推進が望まれている。最終廃棄物の完全な処理技術の開発も、海洋投棄規制の強化の動向に対応して必要となってきている。最後に、これらの防止技術の開発に当たって、その技術がもたらす効用と影響を事前に予測、評価するためのテクノロジーアセスメントについても、その手法を開発し、適用していかなければならない。