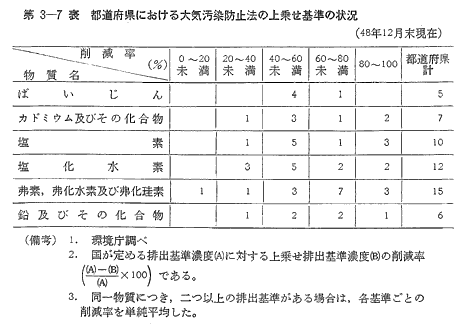
2 地方独自の規制強化
公害防止対策上、公害規制は不可欠の要件であるが、地方行政において、国の規制を一段と強化することにより、当該地域の公害防止を達成しようとする努力がなされてきている。
その第1は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法上のいわゆる上乗せ基準の設定である。これらの規制法においては、国の定める排出基準に加えて、その地域の自然的、社会的条件から判断して必要な場合に一段と厳しい基準の設定を都道府県知事の権限として認めている。
大気汚染防止法上では、ばいじん及び有害物質について、上乗せ基準設定ができることとなっているが、48年12月現在、ばいじんに関し5県、有害物質に関しては15都県で上乗せ規制が行われている。これらの上乗せ規制が国の一律規制よりどの程度厳しくなっているかをみたのが第3-7表である。ばいじんの規制強化は、千葉、愛知、岡山県等臨海工業地帯を中心に行われ、削減率は最高72%の厳しさとなっている。有害物質については、大工業地帯のほかに、秋田、福島、富山県等鉱山地帯において実施され、削減率は10%〜91%に及んでおり、汚染負荷の高い可能性をもつ地域における規制の厳しさがうかがわれる。
一方、水質汚濁防止法による上乗せ基準の設定は、健康項目である有害物質とpH、BOD等の生活環境項目について認められているが、48年8月現在、有害物質について17道県、生活環境項目について41道府県において行われている。また、国の制度上生活環境項目について対象となっていない工場・事業場(平均排出水量50m
3
/日未満のもの)について、条例により規制対象に加え一種の上乗せ基準を設定しているものが21道府県もある。このいわゆる「スソ切り」工場等に対する規制の概況は、第3-8図にみるとおりであるが、特に、広島、岡山、静岡県等工場排水による公害問題を抱えている地域において、全工場・事業場を規制の対象に加えていることが注目される。
地方における独自の規制強化の第2は、規制の方法自体における強化である。現在、国の制度としても準備を進めているいわゆる総量規制方式は、従来の規制方式によっては抑え難い地域全体の汚染量をチェックするものとして大気関係では、今日までに幾つかの道府県等において排出汚染量そのものを規制する方式が採用されている。地方公共団体の総量規制方式のなかには、地域全体の排出許容総量を定めず、単に工場・事業場への汚染排出量の割当てのみを定めたものもある。水質関係では、技術的困難性の大きいこともあって、地方公共団体の動きも比較的に遅いが、神奈川県等の一部の地方公共団体では、総量規制方式を含めた方式が導入されている。
また、独自の規制として、第3に、地方公共団体が地元企業等と締結する公害防止協定をあげることができる。公害防止協定は、住民の公害防止に対する要請の変化や公害防止技術の進歩に即応し、個別企業の実態に即した公害対策として法令による規制を補完しようとするものである。
現在の公害防止協定の原型は、39年に横浜市が電源立地に際して地元企業と締結したいわゆる横浜方式に始まるといわれるが、その後の協定締結状況の推移は、第3-9図のとおり、特に、43年以降急激に増加してきており、47年10月現在では38都道府県、461市町村と合計499団体が協定当事者となった。また、相手方事業所数は3,202を数えるに至っているが、業種別に上位5業種をとり出してみると、第3-10表にみるとおりで、全事業所数では、騒音、悪臭等の公害防止の観点から、中小企業者の多い金属製品製造業や畜産業が上位にランクされる一方、大企業の事業所数では、重化学工業が上位を独占していることがわかる。これら大企業の全国事業所数に占める協定締結事業所数の割合は5業種平均で38%であり、特に、化学工業、鉄鋼業ではかなりの事業所が協定に加わっていることを示している。
防止協定による規制内容は、第3-11図のとおり、公害の種類ごとに所要の規制をきめ細かく行っているが、同図により、全国の公害防止協定を業種別に分類してそれぞれの規制項目の締結された頻度をみてみると、80%以上の頻度で締結された項目は、電力業の原燃料規制等特定のものに集中しており、全体としてみても、鉄鋼以外の業種では、それぞれの汚染のパターンに従ってほぼ共通の規制傾向にあることがうかがわれる。鉄鋼業については頻度40%以上60%未満の項目がほとんどであり、規制の態様が一様でないことを示している。
以上みてきたように、地方公共団体の公害行政においては、その地方の実情に即した公害規制の強化をはじめ、各種の対策によりきめの細かい行政が行われている。しかしながら、今日においても、環境汚染や自然破壊の問題はなお各地において跡を断たない。地域住民の福祉の確保が地方公共団体の使命であることを考慮すれば、一層の地方公害行政の推進が望まれるところである。