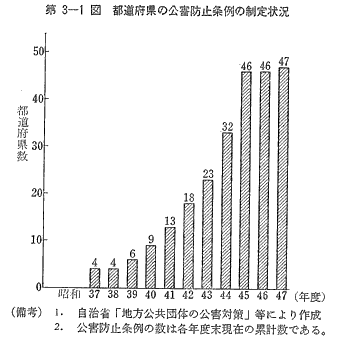
1 対策の推進
もともと公害現象が、ある地域の汚染排出源による汚染現象を通じて公害被害を発生させ、その地域住民に特有の不利益をもたらすという地域性をもった現象であるだけに、公害防止対策において地方行政の果たす役割は大きい。公害対策基本法にもあるように、国が基本的、総合的施策を策定し、実施することにより、国民の健康で文化的な生活を確保するうえでのいわばナショナルミニマムを実現すべき責務を有することに対応し、地方公共団体は、その地域の自然的、社会的条件に応じた施策を策定し、実施することにより、その地域住民のいわばシビルミニマムを確保すべき責務を有しているものといえよう。
このような観点から、地方行政の公害防止対策の動向をみると、まず、公害対策の中核となる規制行政の面では、公害防止条例を軸としてかなり早い時期から対応してきた。古くは、20年代の東京、大阪等大工業地帯における防止条例にさかのぼることができるが、我が国の公害問題が爆発的様相を呈し、国全体としての公害に対する姿勢を明らかにした公害対策基本法の制定をみた42年までに、第3-1図にみるとおり、既に18の都府県において防止条例の制定をみ、47年までにすべての都道府県が防止条例を制定している。公害防止条例は、大気汚染、水質汚濁等公害の種類ごとにその規制を行っているが、これら公害規制が国の制度として確立した時期との関係をみると、第3-2表のとおりとなる。大気汚染関係や水質汚濁関係は、比較的早期に国の規制法が制定され、その後その法律体系の中で地方への権限委譲が行われてきたという形をとっている。また、騒音、悪臭等のいわゆる感覚公害は、一般的には極めて地域性が強く、これらの公害規制は条例による規制が先行する形となっている。
地方レベルにおける公害規制は、防止条例や後に述べる地元企業との公害防止協定等により進められてきたが、次に地方公共団体における公害対策の組織、経費の面をみよう。都道府県の公害担当専門部局は、公害対策基本法制定の42年までに、既に20の地方において設置されており、47年に本土復帰した沖縄県を最後にすべての地方に担当組織が整備された。担当職員数をみると、全国都道府県本庁に47年10月現在で2,276人(うち専任2,071人)配置されており、1都道府県当たり平均48人(うち専任44人)によって公害行政が行われていることになる。これら公害担当組織によってどのような行政需要量に応じているかを定量的には握することは困難であるが、いま公害行政需要量の指標として、大気汚染防止法上のばい煙発生施設及び粉じん発生施設の数、水質汚濁防止法上の規制対象施設の数をとり、これを都道府県別に集計し、施設数の多い順に上位20位までの地方について、それぞれの担当職員1人当たりの施設数をみたのが第3-3図である。
これら上位20位までの地方の平均では、職員1人当たり36施設を担当することになり、公害発生施設に対して規制、監視、測定、指導等のきめの細かい行政を実施していくには、更に職員の拡充が望まれよう。
公害対策経費についてみると、第3-4図のとおり、47年度決算額は全地方公共団体合計で、8,113億円で2年前に比ベ2.2倍の増大をみせている。このうち、約9割までが下水道等の建設事業費であるが、ここ2年間の増加率は、経常経費が2.6倍と建設事業費の2.1倍を上回っている。経常経費を行政需要に対応する費用とし、先にみた規制法上の対象施設1件当たりの金額をみると、全都道府県平均約26万円となっており、この面からも対策経費の拡充の必要性がうかがわれる。
組織、経費の整備拡充を背景として、地方行政による公害防止対策は、公害規制を中心に各方面にわたって推進されてきているが、次に規制と表裏の関係をなす監視測定及び取締りの動向をみると、公害規制法の強化された46年以降、地方公共団体による監視測定体制は逐次整備されてきた。法律に基づき都道府県知事には大気汚染、水質汚濁について常時監視の義務が課されているが、大気汚染については、自動測定、集中監視のテレメーターシステムが普及し、45年度に15都道府県に設置されていたものが、47年度には25都道府県に拡大されている。水質汚濁については、知事は毎年測定計画を策定することとなっており、この計画に基づいて、環境基準の水域類型の指定の行われた247水域すべてとその他必要な水域で水質調査が行われており、その頻度は1水域当たり県際水域で6地点、その他の水域で3地点で月に1日3回の調査を行うこととなっている。
一方、法令違反者に対する取締り状況は、47年度において、大気関係で432の施設に対して改善命令を発動し、勧告その他の行政指導は5,704件にのぼった。水質関係では同年度中に1,426件の改善命令を行い、6,554件の行政指導を行った。施設数の多い上位20都道府県における改善命令、行政指導施設数の内訳は第3-5図にみるとおりである。しかし、違反者に対する告発は、同年度中大気関係では1件もなく、水質関係でも直罰違反者に対する告発は13件と少なく、地方公共団体レベルにおける公害規制が命令、勧告等の行政措置を現実の最終手段として行われていることを示している。一方、公害事犯として警察の処理した件数は47年度で791件にのぼっており、その内訳は廃棄物処理法に関するものが420件で最も多く、大気汚染防止法、水質汚濁防止法関係は合計で47件であり、地方公共団体においても悪質違反者に対しては今後とも一層厳格な態度で臨むことが必要であろう。
公害行政の基礎をなす調査研究の面でも地方公共団体の活動は進められている。昨年環境庁の行った調査によれば、地方の公害研究組織は、37年に愛知県と大阪府で既設の衛生研究所に公害部門が初めて設置されたが、独立した専門機関としては、42年に静岡県と三重県に設けられたのが最初とされている。今日までに専門の公害試験研究機関は26の都府県において設置されてきた。試験研究機関等で調査研究業務に従事する職員の数は全都道府県合計で47年10月現在1,315人となっている。試験研究機関の機能としては、東京都、京都府、愛知県等の場合のように試験検査、調査研究を業務の基本とする純粋の試験研究所型のもののほか、秋田県、福島県、静岡県等のように試験検査業務に加えて、企業に対する監視指導、苦情処理調査等の行政的業務を兼ねて行う行政庁型の機関もある。
環境庁の同調査で集計された38都府県の試験研究機関の自主調査研究数は201テーマにのぼっているが、このうち、過半数の110テーマは当該地方の公害の実態調査や原因解明に関するものとみられ、これら試験研究機関の地方性がうかがわれる。
公害に関する各種の研究や測定、分析の業務は、公害研究所のみならず、衛生研究所、農業試験研究所等でも行われている。これらの業務は比較的地味で、しかも根気を要する仕事であるが、公害問題解決の基礎をなす重要な業務であるといえよう。
最後に、公害対策の重点の一つである被害者救済に対する地方公共団体の動きをみよう。
四日市ぜん息が社会問題となった四日市市で40年から市の認定患者に医療費の支給が開始されたのを初めとして今日までに国の救済制度とは別に独自の制度を設置している地方公共団体は第3-6表のとおりであり、合計23に及ぶものとみられる。これらの地方救済制度においては、国の現行救済制度と同様、医療費、医療手当の支給を主体とするものがほとんどであるが、昨年発足した川崎市等5市における救済制度においては、生活補助費、死亡見舞金等給付の種類に新しい性格が加えられており、昨年成立した公害健康被害補償法による国の新制度が出来るまでのつなぎの措置を行ったものとして注目されてよい。