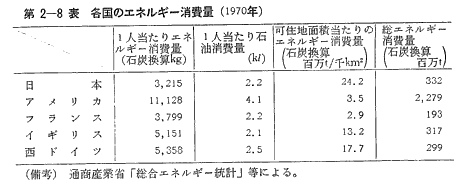
3 石油問題と環境政策の基本方針
今回の石油の「石油危機」によって、「消費大国」であり、かつ、「保有小国」である我が国は、その削減と価格上昇の影響を直接かつ最も強くこうむることが明らかとなったわけで、今後、我が国の政策は、環境保全を前提として、資源・エネルギーの節約とその有効利用を達成しうる経済成長と産業構造の実現を目指して実行されていかなければならない。
このような基本的態度を踏まえ、最近の石油問題に関連する当面の環境政策の方針を述べよう。
(1) 石油問題と大気汚染防止対策
まず、大気汚染防止対策関係についてみよう。
大気汚染に係る環境基準の確保については、環境基準が人の健康を保持するうえで維持されることが望ましい基準である以上、「石油危機」により基準が左右されることはありえない。いおう酸化物の排出基準の強化についても環境基準の達成には排出基準の遵守が必要不可欠であるので従来の考え方に従って強化改定すべきものである。公害防止協定も、公害防止の観点から地方住民の総意を代表する当該地方自治体と地元企業との間で締結されたものであり、一つの契約として遵守されなければならない。
また、「石油危機」に関連し、50年度から実施される自動車排出ガス規制の基準を達成するためには、現在の技術では現行の車に比べ燃料消費量が高くなるという問題がある。しかし、短期的には燃料効率が悪くなったとしても、一方で清浄な空気等環境資源の減耗を防げるわけで、こうしたある程度の追加的な燃料使用は、環境保全達成のための一つの資源の再分配として考えることができよう。もちろん、長期的には資源全体の使用効率を高めるため、新技術の開発促進によって、低公害で燃料効率の高いエンジンの実用化を図り、こうした問題は解決されるべきものであるが、このことをもって、自動車排出ガス対策強化を遅延させることがあってはならない。
(2) 省エネルギー化と環境政策
我が国においては、第2-8表にみるとおり、狭小な国土に高密な人口をもって経済活動が活発に行われているだけに、総エネルギー消費量、可住地面積当たりのエネルギー消費量は高く、環境に対する潜在的インパクトは大きい。
今回の「石油危機」を通じて、石油供給源を全面的に海外に依存する我が国は、あらゆる努力を払ってエネルギー使用の効率化を図っていかなければならないことを身をもって体験したが、同時にエネルギーの大量消費は今日までの我が国の環境汚染の大きな要因をなしてきたわけであり、その意味で、環境問題とエネルギー問題は、いわば「楯の両面」として同時に解決すべき問題であるといえる。このような観点から、今後、我が国が目指すべき方向は、無公害・省エネルギーの経済構造の達成であり、環境保全を前提としつつエネルギーの有効利用を国民経済のすみずみまで浸透させ、少ないエネルギーで高度の経済社会を成立させることである。
省エネルギー化の促進のためには、これまでの生産、輸送、消費等各活動におけるエネルギー消費のあり方を根本的に再検討していく必要がある。
第1に、生産活動におけるエネルギー消費のあり方についてみよう。
第2-9図は、電力、銃鉄粗鋼、パルプ・紙等主な業種の生産をその原材料にまでさかのぼって全過程をみたときに、どの程度のエネルギーを使用し、またどの程度の汚染を発生しているかについて試算したものである。電力、銃鉄粗鋼等の生産額単位当たりのエネルギー使用量が高い業種は、いおう酸化物発生量も高く、電気機械、家具等エネルギー使用量が低い業種はいおう酸化物発生量も低くなっている。
第2-10表は、主な業種別のエネルギー消費量、重油消費量並びに汚染因子の発生量を試算したものである。鉄鋼、化学、窯業・土石等エネルギー消費量のシェアが高い業種では汚染の発生量のシェアも高い傾向にあることがわかる。
今後は、エネルギー消費量の高い業種を中心に各産業が新プロセスの導入、熱効率の向上等によって、省エネルギー化の促進とエネルギー消費量の節約を図り、これを通じて潜在的汚染負荷量の削減を図っていく必要がある。
また、我が国の産業構造についても、環境保全並びに資源・エネルギーの有効利用が達成されるような省資源・省エネルギー型の産業構造への転換を図ることが急務となっている。
第2に、輸送面において、省エネルギー化を促進する必要がある。例えば、自動車は戸口から戸口まで運搬できるという利点を備えている反面、他の輸送手段に比べて、エネルギー効率は悪く、しかも全石油消費量中約18%のシェアを占め、同時に大気汚染や騒音等環境汚染の主要な原因の一つとなっている。今後、環境保全、省エネルギーの観点から、各種の交通手段のあり方についての検討を深めていく必要がある。
第3に、消費面における省エネルギー化を促進することである。
日常生活上で、衣食住すべてにわたって必要なエネルギーの利用の見直しを通じて、家庭用製品及び生活パターンの省エネルギー化を促進しなければならない。我々の日常生活において、近年では様々な分野において使用されている耐久消費財のなかには、利便性の面では相応の存在理由はあっても、エネルギー消費面からみると改善を要するものが少なくない。エネルギー多消費型の製品は他の製品に代替されるか、省エネルギー型の製品に転換される必要がある。
また、個々の製品の省エネルギー化に加えて、太陽熱の活用を含め個々の家庭におけるエネルギーの効果的利用を図らなければならない。
第4に、地域全体としてのエネルギー利用の効率を高めることである。
地域冷暖房は、我が国では緒についたばかりであってその普及度は低い状況にあるが、今後の住環境の快適化の要請に即していると同時に、ボイラーの大型化による燃料使用量の削減、良質燃料への切換え等が可能なため環境保全、省エネルギー化に資するものでもある。例えば、札幌市の北海道熱供給公社の例では、地域暖房の導入によって、同一のエネルギーサービスを個々に行うのに比較して、エネルギー消費量並びにいおう酸化物排出推定量が約50%削減されたといわれている。
地域冷暖房と並んで近年注目を浴びているものにごみ熱発電がある。これはごみ焼却処理施設から出る熱によって発電を行うものであり、資源の再利用を可能にするとともに地域全体のエネルギーの有効利用に資することになるので、焼却処理施設から生ずる有害物質の発生を防止しつつ、その促進を図っていくことが望まれる。
(3) エネルギー開発と環境政策
今後の国民福祉の向上のために予想されるエネルギー供給量を確保するために、省エネルギー化の促進に努めることが肝要であるが、化石エネルギーの安定的確保が容易でなくなった今日、新エネルギー等の開発の気運が国際的にも国内的にも高まっている。新エネルギー等の開発に際しては、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、自然破壊等の環境問題をひきおこさないよう十分留意しなくてはならない。
まず、太陽熱、石炭ガス化・液化、地熱、水素等の新エネルギーについては、今後の研究開発の推進に待つところが多いが、その過程において、例えば地熱発電における蒸気噴出等に伴う騒音、ボーリング等に伴う自然環境の変質等を防止するため、環境保全の観点から十分テクノロジーアセスメントを実施していく必要がある。
原子力発電では、火力発電所の場合と同様に温排水による環境への影響の問題があり、水力開発においては、ダムの上流の河床上昇、下流の流量減少等による生態系の変化、ダムの建設及び輸送に伴う自然環境の改変等の環境問題が考えられ、これを予防するために十分な配慮が必要である。
こうした環境への影響について適切な配慮がされるならば、新エネルギー等非化石燃料の利用促進は石油利用に伴う大気汚染を中心とする環境へのインパクトを低減することになろう。
したがって、新エネルギー等の開発が環境保全政策と抵触しないのみならず環境保全にプラスになるよう、各種の環境保全技術開発が、新エネルギー等の原理面、技術面での開発と並行して行われる必要がある。また、新エネルギー等の開発が具体的に行われる場合には、事前に十分な環境アセスメントを行い、環境に悪影響を及ぼさないよう十分な配慮がなされなければならない。