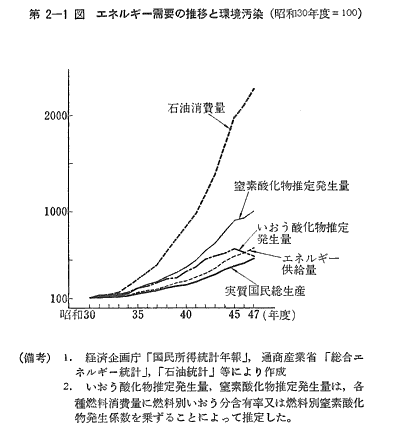
1 石油利用と環境問題
我が国のエネルギー需要、特に石油に対する需要は、実質国民総生産をはるかに上回るスピードで増大してきた。第2-1図にみるように、47年度の実質国民総生産は30年度の5.1倍となったが、この間に一次エネルギー供給は6.3倍となり、石油供給はエネルギーの流体化の推進により実に23倍となり、47年度の消費規模は2億6千万klとなった。なお、これに伴い、いおう酸化物、窒素酸化物の発生量はそれぞれ5.5倍、10.1倍となったものと推定される。
このように巨大な需要量となった石油は、国民生活の多くの分野に使用されている。第2-2図にみるように、鉱工業、電力、運輸、家庭等の熱源、動力用はもとより、石油化学等の原料用としても多方面に使用され、これによる製品は衣食住の各分野において広く使用されている。
繊維製品関係では、その約5割が石油化学製品を原料とした合成繊維であるとみられ、肥料(硫安・尿素)の原料、魚網の大部分は石油化学製品であり、更に、住居関連製品でも、アクリル板、スチロール板、塩化ビニル板等の建設用資材、日用台所製品、カーペット等数多くの分野で石油化学製品が使用されている。また、乗用車には、1台当たり約50kgのプラスチックが使用されているといわれている。
生活に関連した石油製品は第2-3図のように近年著しい生産の伸びを示してきた。35年と47年とを比較してみると鉱工業生産の平均では4.1倍であったのに対して、化学繊維では5.8倍、合成洗剤9.1倍、プラスチック16倍、と高い伸びを示している。
石油関連の消費財の増大や石油を使用する自動車等の耐久消費財の増大は、国民の日常生活における利便や生活水準の向上をもたらしたが、他方、石油の輸送、使用等に伴い環境保全面に悪影響を与えることとなった。
その主な影響の第1は、大気汚染を増大させる結果となったことである。
石油利用の増大に伴って、ばいじんによる汚染は改善されてきたものの、これに代って、いおう酸化物や一酸化炭素等による大気汚染は、現在では改善の傾向にあるものの近年まで悪化を示し、最近では窒素酸化物、炭化水素、オキシダント等の新しい大気汚染を発生させている。
可住地面積当たりのいおう分、窒素酸化物発生量を推定してみると、第2-4図のように太平洋ベルト地域をはじめ全国的に汚染量が増大していることがわかる。46年当時、東京都では可住地面積1k?当たり年間約460トン発生していたものと推定され、30年の約7.3倍となっている。
第2は、水質汚濁の面でも環境汚染の原因の一つとなっていることである。原油の海上輸送の大量化とともに海洋汚染が増大した。海洋汚染防止に係る法規制は近年強化されているものの海上保安庁が確認した汚染発生件数は48年において2,460件であった。このうち油によるものが約9割を占め、この5年間で8.3倍に増加している。廃油ボールについてみると太平洋沿岸を中心に広範囲にわたって漂着している。油による海洋汚染は国際的にも重大視されており、海洋汚染防止条約の強化改訂の動きとなって現れている。
第3は、廃棄物の面でも、石油製品を原料とするプラスチック等について、次節でみるようにその生産の増大に伴って多量の石油を消費する一方、その使用上の利点が同時に廃棄物処理上の短所となり環境汚染を増大させる結果となっていることである。