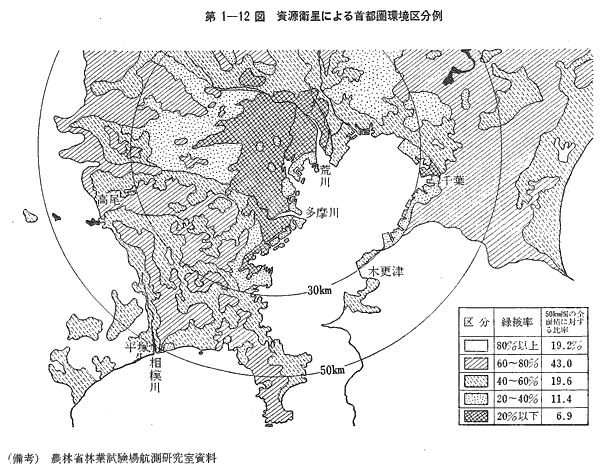
1 自然環境の変貌
自然は人間生活にとって生命をはぐぐむ母胎であり、限りない恩恵を与えるものであり、また、経済活動のための資源としての役割を果たすだけでなく、それ自体が豊かな人間生活の不可欠な構成要素をなすものである。
しかし、狭い国土に巨大な人口を抱える我が国では、人口が集中している都市地域において自然環境の喪失が身近に現れている。我が国の都市地域における自然がいかに失われつつあるかを巨視的に資源衛星(ERTS)による写真によってみてみよう。第1-12図は、首都50km圏内における緑で被われている地区の比率(緑被率)の状況を示したものであるが、これをみても人間活動による自然の浄化力の喪失がうかがわれる。そのうち、6.9%は緑被率20%未満の建築物の高度に密集化した地域であり、特に東京都区部の大半はこの緑の少ない地域となっている。比較的自然が保たれている地域においても各種の開発の波が及び、50km圏内で約314k?の地域が開発進行中であり、そのうち約80%が30〜50km間において行われている。
我々の身のまわりをみると、以前に見られた動植物が失われていった事例も少なくない。東京都区部の中では緑が比較的多い杉並区でも38年当時に樹木、草地は37.0%確保されていたのに対し、10年後の47年には26.6%に減少し、一方、構造物用地は49.6%から60.3%へ増加している。環境庁の調査により東京都における天然記念物等の貴重な樹木の生育の変化をみると、都市化の進展に伴い、環境変化に弱いといわれるケヤキは各所で枯損し、若い木でも所によっては年2回も落葉が伝えられている。環境の変化に強いといわれているイチョウも調査対象樹木のうち正常なものは50.0%で、幾分被害を受けているもので余り目立たないものが25.0%、異常が一見してわかるものが21.4%、生育状態の悪いものが3.6%であり、環境汚染の進行が続けば、今後これらの樹木が残存しにくい状況となってきていることが指摘されている。
全国の動物観測率を動物季節観測指定官署で調査した例をみると、第1-13図のとおりほとんどのものが逐年減少傾向を示し、残りのものも近年減少しつつある。なかでも夏の景物であるホタルやシオカラトンボの減少が著しくなっている。一方、東京都のツバメの生息状況調査によると最近2か年においてツバメの急減した地域は、都心を囲むように半円状をなしており、また、国鉄中央線西荻窪駅を中心として半径500m以内の北半分の地域において観測されたツバメの営巣数は、35年に51つがい見られたのが、47年には2つがいしか観察されていない。
シデムシの生息状況は、自然からの隔たりの度合を表すものであるといわれているが、東京都のシデムシ類の調査によってみると、第1-14図に示すとおり、都心を離れるにつれ種類が増加していることがわかる。シデムシ類が生息しないことは本来の自然の生態系がゆがめられていることを示すものであろう。
しかし、最近幾つかの明るいニュースも聞かれる。環境庁の調査による東京都のモクセイの開花状況は、都心部においては花の咲かないものが多く、郊外に行くにしたがって全面的に開花するといる傾向を示しているが、都区部において41年当時花の咲かなかったもののうち47年に花が咲くようになったものが数か所でみられるようになったという報告がある。隅田川でも魚を見かけるようになったという例もみられる。また、各地においてハクチョウ、ガン、カモ等の渡り鳥の渡来数が増加しているという事例も報告されている。
以上、都市地域における自然の退行現象又は自然が受ける影響を身近な例でみてきた。
人間は本来自然と一体となり、その微妙なバランスのなかで生存する存在であるにもかかわらず、人間自らが十分な配慮をなさずにこの微妙な自然のバランスを壊してきていることが少なくない。このことは単に都市地域のみならず国土全域においても種々の問題を提起している。
特に、近年各地において、自然環境の破壊につながるような道路の建設、ゴルフ場・別荘地等の造成、埋立地の造成、宅地の造成、森林の伐採、土石の採取等の大規模な開発行為が行われ、批判を受けている場合が少なくない。
以下その問題とされる例をみてみよう。
(1) 道路の建設
道路建設が自然環境の豊かに残されている地域で行われる場合は、通過地域の選定、工法等によっては直接的、間接的に自然環境の保全に悪影響を及ぼす事例が生ずることが少なくない。
道路建設に伴って生ずる自然環境への影響としては次のようなものが考えられる。第1は、道路建設そのものから生ずる地形の改変、森林の伐採等による植生の損傷、山肌の露出による景観の破壊等直接的なものである。例えば、密生していた森林を伐開して道路を通したため、道路に接する樹木が強風にさらされて倒れたり、傾斜した例があり、また林内が乾燥し、水分の供給が追いつかず、森林がバランスを失って立枯れした例もある。道路建設の際に生じた捨土を後方へ運ばず斜面の下方へ捨てたため、樹木が土砂、岩石等により傷つき、又は深く埋まり枯死する例も多く見受けられる。
第2は、道路の開設に伴い野生動物の生息地域が分断され、生息環境が損なわれたり、当該地域の自然の生態系が乱されることである。例えば、立山アルペンルートではかつて野犬が入り込み、立山近辺に生息しているライチョウを襲った例も報告されている。
第3は、二次的自然破壊というべきものである。道路が完成したことにより、他の種々の開発を誘引し、それらの開発行為により自然破壊が生ずる場合が少なくない。また、自動車の普及とともに多数の観光客が訪れ、それらの者が高山植物地帯や湿原に入り込み、裸地化させたり、樹木を盗伐していく者が跡を絶たない。なお、観光客によるごみの投棄や水質汚濁の問題につながるという側面もある。
このように道路建設の自然に及ぼす影響が多岐にわたることから、自然環境の優れた地域における道路建設について、大雪山国立公園の大雪山道路、上信越高原国立公園の妙高高原道路等の建設を巡って、自然環境保全の面から種々論議された。
このうち、大雪山道路は地域産業の振興、住民の生活の安定向上等を図るため、大雪山国立公園内において計画されたが、これに対して、当該地域は、我が国で最も優れた原始的自然の豊かな山岳地域として保全すべきであるとの意見もあり、また、自然環境保全審議会において当該道路の自然に及ぼす影響についての調査が十分でないこと等の指摘もあり、これに関する調査を実施することとし、当該道路計画についての協議は取り下げられた。
これらの問題に関連して、自然環境保全審議会自然公園部会長談話が発表されたが、その趣旨はおおむね以下のとおりであり、これは自然環境の優れた地域における道路建設についての今後の方向を示唆するものといえよう。すなわち、国立公園等の自然の豊かな地域における道路の建設については、地域住民のため当該道路が是非必要であり、これに代わる適切な手段が見出せない場合に限られるべきである。その場合でも、当該地域の自然環境について事前に十分科学的調査を行う必要がある。また、道路建設に際しては原始的自然環境や優れた景観を保持している地域、亜高山帯・高山帯、急傾斜地等のうち緑化困難な地域、稀少な野生動植物等の生息している地域、渡り鳥等の貴重な渡来地等については、あらかじめ慎重に避けるよう配慮し、これらの地域の限られた貴重な自然環境を維持、保全していく必要があるという趣旨のものであった。
これらの地域においてやむをえず道路を建設する場合にあっては、自然環境を破壊しない適切な工法によって行うべきであり、そのために要する費用の支出を惜しんではならないであろう。
(2) ゴルフ場、別荘地の造成
最近盛んとなってきたレジャー開発に伴う自然環境への影響をゴルフ場と別荘地の造成を例にとってみてみよう。
全国のゴルフ場数は、40年の423か所に比べ、48年7月には709か所に増加している。東京周辺7県では、49年2月現在、既設のもの192か所、造成中のもの78か所のうえに更に計画中のものが既設のものの約2倍にものぼるといわれている。
特に、最近多くのゴルフ場は敵地が少なくなったこともあり、従来平地に建設されていたものと異なり急峻な地形に設けられることが多く、施行方法も森林を伐採し、機械力を駆使して山を削り、谷を埋めて建設されていることに問題がある。そのため、近年の山林原野におけるゴルフ場の建設は地形の大規模な改変のみならず、たとえ芝生によって緑は確保されたにしても森林の保水機能の低下により水源をこ渇させ、水脈の切断による土砂の流出等災害の原因ともなる。
また、民間企業の土地の蚕食的な取得や一定の地域にゴルフ場が集中することにより、当該地域の適正な土地利用が阻害されるとともに乱開発となり自然破壊に一層の拍車をかけることとなる。
次に、別荘地の造成は、都市の過密による脱都会化、所得水準の向上等を背景として、交通の発達により開発適地が都市近郊から遠距離へ伸びたこと、過疎対策の一環として受け入れられたこと等もあって近年急速に増大してきた。長野県においては、現在別荘地等の開発は171件、6,250haを占め、レジャー用施設用地の合計13,952haの44.79%に当たり、計画中のものは183件、14,062haであり、レジャー用施設用地の計画全体の71.0%を占めている。
別荘地の造成は、自然の豊かに残されている地域において大規模に行われることが多いこと及び造成後これらの別荘から排出される廃棄物等により下流の水源が汚染される等自然環境に悪影響をもたらす可能性が大きい。
ゴルフ場の建設や別荘地の造成に際しては、自然環境保全の観点から、場所の選定、工法について十分に配慮することが望ましい。国、地方自治体は、無秩序な土地利用から自然環境を守るため、ゴルフ場の造成、別荘地の造成等の開発行為に関し、法令改正や条例、要綱等の制定を行い、それらの行為を規制することにより、良好な自然環境を保全しようとしている。
(3) 埋立地の造成
埋立てによる用地造成の実績は、31年度から46年度までにおいて、港湾区域では、25,528ha、その他の区域では39,770haとなっている。
埋立ては、工業用地、農業用地、都市再開発用地、又は下水処理場用地等として利用され、国民生活の向上や生活基盤、生活環境の整備に寄与している。しかし、一面において、埋立地の場所、規模等によっては、水面を陸地化することにより、自然環境上の問題をひきおこす場合もある。
埋立てが自然環境へいかなる影響を及ぼす場合があるかをみてみると、まず第1は、埋立てにより、自然海岸線の美しさが失われるとともに国民の保健休養の一つとしての潮干狩や海水浴の場が失われることである。
第2は、埋立てにより魚介類の生息地が失われることである。自然海岸線は栄養物や有機物に著しく富み、アサリ、ハマグリ等の貝類、エビ類、カニ類等多数の生物が生息している。
藻場が発達しているところは、水の動きが和らぎ、光合成により酸素に富み、植物体の表面に珪藻等が付着するのでそれらを食物とする甲殻類、貝類等の小型動物が繁殖している。また、各種の魚類の産卵場所、成育場所となり、回遊魚が滞在する等の生態系を形成し、水産資源の重要な場所となっている。埋立てにより、これらの場所が失われ、生物の食物連鎖が分断されることにより、海洋生物等の長期的な減少につながるといわれている。
第3は、干潟等の埋立てにより鳥類の生息地が失われることである。干潟等はシギ、チドリ等の渡り鳥の渡来地、繁殖地、採餌地となるものであるが、埋立てにより、これらの地が奪われることとなり、渡り鳥の減少という結果を生ずる。東京湾は日本三大干潟の一つといわれていたが、近年の埋立てにより鳥類の減少が著しい。千葉の新浜においても埋立てにより鳥類が減少し、隣接する東京都の葛西において観察された例では5年間のうちに96種の鳥類が半分の48種に減少している。
その他、自然海岸線では、潮の干満と波浪によって物理的にろ過が行われるほか、砂粒に付着したバクテリアや原生動物、小型多細胞動物等が有機物を分解し、浄化しているといわれており、内湾や内海等海水交換の悪い海域においては埋立てにより当該海域の水質浄化機能が減少することがある。また、埋立てにしゅんせつが伴う場合には、工法等が適切でないと、汚濁、藻場の喪失、潮流の変化が起こり、ノリ、カキ類等の水産資源に大きな影響を及ぼす場合もある。
以上のように埋立てが自然環境へ及ぼす影響は大きなものがあるため、従来の環境保全に対する運用に加えて、第71回国会において公有水面埋立法の一部改正が行われ、埋立てについての環境保全上の配慮が更に強化されたところであり、今後はその趣旨に沿って自然環境保全に一層配慮することが必要である。
(4) 宅地の造成
宅地造成は、森林、緑地等の自然環境の後退をもたらし、土地利用計画の策定や宅地造成の設計によっては自然に悪影響を及ぼすことがある。
経済の発展、都市化の進行等により都市への人口集中は年々著しくなってきており、45年の国勢調査によれば人口の44.3%が東京、大阪、名古屋を中心とする三大都市圏に集中していることを示している。
人口集中に伴う宅地への需要は高く、35年から45年の間の三大都市圏の宅地の増加をみると、全国の増加258,033ha(46.3%増)に対し、東京圏49,969ha(53.2%増)、大阪圏26,853ha(62.5%増)、名古屋圏25,252ha(58.0%増)となっている。
宅地の増加は、大都市における活発な住宅需要を背景とするものであるが、宅地の造成が環境条件を無視して無秩序に行われると適正な自然環境が保全されない場合がある。また、土地取得難等の事情を反映して、宅地開発が山間丘陵地や農業的土地利用がなされている地域で行われる場合が多いが、これらの地域における宅地の造成は、土地利用計画の策定や宅地造成の設計によっては良好な自然環境を損なう場合があるので、造成に当たっては自然環境保全に十分配慮する必要がある。
更に、宅地の造成は、森林、生産緑地等のオープンスペースの減少をもたらすこととなる。大都市圏の住民が居住環境を良くするため何を最も望んでいるかを47年の総理府の世論調査によってみると緑の増大を望んでいる者が最も多いことを示している。このような事情を考慮し、また、都市の森林が心に潤いを与えるのみならず、防災的機能を有し、更に環境を浄化する役割を有していることを評価すれば、今後、宅地開発をするに当たっては、当該地域を事前に十分調査し、地形地質を考慮に入れ、あらかじめ現存の植生を生かすように計画的に緑地等を確保する等の慎重な配慮が要請される。
なお、宅地化されたのち、住宅から排出されるごみや生活排水による河川等の汚濁の問題が生ずる場合がある。特に近隣河川の水量がわずかである場合、又は下水道等の施設が不備な場合は家庭排水が汚濁等の原因となることもあるので、今後の宅地造成に当たっては水質汚濁対策、廃棄物対策について十分留意する必要があろう。