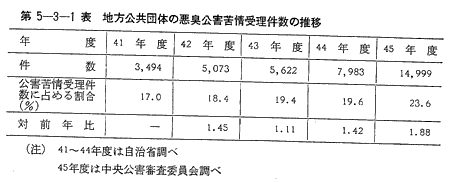
1 悪臭公害の現状
(1) 概要
悪臭は、嗅覚という人の感覚により直接知覚されるものであるだけに、公害としての歴史もふるく、すでに明治年間の大阪府の「製造場取締に関する規則」においても、「有害瓦斯又は悪臭・騒音を発する製造場」は、許可なくして設置することができない製造場の一つとして規制されていた。しかしながら、この悪臭については、悪臭の原因となる物質が不明確であり、その物質の量と被害の程度との間の量的関係が十分解明されていないこと、悪臭の原因となる物質の排出を減少させるための技術の開発が遅れていること等の理由から、これを防止することが最も困難な公害であるとか考えられ、その対策が遅れていた。
しかし、近年の各種企業の大規模化に伴う汚染の広域化、都市の郊外、近郊へのスプロールに伴う住居の悪臭発生事業場への接近により、悪臭公害に関する苦情は増加の一途をたどっており、昭和45年度に地方公共団体が受理した公害に関する苦情のうち悪臭に関するものは、全体の24%を占め、騒音、振動に関するもの(36%)についで第2位となっている。また特に市(区)部において苦情が多く寄せられていることが認められる(第5-3-1表、第5-3-2表)。
(2) 悪臭公害の実態
悪臭の原因となる物質については、業種、事業の規模、作業方式等により種々ことなるが、代表的な悪臭発生事業場とこれから排出される悪臭の原因物質は第5-3-3表のとおりである。悪臭の原因物質の排出の形態およびその排出により影響を受ける地域の範囲も多種多様であり、たとえば、クラフトパルプ製造工場から排出される硫化水素、メチルメルカプタン等の大部分は高煙突からのものであり、1〜2kmも離れた地点が最も悪臭が強く感じられるのに対し、畜産業等については、畜舎からの悪臭の原因物質の排出が主であり、隣接地帯が最も悪臭が強いともいわれている。