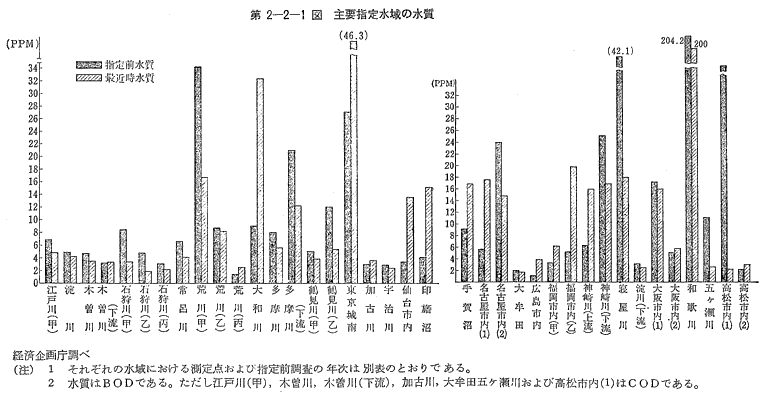
1 水質汚濁の概況とその背景
共公用水域の水質汚濁が人の健康や上水道、漁業等生活環境に悪影響を与えるものとして問題になってからすでに久しく、近年ではますます深刻の度を加えている。これを、水質保全法に基づき水質基準を定めて排水規制を行なうこととしている指定水域の数でみると、昭和37年以来年々増加してきており45年度末で71(一般指定水域のみ)を数えるに至った。第2-2-1図は、これら指定水域の指定前と最近の水質を示したものであるが、概して改善の方向を示しているといってよく、指定前と比べても調査対象54か所中水質の改善をみたものは30か所にのぼっている。しかしながら、悪臭の発生限界といわれるBOD10ppmを大幅にこえる水域もなお多く、水質源としての利用、環境としての機能をともに失いつつある状況にあるものもある。
こうした水質汚濁の背景として第1に指摘できることは、急速な経済成長に伴う水消費の増大と汚染因子の増加である。国民総生産(実質)は、43年には37年当時に比べ86%の増大をみせ、生産の拡大は、一方で水利用の増大をまねいた。つまり工業用水使用量(海水および回収水を除く。)は、この間に2,696万トン/日から3,603万トン/日へと34%伸び、その結果排水量も増大した。とりわけ、わが国産業のなかで汚濁負荷量の大きな業種である紙・パルプ、食料品、化学における工業用水使用量(海水および回収水を除く。)の製造業全体に占める割合は、37年には合わせて40.5%だったものが、43年には61.3%へと約50%増加し、公共用水域の汚濁を著しいものにしている。
水質汚濁の背景の第2は、人口、産業の著しい都市集中である。過密化による水質汚濁の進行は、自然の浄化能力をこえ、汚濁を著しいものにする。現在までに、水質保全法に基づく指定水域として指定された水域が全公共用水域に占めるウエイトは比較的小さいにもかかわらず、その流域において、わが国の人口の約54%、工業出荷額の約74%が集中しているという事実は、人口・産業の集中と水質汚濁の進行との関係を物語っていよう。
第3の背景は、公共下水道等生活環境の保全に関連する社会資本の整備の立ちおくれである。わが国の下水道普及率は、22.8%(排水整備面積/要整備面積)ときわめて低い。経済の成長、人口・産業の集中のテンポに即応して下水道の整備が行なわれなかったことが水質汚濁、とりわけ都市の河川の汚濁をもたらしたものといえよう。
なお、わが国は、古来から水に恵まれており、公共用水域の汚染防止に対する意識が立ちおくれていたことも、水質汚濁問題をいっそう深刻なものとした背景であろう。