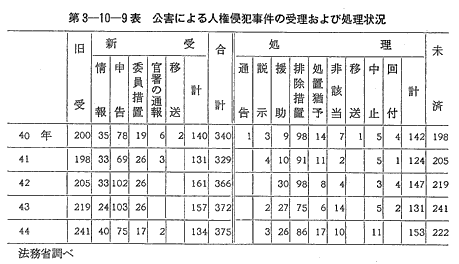
2 人権擁護機関による処理
(1) 人権擁護機関と公害
法務省においては、人権擁護局とその下部機構である法務局、地方法務局および支局ならびに法務大臣が委嘱している人権擁護委員が人権擁護機関として、人権侵犯事件の調査、処理、人権思想の普及高揚、貧困者への法律扶助等に積極的に取り組んでいる。
公害は、人権擁護の立場から放置できないものがあり、公害が社会問題として一般に取り上げられるようになるとともに、公害に関する人権擁護機関への被害救済の申出が増加してきたことを考慮して、36年から人権侵犯事件の類型にあらたに「公害」を追加し、「不特定又は多数人の福祉に影響する騒音、ばい煙、汚水、悪臭、紛じん等の放出あるいは振動により、人及び家畜、農作物、水産物等に被害を及ぼすもの」をその対象として、積極的に対処していくことにした。
現在では、国の公害規制立法や地方公共団体の公害防止条例が逐次制定されて、公害の予防体制もかなり整い、また、それらの法令による和解の仲介制度のほか各省庁や地方公共団体の事実上の公害紛争に関するあっせんなど、それぞれ専門立場から、公害予防、被害者救済の努力がなされている。人権擁護機関としては、これからも関係機関との協力提携を図りつつ、人権擁護の立場から被害者の救済に努めなけらばならないであろう。
(2) 公害事件の受理、処理の概況
人権擁護機関が過去5年間に取り扱った公害による人権侵犯事件の受理および処理件数は、第3-10-9表のとおりである。公害問題が社会的に関心をもたれはじめた34年ごろから年間受理件数は100件をこえ、40年には140件を記録し、その後多少の起伏があるが、44年には134件となっている。
受理区分をみると、被害者の「申告」が最も多いが、これは、公害を人権問題としてとらえ、人権擁護機関による救済を求めようとする国民の切実な要求を反映しているものであろう。「情報」がこれに次ぐが、これは人権擁護機関(ただし、人権擁護委員を除く。)が新聞、テレビ等によって被害の事実を知った場合に、被害者の申告をまたずに調査を開始するものである。「委員通報」は、人権擁護委員が申告を受け、自ら侵害を現認し、あるいは新聞等でその事実を知ったことにより受理した事件をいう。
処理区分では、「排除措置」が圧倒的に多い。「排除措置」というのは、関係者に対する説得、勧奨、あっせんなどにより被害の除去、減少の措置がとられた場合の処理区分である。人権擁護機関の調査、処理には別段強制権限はなく、すべて任意手続きによるものであるから、調査の結果、侵害の事実が認められる場合には、関係者を説得するなどして自発的に侵害を排除してもらうことに重点をおいている。そして、公害のように侵害の状態が継続する人権侵犯事件の処理は、その侵害を排除しなければ救済の真の目的が達せられないので、そのための努力をしており、その結果、処理事件のうち約65%は「排除措置」となっている。しかし、「排除措置」が諸種の事情によって事実上困難な場合は、金銭的な慰謝によって被害者の救済を図るとか、あるいは裁判手続にゆだねる以外にみちがないこともある。それらの方法によって処理した場合が「援助」である。したがって、このなかには、被害者に損害賠償請求のための調停や裁判手続に関する助言をしたものも含まれ、その際、訴訟費用等を負担できない貧困者に対しては、事情により法律扶助協会による訴訟援助のあっせんもしている。その他侵犯者ないしその者を指導、監督する者に対する「説示」、当該人権侵犯事件を処理するに相当と認められる官公署等に対し文書で侵犯の事実を知らせる「通告」がみられ、さらに処理区分として司法警察機関に対する「告発」侵害者ないしその指導、監督者に対し文書でする「勧告」があるが、前述のような公害事件の性質上、これらの処置をとることはきわめて少ない。
次に、43年中に人権擁護機関が処理した公害事件131件のうち、人権擁護局に報告のあった主要事件51件について発生原因、発生業種、講ぜられた対策を分析したのが第3-10-10表である。この表からもわかるように人権擁護機関であらゆる種類、あらゆる規模の公害を取り扱っている(数件数と公害の種類に計上されている件数が一致しないのは、たとえば1件で騒音・振動、悪臭・水質汚濁等のように2以上の公害を発生させているものがあるからである)。最も多いのは騒音であるが、これは全国的にみられる一般的な公害であるからであろう。調査・処理の結果講ぜられた対策では、公害防止施設の設置や既存設備の改善を加えた「設置改善」が最も多く、「作業方法改善」がこれに次いでいる。
しかし、最近の公害事件は、種類が多様化するばかりでなく、規模も大きく、発生原因や利害関係等も複雑なものが多い。このような公害事件の調査・処理は、法律上なんら強制権限を与えられず、専門的研究員・調査員や特別の公害予算を有しない人権擁護機関にとって容易な業でないのである。