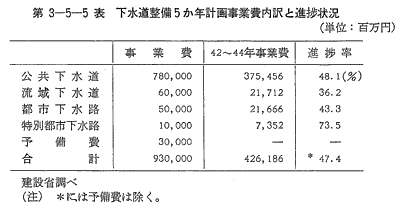
1 下水道整備の促進
(1) 水質汚濁防止に果たす下水道の役割
下水道とは市街地における雨水を排除し、人間の生活または生産活動に起因する汚水を排除および処理するための施設であって、現代の都市にとって必要不可欠な基本的な施設である。その目的機能は、水質汚濁防止、降雨による市街地の浸水防止、水洗便所化による生活環境の改善等多方面にわたっている。
とくに水質汚濁防止はその目的機能のうちでも、最も重要なものである。近年の工業の飛躍的発展と人口都市集中に伴ない、工場排水、あるいは家庭汚水が公共用水域に放流されることにより、公共用水域における水質汚濁が急激に進みつつあり、生活環境の悪化はもちろんのこと、水道水源および工業、農業、水産業等に対する水資源の質的価値の低下をもたらしている。
これら公共用水域の水質汚濁の原因者は、市街地においては、不特定多数の工場、一般家庭であるため、水質汚濁の防止は、全面的に管渠を整備し、末端の終末処理場で汚水を処理し、きれいにして放流するという公共下水道の整備にまつほか事実上方法はない。
大気汚染、騒音、地盤沈下等についての公害対策は不特定多数の原因者を対象とする個別的な規制が中心となるため、完全を期すには困難が伴う。しかし水質汚濁は公共下水道を整備することにより、工場廃水を含めた都市内の汚水を収容し、処理することが可能であるため、市街地および周辺については、完全な対策を講ずることができる。下水道の整備は、この意味において水質汚濁の抜本的かつ完全な対策となり得るのである。
このような下水道の水質汚濁防止に果たす役割の重要性については、昭和44年12月に水質審議会からも公共用水域における水質汚濁防止のための下水道整備の促進についての意見具申がなされた。
下水道はその構造、目的等により公共下水道、流域下水道、都市下水路、特別都市水下路に区分されるが、雨水排除を目的とした都市下水路を除いた他の3種はすべて水質汚濁防止に資するものである。
公共下水道は下水道施設としては完全なものであり、雨水、汚水を集める管渠、汚水をきれいにする終末処理場を持っているため、し尿を含む一切の都市下水をそのまま流すことのできる下水道であり、都市部における静脈ともいえるものである。
下水道法第10条は、公共下水道が供用開始された区域内では、住民に公共下水道に流入させるための排水設備の設置を義務づけているため、当地域内で発生する汚水が公共下水道に収容されることになる。
流域下水道は、とくに、水質汚濁の防止を図るという観点から、市町村の行政区域にとらわれることなく、水質保全法に基づく指定水域の流域単位に設置される大規模な公共下水道の幹線管渠および終末処理場である。
特別都市下水路は、中小工場等が多数存在している地域において、公共用水域における水質汚濁の防止を図るという観点から工場排水を集め処理してから放流する施設である。
以上の3種の下水道により、市街地から発生する汚水を処理し、放流することにより、きれいな川、きれいな海をとりもどすことができるのである。
(2) 44年度の下水事業
わが国の下水事業は、下水道整備緊急措置法を根拠法とする第二次下水道整備五か年計画(昭和44年2月21日閣議決定)に基づいて推進されている。計画は42年度を初年度とするもので、その内容は第3-5-5表および第3-5-6表のとおりである。
44年度は五か年計画の第3年次にあたり、総事業費約1,598億円(国費381億円)で事業を実施した。このうち水質汚濁防止対策事業としての公共下水道、流域下水道、特別都市下水路の事業費は、約1,528億円であり、総事業費の約96%にあたる。
公共下水道については総事業費約1,403億円をもって全国225都市で事業を進めた。市街地人口10万人以上の都市(60都市)はすべて公共下水道事業を実施中である。44年度末の全国下水道普及率(排水面積/市街地面積)は、22.1%である。(第3-5-7表参照)。
流域下水道については、総事業費約100億円をもって9か所において事業を実施した(第3-5-8表参照)。このうち猪名川左岸、右岸流域下水道の原田処理場および安威川流域下水道の中央処理場については一部運転を開始した。猪名川左岸、右岸流域下水道は伊丹市、豊中市、池田市の汚水処理を受けもっている。安威川流域下水道は、1日ピーク60万人の入場者が見こまれる万博博覧会場の汚水を引き受けるものであり。安威川、下流の神崎川の水質汚濁の防止に寄与することができる。
44年新たに着手して流域下水道事業は、武庫川流域下水道および相模川流域下水道の事業である。
相模川流域下水道事業は、相模川流域の人口増加に伴う近年の著しい汚濁の進行に対処するためのものであり、武庫川流域下水道は尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市等阪神間の人口過密地帯から排出される汚水による武庫川の水質汚濁を防ぐためのものである。
特別都市下水路については総事業費約26億円をもって9か所で事業を実施した(第3-5-9表参照)。
44年度に新規に着手したのは神栖村その他の鹿島地区、市原市、浜田市の三か所である。とくに鹿島地区は今後の発展が期待される工業団地であり、先行的に廃水処理施設を建設しようとするものである。
(3) 調査の実施
昭和44年度には下水道事業を円滑に進めるのに必要な各種の調査を実施した。主なテーマは次のとおりである。
イ 下水道処理施設設計の合理化に関する調査
ロ 下水汚泥の処理処分に関する調査
ハ 琵琶湖の将来水質の予測調査
ニ 琵琶湖周辺下水道基本計画に関する調査
ホ 千葉県手賀沼流域下水道調査
ヘ 諏訪湖流域下水道調査