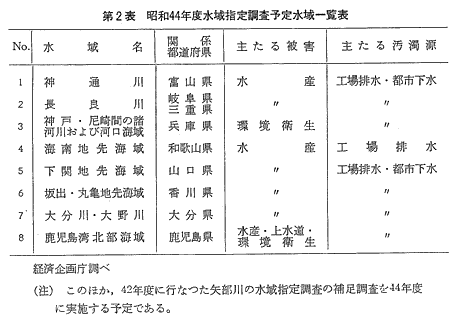
1 水質保全法および工場排水規制法等の施行
(1) 公共用水域の水質調査の実施
昭和44年度においては、公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)に基づく指定水域の指定および水質基準の設定の円滑な実施を図るため、従来に引き続き2,200万円の予算を計上し、指定調査(概括的な調査により、水質汚濁問題の所在をは握するとともに、水質の規制に関して必要な資料を作成するための調査)を8水域について、また基準設定調査(具体的に水質基準を設定するための詳細な調査)を11水域について、それぞれ実施する(第2表および第3表参照)。
さらに、特殊問題調査(全国的に問題となつている事項に関し、あらかじめ所要の調査を行なうことにより、その後の指定調査、基準設定調査の促進を図るための調査)として、潮汐流等による工場排水等の希釈、拡散の状況等をは握することにより、近時大きくクローズ・アップされている沿岸海域港湾等の水質汚濁問題に解決を与えるため、重点的に海域特性調査を実施するとともに、石油化学等に係る廃液の処理に関して、産業排水処理標準調査を行なう。
(2) 水質基準設定後の指定水域の水質調査の実施
すでに水質基準が設定されている水域について、その後の水質の状況を監視し、問題があれば水質基準の改訂等の適切な措置を講ずるため、水質保全調査(アフターケア調査)を実施する。特に昭和44年度においては、1,800万円の予算を確保して、一般水域(39水域を予定)について年12回にわたり上記の調査を行なうほか、新たにメチル水銀の排出規制に係る水域(37水域を予定)についても、所要の基準地点を中心に重点的なアフターケア調査を実施する。
(3) 指定水域の指定と水質基準の設定
すでに実施された公共用水域の水質調査をもとに、所要の解析、検討を加えて、44年度においては、五ヶ瀬川、大竹岩国地先海域等10水域程度について、指定水域の指定と水質基準の設定を進める(第4表参照)。
また、メチル水銀については、塩ビモノマーおよびか性ソーダ製造業に関して、その排水中に「検出されてはならない」旨の水質規制を行なつたところであるが、さらに、これら業種以外の水銀使用工場に関し、メチル水銀を排出するおそれがあるかどうかを、引き続き水質審議会水銀部会において所要の調査審議を加えるとともに、メチル水銀以外の有機水銀および無機水銀についても、関係各省庁とともに工場排水の実態、公衆衛生上への被害の実情等所要の調査分析を加える。
また、カドミウムについても、通商産業省では鉱山保安法に基づき、全国10か所の鉱山保安監督局・部を通じて、鉱山および精錬所を定期的に巡回監督しており、利水地点におけるカドミウム濃度が、世界保健機構の水質基準(0.01ppm以下)を満足するよう今後とも指導していくとともに、厚生省と通商産業省において現在進められている防止対策についての調査研究の結論を待ち、必要に応じて水質基準の設定等の措置を講ずる。
なお、上記のほか大淀川、志布志湾等にみられるでん粉排水による水質汚濁問題の解決を図るため、すでにでん粉部会において結論を得た基本的考え方にのつとりつつ、所要の水質基準の設定を行なう。
(4) 工場排水規制法等の施行
水質保全法に基づきすでに水質基準が設定され、または今後設定される指定水域に排出する工場、事業場について、当該水質基準を遵守させるよう工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)等に基づき、引き続き所要の指導監督を行なう。
(5) 水質基準の対象事業場の範囲の拡大等
近年における水質汚濁源の多様化等の傾向に対処し、水質基準が適用される事業場の範囲を拡大することとし、従来からの工場、鉱山等に加えて、へい獣処理場等、採石場、と畜場、廃油処理施設を設置する事業場および砂利採取場を追加するとともに、し尿処理施設、養豚施設、養鶏施設等を設置する事業場を政令で指定して追加するみちを開くこととするほか、公害対策基本法の趣旨に即して、水質保全法の目的等につき所要の改正を行なうこととし、同法の一部改正法案を第61回国会に提出している。