平成17年度循環型社会の形成の状況
序章 世界に発信する我が国の循環型社会づくりへの改革 -我が国と世界をつなげる「3R」の環-
はじめに
平成16年6月に米国・シーアイランドで開催された主要国首脳会議(G8サミット)で我が国の小泉首相は、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再利用(リサイクル)の3Rの取組を通じて、地球規模での循環型社会づくりを推進しようという「3Rイニシアティブ」を提唱し、G8の各国首脳の間で合意されました。
これを受けて平成17年4月に東京で開催された3Rイニシアティブ閣僚会合において、我が国は「3Rを通じた循環型社会の構築を国際的に推進するための日本の行動計画」(ゴミゼロ国際化行動計画)を発表しました。
この国際化行動計画では、主にアジア地域での様々な取組を中心に、国際的な視野での循環型社会の実現に向けた取組を提唱しており、そのため我が国においても循環型社会の実現に向けた取組を着実に進めることとしています。
我が国は、60数年前、第二次世界大戦による焼け野原の時代を経験し、その中から世界史にもまれに見る経済復興を遂げました。この過程で様々な困難な廃棄物問題を経験し、これを解決していくため、関係主体が様々な努力を積み重ねてきています。
これらの経験は、循環型社会形成のために努力されている世界の国々にとって必ずや参考となると思います。
本年度の白書は、我が国の循環型社会づくりへの経験と困難に際しての改革への取組を世界に発信するために取りまとめました。併せて、廃棄物などの国際循環をめぐる状況などを踏まえた国際的な循環型社会形成の考え方と我が国の役割を示していきたいと思います。
第1節 廃棄物政策の改革以前の状況 -戦後から平成初頭にかけて-
我が国のものの流れ(物質フロー)をみると、輸出される資源は極端に少ない一方で、我が国で消費・蓄積される資源が非常に多くなっています。資源の少ない我が国が持続可能な発展を続けていくためには、この問題を直視し、廃棄物*1を含む限りある資源をいかに有効に利用するかが大きな課題となっています。
しかしながら、第二次大戦の焼け跡から再出発した我が国では、より豊かな生活を求めて経済発展を進め、企業の利潤・利益や個人の利便が優先される中で、「生産活動にとってマイナスでしかない」廃棄物の発生抑制やリサイクル、最終処分などの適正処理に費用を投資するというコンセンサスは定着していませんでした。大量の廃棄物が排出される中で、その処理は単なる焼却や埋立てという方法により、とにかく目の前から消すということが優先されていました。
この結果、廃棄物の不法投棄などの不適正な処理を原因とした種々の環境汚染が続出し、また、廃棄物をめぐる国民の不安、不信が高まりました。こうした中で、例えば、当初は有用な物質として大量に使用されたポリ塩化ビフェニル(PCB)のように、後に有害性が判明したにもかかわらず、その処理が滞るといった事例も発生しました。
*1 廃棄物とは、我が国の法制度では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」と定義されています(廃棄物処理法第2条第1項)。廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など法令で定められた20種類のものと輸入された廃棄物を産業廃棄物とし、家庭から排出される家庭系ごみなど、それ以外の廃棄物を一般廃棄物としています(廃棄物処理法第2条第2項、第4項)。
1. 廃棄物の処理に向けた当時の枠組み
廃棄物の問題は、戦後当初は、汚物による公衆衛生の問題を解決する「衛生問題」としてとらえられており、その観点から、昭和29年に清掃法*2が制定されました。その後、高度成長期などに廃棄物問題が質的にも量的にも深刻化するにつれて、廃棄物問題が衛生問題に止まらず、公害問題への対応も含めた広い「環境問題」として認識されるようになり、昭和45年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」*3により、産業廃棄物も含めた廃棄物の処理責任や処理基準が明確化されるなど、廃棄物処理の枠組みが整備されてきました。
*2 清掃法(昭和29年4月法律第72号)は、明治33年に制定された「汚物掃除法」を廃止して昭和29年に制定され、「汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図ること」を目的とし、清潔の保持や公衆衛生的見地からの措置に重点が置かれていました。
*3 昭和45年12月法律第137号。
(1) 戦後から高度成長期にかけて
ア 「公衆衛生の問題」としての廃棄物問題
第二次大戦によりゼロからの出発となった我が国では、都市への人口の流入等により排出量が増加するなど、都市部を中心としてごみ*4の処分が大きな問題となってきました。また、化学肥料の普及等により、し尿を肥料として利用しなくなったため、し尿の処理が問題になってきました。この当時、ごみ、し尿は海洋投棄や土地投棄処分に頼っており、ごみの処分場は蚊、はえの発生がひどく、不衛生な状態でした。
こうした中で、昭和29年、「清掃法」が施行されましたが、この法律では「汚物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上をはかること」を目的とすると規定した上で、清掃事業の実施主体を市町村におき、市街地を中心とする特別清掃区域の制度を設けて処理区域の明確化を図るなど体制の整備を図ったものです。当時は、ごみ、し尿を「汚物」と称し、衛生的で快適な生活環境を保持することを目的に、公衆衛生的な見地から汚物を処理しようとするものでした。
昭和31年度の「厚生白書」においては「ごみ処理の不徹底は、はえ、悪臭の発生源となるなど、国民の生活環境はいたるところ汚染され、健康に悪影響をもたらしている」と記述されています*5。このように、ごみの問題は、はえや蚊の発生に代表される公衆衛生の問題として捉えられていました。
*4 本白書では、現在の廃棄物処理法の枠組みにより、一般廃棄物のうち、し尿を除いたものを「ごみ」としています。なお、廃棄物処理法による廃棄物の分類については、第1章第1節2.(1)廃棄物の区分を参照ください。
*5 昭和31年度厚生白書第2章第5節1.環境衛生より。
イ 高度成長期での廃棄物問題の変化
昭和30年代から昭和40年代中頃にかけて、我が国経済は戦後の復興期を脱し高度成長期に入りました。昭和43年には国民総生産(GNP)が資本主義国家の中で第2位に達し、また昭和30年の一人当たり国民所得81,797円が昭和45年には561,734円になるなど*6、経済の規模は大きく拡大し、これに伴い国民生活も大きく変化しました。
国民生活の変化は、廃棄物の問題にも大きく影響を与えました。所得の増加は、国民の消費活動を利便性の追求に向かわせ、「三種の神器」と称されたテレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機に代表される家庭の電化が進みました。特に、テレビの普及は、団地という居住形態に代表される都市型の生活スタイルが全国に拡大する一因になるとともに、大量に流される製品などの宣伝を通じて視聴者の購買意欲を増加させ、大量消費へとつながる一因にもなりました。
この時期には、数多くの新製品が登場しました。例えば、昭和45年の工業生産のうち、昭和25年以降に生産指数に採用された商品の割合が40%を超えているなど、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の三種の神器に代表される数多くの新商品の登場は、物質的に豊かな社会の実現を進めたと言えます。一方で、これらは大量生産-大量消費というプロセスによって生み出されたもので、次々に現れる新商品やニューモデルといったものが既存の商品を陳腐化させ、結果として、廃棄物の増加がみられました。
また、昭和20年代後半に登場したスーパーマーケットに代表されるセルフサービス方式による大量販売は、経費率が低いことなどから商品単価が安いことを特長に、都市部を中心に高い成長を遂げました。この結果、電気冷蔵庫の普及による食料品の長期保存が可能となったことと相まって、従来の小口毎日買いなどの消費者行動からまとめ買いによる行動へとの変化を促し、ともすれば買いすぎによる無駄を生じさせる一因となりました。
こうした生活の変化が進んだ昭和30年代後半になると、人口流入が進んだ都市部を中心に、ごみの排出量が大きく増加していきました。この頃になると、ごみの焼却処分が増えてきましたが、その処分方法をみると、4割近くが、覆土等を施す埋立ではなく、素掘埋立、山間投棄等の処分となっていました*7。もともと高温多湿な我が国においては、生ごみがそのまま埋め立てられると、大量のはえ・蚊の発生を招きます。このため、町内会・自治会などの地区組織により、その駆逐のための活動が行われていました。また、国土が狭小な我が国では、埋立地の確保は重要な問題となってきました。
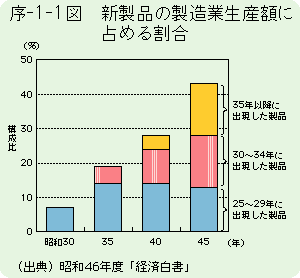
こうした状況を踏まえ、我が国の立地条件からは、埋立地の確保は困難であり、またごみだけではなく、汚水・し尿の処理施設の整備の立ち後れが目立つこととなったことから、昭和38年に、「生活環境施設整備緊急措置法」が公布され、政府はこれに基づき、「生活環境施設整備第一次五箇年計画」を策定し*8、都市などでのごみは原則として焼却処理した後、残さを埋立処分する方針を示しました。
我が国がごみの処理の基本として、焼却を経た残さの埋立処分を行うこととしたねらいは、あくまでも焼却により衛生的に安定化した上で、廃棄物を減量化することにありました。この観点から、焼却処理による減量化は有効な手段でした。
*6 昭和46年度経済白書による。
*7 昭和38年度厚生白書第2生活環境の整備1.下水、し尿及びごみ処理(4)ごみ処理の現状より。
*8 同計画は、昭和40年に閣議決定されています。
コラム1 夢の島のはえの大発生

昭和40年7月、東京都の湾岸地域である江東区の海上埋立地である夢の島ではえが大量発生しました。この年は猛暑であったため、焼却されない生ごみを餌として異常発生したのです。近隣の小学校では、給食時にはえ叩きが必要だったほどで、ヘリコプターによる薬剤散布も間に合わず、ついには重油を撒いての焼き払いが行われました。

しかしながら、我が国の経済成長とそれに伴うごみの増加は、市町村の清掃関係者の予測をはるかに超えるものだったと考えられます。整備計画に基づき焼却施設の整備が精力的に進められましたが、1人1日当たりごみの排出量の伸びは、昭和40年代前半には、年平均約6%で推移し、依然として直接の埋立処分量が減少しない状況が続きました。
また、この頃になると、ごみの質にも変化があらわれました。粗大ごみとプラスチック廃棄物といった、焼却などの処理が困難な廃棄物の増加です。
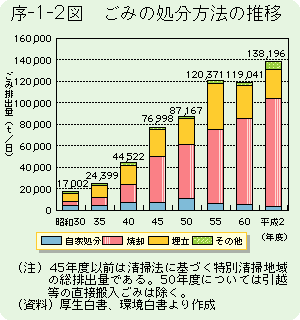
耐久消費財を中心とした粗大ごみには、不燃物が多く含まれているため、焼却になじまず、また、プラスチック廃棄物は、セルロース系のごみと比較すると数倍から10倍の燃焼発熱量を有するため、燃焼炉内の温度が高温になることから、炉材を損傷することになり、また分解しにくいため自然の循環メカニズムの中に組み込みにくく、埋立てにも向かない廃棄物です。
特に、プラスチック類はその生産量が昭和40年代前半の年平均伸び率が約25%にも達し、さらには当時のごみ処理施設の性能からみてプラスチックの混入率の限界である10%に近づく地方公共団体が増加するなど、市町村の清掃事業にとって困難な舵取りを迫られる事態となりました。
(2) 高度経済成長期以降からバブル期まで
ア 廃棄物処理法の枠組みの形成
我が国の高度経済成長は、家庭から出るごみの中での粗大ごみやプラスチック廃棄物の増加といったごみの質の問題以外にも、事業者の生産活動によって生じる産業廃棄物の問題をもたらしました。
産業廃棄物は、当時の清掃法の枠組みでは対応できず、地域内・工場内蓄積として、あるいは企業の努力により処分されてきていましたが、都市化の進展と最終処分場(埋立地)のひっ迫により、適正な処理が行われない場合が増加し、例えば、廃油の不適正な処理による水質の汚濁などが問題になり始めました。また、その発生量は、昭和42年当時、1日当たり約120万tと推定され、家庭ごみ5万tの24倍に相当するものと見積もられていました*9。これらの産業廃棄物は不燃性のものが多く、また、環境汚染を防止するため特殊な処理を必要とするものも多いため、市町村の処理体系では対応できない状況でした。
このため、昭和45年のいわゆる「公害国会」で清掃法を廃止して廃棄物処理法が制定され、同法は昭和46年9月末に施行され、現在の廃棄物処理体系が整備される出発点となりました。清掃法との大きな違いは、法の目的に、衛生問題としての処理に加えて公害問題への対応も含めて「生活環境の保全」を行うことを打ち出すとともに、事業者による廃棄物の処理責任を明確化しました。
廃棄物処理法では、廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分して定義されることとなり、初めて法制度上に産業廃棄物が位置付けられることとなりました。その上で、他の公害法規と同様に、汚染者負担の原則に基づいて、事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者が処理責任を有することとされました。さらに、事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならないこととされ、製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者としての責務も定められました。
また、廃棄物の処理体制も大きく変化しました。一般廃棄物の処理は従前どおり市町村の責任とされましたが、従来の清掃法による特別清掃地域の指定制度が廃止され、原則として市町村全域が一般廃棄物処理の対象地域となりました。新たに位置付けられた産業廃棄物については、環境を汚染する原因となり得る廃棄物であって市町村の清掃事業の処理体系になじまないため、事業者による処理を原則とし、事業者の個別処理又は共同処理を中心とする産業廃棄物の処理体系を確立し、これを通じた処理に委ねることとされました*10。
*9 昭和44年度厚生白書 各論第2章第2節「4都市・産業廃棄物の処理・処分問題」による。
*10 事業系の一般廃棄物については、市町村が処理を行うものの、最終的な処理責任は事業者にあることとされています。
イ 有害廃棄物の処理基準の設定
有害な産業廃棄物の処分は、公害問題への関心の高まりの中で、当時は最大の問題となっていました。このため、昭和46年の廃棄物処理法の施行時から、水銀、カドミウム等の有害物質を含む汚泥及び鉱さいの最終処分に関して人の健康保護に万全を期する見地から特に厳しい基準を設けていました。例えば、水銀又はその化合物を含む汚泥の埋立処分を行う場合は、あらかじめコンクリート固化を行い、当該水銀若しくはその化合物が漏れないようにすることなどとされていました。
その後、昭和48年の施行令改正により、埋立処分又は海洋投入処分を行おうとする有害物質を含む汚泥等の産業廃棄物のうち、有害物質として取り扱うものの判定基準が設けられました*11。
*11 実際の処理基準としては、「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」及び「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」が定められました。
ウ 廃棄物問題の社会問題としての深刻化
このように、廃棄物処理法の制定により、産業廃棄物についての定義が明確化され、廃棄物の全体について、その処理責任や処理基準も明確化されましたが、この当時、処理の実態は十分に把握されておらず、不適正な処理が発生していました。「廃棄物の保管不備、不適正な処理又は無許可の業者による不法投棄等により生活環境の保全に影響を与える事例が頻発している」と昭和49年度の環境白書には記述されています*12。こうした中で、当時から排出量で多くを占めていた産業廃棄物の不法投棄などの問題が大きな問題であり、一般廃棄物については、その処理責任を負っている地方公共団体間で、最終処分場の確保をめぐっての対立が生じました。
産業廃棄物は新たに法的に位置付けられたこともあり、その処理の実態を的確に把握する仕組みが不十分だったため、行政庁による監視・指導も不徹底になり、不法投棄などの違法行為が後を絶たないなど、排出事業者の責任が徹底されていないといった問題がありました。また、廃棄物の最終処分地の確保が困難となっている中で、工場敷地内での野積み状態での放置も増加していました。こうした状況を端的に表した事例として、昭和50年夏、東京都内の重クロム酸ソーダ等六価クロム*13化合物製造工場における六価クロム含有鉱さいの埋立処分とそれに伴う周辺の環境汚染、さらには住民の健康障害のおそれが問題となりました。これを発端として他の地域でも広く六価クロム鉱さいによる汚染の事実が発見されたため、大きな社会問題となりました。この問題自体は廃棄物処理法施行以前に起こった事例でしたが、これをひとつの契機として、産業廃棄物の処理の実態や制度の在り方について様々な問題が指摘されました。
また、一般廃棄物についても、全ての地域で十分な処理能力が確保できるとは限りませんでした。公害問題が発生し、環境汚染への国民の意識が高まる中で、ごみの処分をめぐって、ごみは発生した地域内で処分すべきという自区域内処理の考え方が広まり、最終処分場を持たない地方公共団体と、ごみの搬入を阻止しようという地方公共団体との間で紛争が生じる場合も生じました。
*12 昭和49年度環境白書第4章第5節1「廃棄物処理の現況」による。
*13 クロムは銀白色の光沢のある耐食性、耐熱性、対摩耗性に優れた金属で、ステンレス鋼の重要成分として利用され、酸化されて三価や六価のイオンとなると、毒性を持ちます。六価クロムは人工的に生成され、強い酸化剤で金属メッキ、皮なめし、顔料などで広く用いられますが、クロム潰瘍、鼻中隔穿孔、感作性皮膚炎、肺がんなどの原因となります。
コラム 2 東京ごみ戦争

公害が社会的問題となっている中、それを象徴するような廃棄物問題が起きます。昭和46年から始まったいわゆる「東京ごみ戦争」です。当時の東京都のごみの最終処分場は、江東区内(新夢の島:現在「若洲海浜公園」)にありましたが、まだ焼却処分が進んでいなかったため、家庭の生ごみの一部も直接埋立が行われていました。そのため、中間処理として焼却処分を行う焼却場である杉並清掃工場建設計画が立てられましたが、杉並区の周辺住民が反対運動を起こしたのです。このため江東区は杉並区からのごみの受入を拒否し、深刻な社会問題となりました。これを契機に埋立処分に対する問題点が浮き彫りになり、焼却処分と自区域内処理への大きな流れが出来ていきました。

このように廃棄物問題が社会問題化する中で、迅速に対応を進めていく必要が生じていました。廃棄物処理法の制定後、廃棄物の適正処理の確保のための各種の基準が策定され、 法制度の整備が進められていましたが、昭和51年には、排出事業者・処理業者の責任の確実な遂行や、適正な最終処分を確保する観点からの規制強化*14を中心とする廃棄物処理法の改正が行われました。さらに、この法改正を受け、昭和52年には、廃棄物の内容に応じた最終処分場の方式として、遮断型、安定型、管理型の3類型の類型を定めたほか*15、それぞれの類型に応じた構造・維持管理上の基準を設定した「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」が定められました。
また、こうした法制度面の整備と一体となって、市町村の一般廃棄物処理施設の整備に対する国庫補助や産業廃棄物処理施設の整備に対する低利融資、税制特例措置などにより、処理施設の整備を始めとした基盤の整備が進められました。また、処理技術の点でも、現在広く普及しているストーカー式連続焼却炉が登場し、安定して連続的にごみを燃やせることから、その普及が進んでいきました。
*14 具体的には、排出事業者などの責任追及の制度としては、措置命令規定の創設、処理業の委託基準の設定、処理責任者による処理記録の記録保存などを行いました。また、適正な最終処分の確保の観点からは、届出制の創設、技術基準による事前調査などを行いました。
*15 産業廃棄物の最終処分場については、有害な産業廃棄物を埋立処分するための遮断型、廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず等その性質が安定しており生活環境保全上の支障を及ぼすおそれが少ない産業廃棄物を埋立処分するための安定型、及びこれら以外の生活環境の保全上の支障を防止するための措置を講ずる必要がある産業廃棄物を埋立処分するための管理型の3類型に区分されました。また、一般廃棄物の最終処分場は基本的に管理型とされました。
(3) バブル期
その後、2度にわたる石油危機により経済が停滞し、廃棄物の発生量も一時的に減少していましたが、昭和60年のプラザ合意を契機に、いわゆるバブル景気(昭和60年代から平成初頭の好景気)が起こります。好景気による株や土地への投機の過熱は、経済全体に波及し、これと相まって廃棄物の発生量は再び増加傾向に転じました。
ア バブル景気による質・量両面での廃棄物問題の拡大
この頃になると、消費活動の拡大・多様化や技術革新の進展等を反映して、排出される廃棄物も多様化し、乾電池や大型化したテレビ、冷蔵庫などの家電製品といった、質的にも量的にも適正処理が困難な廃棄物が増大しました。
また、生活スタイルにも大きな変化が現れました。高度成長期の豊かな時代に就職した世代が社会の中心につき、これらの世代は画一的な様式よりも多様な生活スタイルを求める傾向にありました。このような変化は商品の少量多品種化と多頻度流通の傾向を高め、これらの販売に際しプラスチック容器や包装紙の使用が多くなりました。昭和40年代後半に登場し、店舗の増加と24時間営業の拡大等により急成長したコンビニエンスストアの成長は、この少量多頻度流通の一例と言えるでしょう。合成樹脂びん(ペット(PET)ボトル)の普及が拡大し始めたのもこの頃です。
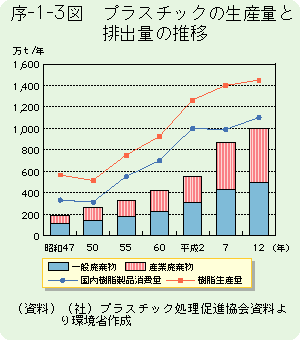
市町村が収集する廃棄物には事業系の紙ごみも含まれます。OA化の進展等を背景にコピー用紙や電算用紙等からなるオフィスからの紙ごみの発生量も増加しました。
また、産業廃棄物についても、土地の資産価値の増大を背景に、都市域における住宅・オフィスビルの需要が増大し、土木・建築工事が盛んとなり、それに伴う建設廃材などの発生量も増加しました。
バブル景気は平成3年頃まで続き、その後、縮小に向かいますが、廃棄物の排出量はその後も横ばいで推移していくこととなります。
イ 廃棄物処理に伴う有害物質による社会問題の発生
昭和58年、東京都公害研究所は、水銀、アルカリ、マンガンなどの水銀を含む乾電池が使用済みとなった後、ごみとして廃棄され、焼却・埋立処分される過程で、水銀による環境汚染のおそれがあるとの調査結果を発表し*16、大きな社会問題となりました。また、同時期に、都市ごみ焼却炉の焼却灰からダイオキシン類を検出したとの新聞報道がなされ*17、廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策が大きな課題となりました。
我が国では、最終処分場の確保が困難であるため、このため、中間処理として、焼却処分や圧縮、破砕等により減量化が図られています。特に、都市ごみを衛生的に処理する観点から、廃棄物の焼却処理が進められてきたことは前に述べたとおりです。昭和40年代当時、廃棄物の処理で問題となっていたのは、生ごみの悪臭、はえの大量発生、水質汚染などでした。しかし、有害物質を含む廃棄物の混入は、廃棄物の焼却過程におけるダイオキシンの発生や有害物質による環境汚染の問題を提起したのです。
廃棄物を焼却し、減量化を進めたとしても、焼却灰を適正に最終処分することが必要になります。バブル期の廃棄物量の急増は、最終処分場のひっ迫に拍車をかけました。しかしながら、新規の処分場の設置は地価の高騰による用地難や周辺住民の反対等により一層困難な状況になりました。特に人口や産業が過度に集中した大都市圏においては廃棄物の増加のスピードが早いことに加え、用地を確保することが難しいことから、施設整備も進まないため、さらに厳しい状況となりました。
また、個々の市町村が自区域内に最終処分場を確保することが困難な場合、他の市町村の最終処分場に廃棄物を持ち込まざるを得ず、広域的に移動します。事業者の責任で処理される産業廃棄物の場合には、一般廃棄物以上に広域に移動し、これらの産業廃棄物は、山林、原野等に捨てられる事件が多発しました。
*16 平成13年度 循環型社会白書 「コラム12 廃乾電池問題」より。
*17 本白書第1章第4節7.「ダイオキシン類の排出抑制」より。
2. 廃棄物の不適正な処理の事案の発生
1.では戦後からバブル期(昭和20年代から平成初頭)までを概観しました。高度成長期以後も経済活動は拡大し、我が国では物質的に極めて豊かな社会が実現されましたが、その反面、大量消費、使い捨ての生活が一般化するという社会的な変化が生じ、こうした変化を反映した廃棄物の量の増大、質の多様化のため、廃棄物の適正処理が困難となってきました。予想を超えて増大するごみを前にして「とにかく目の前から片付けなければ」と事後処理的・対症療法的に関係者が対応せざるを得なかった感は否めません。
(1) 不法投棄に代表される廃棄物の不適正処理の問題
廃棄物の不当投棄などの不適正処理は、廃棄物中に重金属や有機塩素化合物等の有害物質が含まれている場合には、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染を引き起こすほか、投棄された土地の原状回復には多額の費用が発生することとなります。しかしながら、廃棄物の量の増大や廃棄物処理費用の上昇、最終処分場のひっ迫などの要因により不法投棄や悪質な不適正処理は後を絶たない状況でした。こうした状況を表す代表事例としては、この当時発生した大規模不適正事例のうち、香川県豊島の不法投棄事案と福島県いわき市での不適正保管事案が挙げられます。
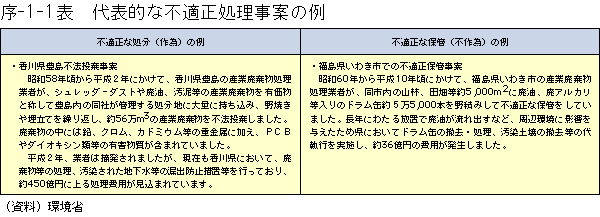
これらの例を見ても分かるとおり、廃棄物の不適正処理は、環境汚染等を通じて人々の健康や暮らしに多大な影響を及ぼすばかりでなく、その原状回復等には巨額の費用が発生します。
しかしながら、当時は、
1) 廃棄物の処理が適正になされているかかどうかは、廃棄物処理業者の問題であり、排出事業者の直接の生産活動に影響しないものと考えられていたこと、
2) 廃棄物自体には経済的な価値がないことから、その処理に排出事業者が適正な費用を負担する経済的なインセンティブが働きにくいこと
から、不適正でも、安価に処理を請け負う廃棄物処理業者に顧客が流れるといった、いわば「悪貨が良貨を駆逐する」といった傾向となっていました。この結果、水・大気環境の汚染をももたらす廃棄物の不法投棄が発生していました。
このような廃棄物の不適正な処理が発生する要因としては、当時の法制度などの面で、
1) 排出事業者が、自らが排出した産業廃棄物が、最終的にどこでどのように処分されているか処理経路の各段階で確認するシステムがなかったこと、
2) 特に多量に廃棄物を排出する事業者について、排出する廃棄物の量や適正処理の取組が計画的に行われていなかったこと、
3) 暴力団関係者などが経営に関与した悪質な廃棄物処理業者が、排除されなかったことなどの問題がありました。
繰り返し報道される廃棄物の不法投棄などの問題は、適正な処理を行うために必要な廃棄物処理施設の建設に対しても国民の疑念を抱かせる結果となり、適正な処理施設の不足が一層不法投棄を生むといった悪循環を生じさせることとなっていました。
(2) PCB問題
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器を始め幅広い用途に使用され、国内では、昭和47年までに約54,000tのPCBが使用されました。しかし、昭和43年に発生したライスオイルにPCBが混入したことによって西日本で中毒症状が多発したいわゆる「カネミ油症事件」を契機に、生体内に蓄積しやすく、皮膚障害などを起こすといったPCBの毒性が社会問題化し、昭和49年に新たな製造や使用が禁止されました。
こうした状況に対応し、昭和48年に設立された(財)電機ピーシービー処理協会が中心となって、PCB焼却処理施設の設置の動きが幾度かありましたが、焼却処理に伴って発生する排ガスなどへの住民の強い不安を払拭することができず、施設の設置に周辺住民などの理解が得られませんでした。
このため、大量のPCBは、結果として、ほぼ30年にわたり処理されずに保管され、その間に紛失したり保管状況が劣悪なものなどが判明し、環境汚染の危険性が指摘されました。