第2節 3Rの推進に向けた取組の現状と課題
前節での我が国のごみをめぐる状況を踏まえ、この節では、3Rの推進に向けた具体的な取組の現状と課題について見ていきたいと思います。
1. リデュース(発生抑制)対策
リデュースとは、必要のないものは買わない、使い捨てのものなどごみになりそうなものは利用しないこと等により、ごみの量を「減らす」ことです。ごみ問題のみならず、環境問題全般にとって、最も重要で効果的な取組です。
新しいものや流行を追いかけるという現在の生活様式の中で、リデュースはなかなか難しいという意見もあると思いますが、コンビニエンスストアでレジ袋や不要な割りばしを断るといった小さな行為も立派なリデュース対策です。このように我々国民一人ひとりにできることは身近なところにたくさんあります。
しかしながら、前節で見たように、ごみの排出量の削減は進んでおらず、循環型社会を実現する上で最も優先すべきとされているリデュースを推進するため、今後、対策を一層充実していく必要があります。
このため、環境省では、ごみのリデュース対策の推進のための重要な課題として、1)ごみ処理の有料化の推進、2)国民一人ひとりのライフスタイルの見直しにつながる効果的な普及啓発、3)容器包装におけるリデュースの取組等について検討してきました。
ここでは、ごみのリデュースの現状と取組や上記の課題の検討状況について見ていきたtxtいと思います。
(1) ごみのリデュースの現状と取組
ア ごみのリデュース対策の現状
ごみのリデュースに係る目標としては、循環型社会基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画(循環型社会基本計画)及び廃棄物処理法に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(廃棄物処理基本方針)に基づくものがあります(序-2-1表)。
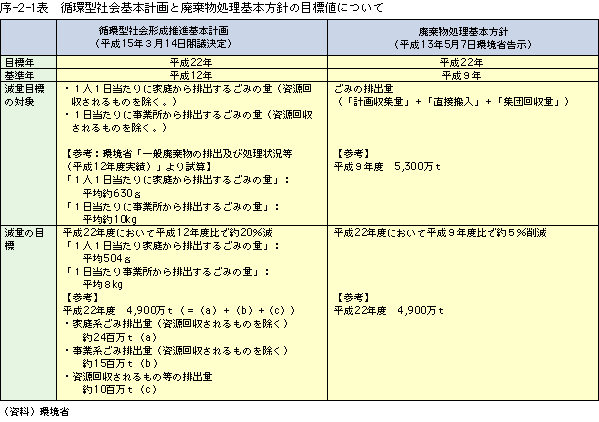
(ア)循環型社会基本計画に掲げられた目標の達成状況
循環型社会基本計画では、1人1日当たりに家庭から排出するごみの量(資源回収されるものを除く。)及び1日当たりに事業所から排出するごみの量(資源回収されるものを除く。)を対象に、平成22年度において平成12年度比で約20%減少させることを目標としています。
平成14年度における1人1日当たりに家庭から排出するごみの量は618gであり、基準年である平成12年度と比較して2.4%減少しています。また、1日当たりに事業所から排出するごみの量は9.3kgであり、基準年である平成12年度と比較して6.1%減少しています。
循環型社会基本計画に掲げられたごみの排出量に関する目標については、1日当たりに事業所から排出するごみの量は順調に削減が進んでいますが、1人1日当たりに家庭から排出するごみの量は基準年と比較すると減少しているものの、目標の達成は容易ではない状況となっています(序-2-2表)。
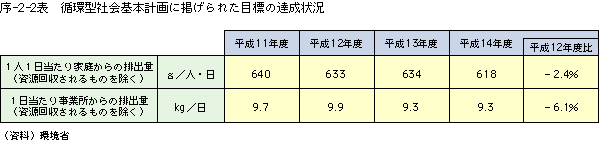
(イ)廃棄物処理基本方針に掲げられた目標の達成状況
廃棄物処理基本方針では、ごみの排出量を対象に、平成22年度において平成9年度(5,300万t)比で約5%減少させることを目標としています。
平成14年度におけるごみの排出量は5,420万tであり、基準年である平成9年度と比較して2.1%増加しています。
廃棄物処理基本方針に掲げられたごみの排出量に関する目標については、平成12年度をピークとして減少傾向に転じたものの、平成14年度においても基準年を上回っており、こちらも目標の達成は容易ではない状況となっています(序-2-3表)。
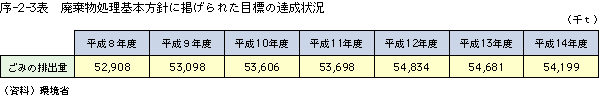
以上を踏まえれば、これらの目標を達成するためには、家庭からのごみの排出量をより一層削減することが最大の課題となっています。
イ 政府の取組
このような状況を踏まえ、ごみのリデュースの推進に向けて、中央環境審議会において検討が進められていましたが、平成17年2月に取りまとめられた意見具申「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について」において、ごみ処理の有料化の推進等に係る提言がありました。これを受けて、廃棄物処理法に基づく基本方針の改正を行うとともに、有料化に伴う様々な問題に関する考え方や、有料化の進め方などについて検討を行っています。
また、国民に対してごみのリデュースを呼びかけるためにマイバッグの使用や、簡易包装の推奨、ライフスタイルの変革を呼びかける普及啓発活動を実施しています。
(2) ごみのコスト分析及び効率化の推進
循環型社会の形成を目指し、リデュース対策を始めとする3R推進の取組や、ごみの処理システムの最適化等を検討する場合には、検討の基礎情報として、ごみ処理に係るコストの分析・評価が重要です。また、昨今、行政サービスの効率化が求められており、コスト面を含めて処理・リサイクルシステムの最適化を図っていく必要があり、その根拠となるコスト情報の提供が重要です。
しかしながら、ごみに係るコストの分析方法については統一的なものがありません。コスト分析を行っている市町村においてもその方法、範囲、区分は一致しておらず、それぞれの金額を相互に比較参照することは容易でないというのが実態です。
循環型社会の形成を進めていくための基礎情報として、標準化された分析方法に従い、各市町村のごみ処理事業コストを開示していくことが望ましいことから、環境省では、コスト分析の対象となる費目の定義、共通経費等の配賦方法、減価償却方法など、コスト分析に係る様々な課題を検討し、標準的な分析手法を提案することとしています。
(3) ごみ処理の有料化の推進
ごみのリデュースについては、ごみ処理の有料化といった経済的手法の活用が有効とされています。特に、本年2月に中央環境審議会において取りまとめられた意見具申においては、「一般廃棄物の発生抑制や再使用を進めていくためには、経済的インセンティブを活用することが重要である。一般廃棄物処理の有料化は、ごみの排出量に応じた負担の公平化が図られること、住民(消費者)の意識改革につながることなどから、一般廃棄物の発生抑制等に有効な手段と考えられ、現に一定の減量効果が確認されているところです。このため、国が方向性を明確に示した上で、地域の実情を踏まえつつ、有料化の導入を推進すべきと考えられる。」との提言がなされています。
ごみ処理の有料化を進めていくため、環境省では、今後、導入時の留意事項等に関するガイドラインを作成して、市町村の取組を支援していくこととしています。以下では、ごみ処理の有料化の現状や課題を紹介します。
ア ごみ処理の有料化の現状
ごみ処理の有料化に関する状況を把握するため、ごみ処理有料化実施の有無、ごみ排出状況等について、平成14年度に全国の市町村及び一部事務組合に対して実施したアンケート調査*4では、約40.0%に当たる1,295の地方公共団体(市町村および一部事務組合)(人口ベースでは75.0%)から回答が得られました。ここでは、その結果を分析していきます。
*4(社)全国都市清掃会議「ごみ処理の有料化に関する全国調査」
1)調査期間 平成15年3月
2)調査対象 全国3,241市区町村
3)有効回答数 1,295市区町村(40%)
(ア)有料化の実施状況
ごみの処理を有料化している市町村の割合は、家庭系ごみ42%(有効回答数1,270市町村中533市町村)、粗大ごみ58.0%(710市町村)、事業系ごみ70.0%(888市町村)であり、家庭系ごみは、人口規模の小さい市町村ほど有料化の割合が高くなり、事業系ごみについては、人口規模が大きい市町村ほど有料化の割合が高くなっています(序-2-1図、序-2-2図、序-2-3図)。
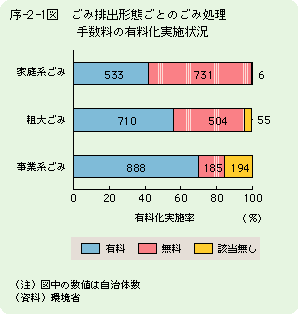
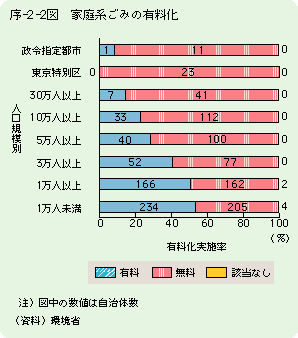
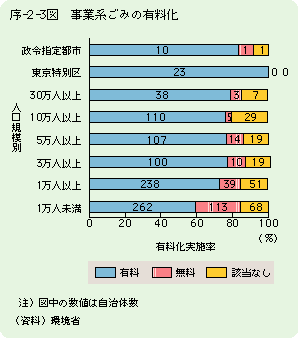
また、家庭系ごみを有料化していない731地方公共団体のうち、有料化を内部的に検討している、あるいは議会に条例案を上程している等有料化を検討しているものは223団体(31.0%)で、事業系ごみを有料化していない185地方公共団体のうち、有料化を検討している団体は78団体(43.0%)でした(序-2-4図)。
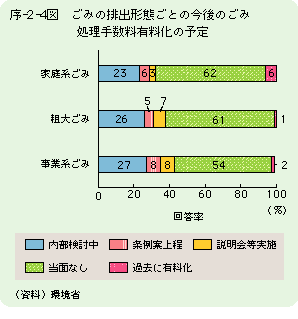
(イ)有料化の目的
家庭系ごみの処理を有料化している533地方公共団体のうち69.0%が、有料化に際して重視した点は、「家庭系ごみの減量化」を挙げています(序-2-5図)。
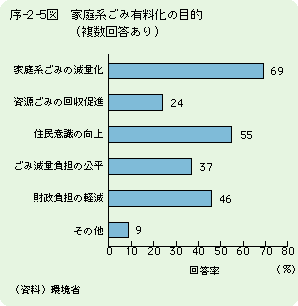
一方、事業系ごみの処理を有料化している888地方公共団体のうち46.0%が、有料化の際に重視した点は、「事業者の責任の徹底」を挙げています(序-2-6図)。
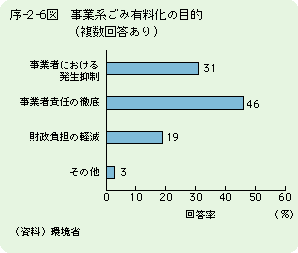
(ウ)有料化の料金体系
a 手数料の徴収方法
家庭系ごみの手数料の徴収方法は、有料指定袋方式が最も多く82%となっています。一方、事業系ごみについては、納入通知書方式が最も多く44%であり、有料指定袋方式は21.0%となっています(序-2-7図)。
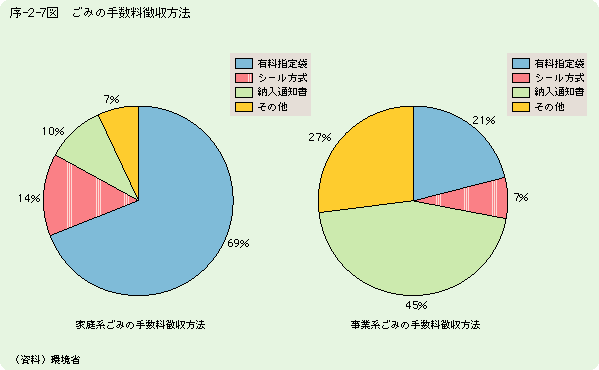
b 料金設定の水準
家庭系ごみ、事業系ごみを有料化している地方公共団体について、料金設定の水準を整理すると、重量ベースで料金を設定している地方公共団体や、容量ベースで料金を設定している地方公共団体の割合は以下のとおりとなっています(序-2-8図、序-2-9図)。
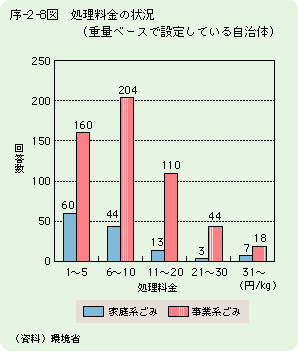
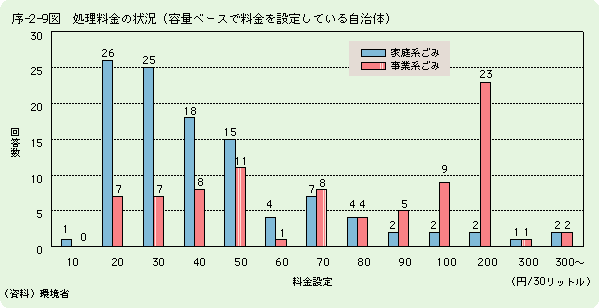
c 料金設定の根拠
料金設定の根拠としては、「他市町村の前例・実績を参考に設定」、「ごみ処理に要する費用(ごみ処理原価)から設定(例えば、費用の一定割合など)」が多くなっています(序-2-10図)。
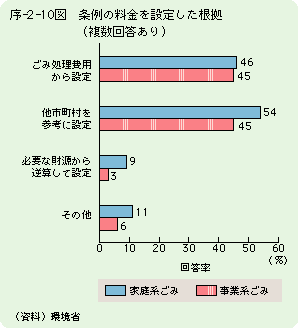
イ 一般的な効果と問題点
(ア)減量効果
ごみ処理の有料化については、ごみ排出量の減量化に有効な手段であると評価する意見がある一方、有料化直後には減量効果が認められるものの、その後徐々に増加する「リバウンド」により、持続的な効果が期待できないという意見もあります。これは、個別の有料化事例について見ると、ごみがほとんど減っていない地方公共団体から約半減しているものまで、かなりのばらつきがあることから、このような論点が生じているものです。
有料化のごみ減量効果に関しては、複数の研究成果をレビューした結果として「比較的人口規模の大きな自治体を含む平均値はやや低いが、これを除く日本の研究では、概ね平均2割前後の家庭系ごみの減量が見られ、米国ではさらに大きな減量が見られている。」とする報告や、有料化している地方公共団体と有料化していない地方公共団体の一人一日当たりの排出量を分析した結果、有料化している地方公共団体の方が、統計的に有意に排出量が少なく、その減量効果も平均的には10年以上の持続性があるとの報告があるなど、一般的には有料化によるごみ減量効果が認められているところです。
ただし、有料化による減量効果を得るためには、料金設定レベルや徴収方法等有料化の方法について、十分な検討を行うことが必要と考えられます。
(イ)住民意識向上
家庭ごみの有料化にかかる住民の意識について東洋大学が行った調査*5によると、有料化時と比較すると有料化後では、有料化を支持する住民が増えている市区が多いとの結果が出ています。
また同様の調査によれば、有料化に伴って行ったごみ減量化対策について、埼玉県与野市(現在はさいたま市)における市民の行った対策の内訳としては、分別や集団資源回収、店頭回収箱へ包装物の投入等のリサイクルが7割となり、残り3割が過剰包装の拒否、ごみにならない商品の選択、買い物袋の持参等のリデュースが挙げられています。これらのリデュース対策を実施した市民のうち3割程度の市民が有料化を契機として取組を開始しています。
*5「東洋大学山谷研究室調査」
1)調査期間 平成12年9月
2)有効回答数 694市区
(ウ)財政面への寄与
アのアンケート調査では、有料化による効果として、財政面への寄与を挙げる団体が、約28.0%あり、厳しい財政事情の中で、有料化は財政面でも意味を持つことがうかがえます。
(エ)その他の効果
比較的人口の多い都市部では、住民に処理コストの応分の負担を求めることを有料化の動機としてあげているところが多く、都市部における処理コストの高さを反映しています。
また、有料化した地方公共団体によると、分別の徹底や分別収集の促進、資源ごみの収集量の増加を有料化の効果として挙げる団体が多く、有料化による住民意識の向上を裏付ける結果となっています(序-2-11図)。
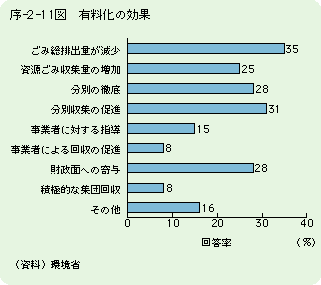
(オ)問題点
家庭系ごみの処理を有料化している533団体において、有料化後に生じた問題・課題としては、「一時的に減量したがもとに戻りつつある」が49.0%、「有料化ルールに違反する排出」が42.0%、「有料化ルール違反以外の不法投棄」が26%となっており、有料化後の「リバウンド」が大きな問題となっていることがうかがえます(序-2-12図)。
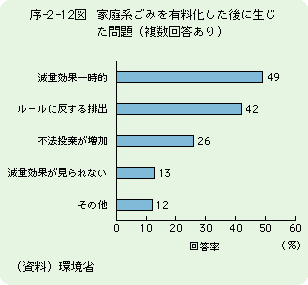
ウ 有料化導入に当たっての留意事項
有料化に当たっては、実際に減量効果が得られるような料金設定及び徴収方法とすることが必要です。これまでの実施事例においては、周辺地方公共団体の料金を参考として決めたり、ごみ処理費用から一定割合を算定することにより決めたりしている場合が多いですが、有料化の目的や効果、コスト分析の結果を十分に検討した上で、料金レベルを決定する必要があります。
また、有料化直後にはごみ排出量が大きく減量されるケースが多いものの、その後徐々に増加する「リバウンド」の抑制や不適正排出、不法投棄の抑制等に関して対策を行い、減量効果を持続させるための総合的施策を展開することが必要であり、有料化の導入効果とともに、ごみ処理コスト等に関する情報開示を進めることが重要となります。
(4) ライフスタイルの見直しに向けた普及啓発
家庭からのごみのリデュースを始めとする3Rの取組を推進するためには、国民のライフスタイルを見直していくことが不可欠となっています。このためには製造事業者や販売事業者においても、使い捨て製品や過剰包装使用の自粛、詰め替え製品や簡易包装の推進、製品の長寿命化、リユースやリサイクルしやすい商品設計等、できるだけ環境負荷の低い製品の開発・提供が必要であり、消費者とのパートナーシップによりレジ袋の削減や環境負荷の低い商品の普及に努めていくことが重要です。
国や地方公共団体は、こうした取組を支援するために必要となる情報の提供や、環境教育、普及啓発活動を実施していく必要があります。
ここでは、こうした普及・啓発の取組の一例として、3Rを推進し、ごみを減らしていくライフスタイルである「リ・スタイル(Re-Style)」をキーワードとした活動を紹介します。
環境省では、平成14年版の循環型社会白書で提唱されたこのリ・スタイルを広く周知するため、WEBマガジン「Re-Style」の発行や、イベントを開催しています。
ア WEBマガジン「Re-Style」(http://www.re-style.jp/)
ごみを減らし、資源をできるだけ有効に活用するためにはどうしたら良いのか、日常生活においてできることや環境に優しいライフスタイルについて分かりやすく情報提供するため、環境省では、WEBマガジン「Re-Style」を平成14年6月に開設しています。
「Re-Style」では、
1) 特定のテーマに関する特集
2) 著名人や芸術家等の日常生活における環境にやさしい取組やライフスタイルなどのインタビュー形式での紹介
3) 環境保全をテーマとするイベント等における取組や時事問題、2)で取り上げられない緊急インタビュー等のレポート
4) リサイクルプラザやリサイクルショップの上手な活用方法等を紹介するコラムをメインコンテンツとし、その他にも身近な情報や取組を検索するためのデータベース等を掲載してライフスタイルのリ・スタイル化に関する情報を提供しています。
イ Re-Style LIVE
Re-Style LIVEは、将来の世代を担う若者を主な対象として、ライフスタイルの変革や環境問題への関心を高めるきっかけをつくるため、著名なアーティスト及びTV、ラジオ、雑誌等の媒体の全面的な協力を得て実施した音楽ライブイベントです。
平成15年10月に第1回、平成17年3月に第2回を実施しましたが、各回とも参加定員を大幅に上回る応募をいただいたため、抽選の結果招待した参加者と協力媒体等の関係招待者を合わせて約3,000人近い参加者を得て大盛況のイベントとなりました。
このイベントでは、環境に配慮したイベントのモデルケースとして、
1) グリーン電力を導入した会場の使用
2) リユースカップ及びリユース食器の使用
・出演者、スタッフ(150名前後)が楽屋でリユースカップを使用
・来場者用のドリンクはリユースカップで販売
・出演者、スタッフ用の食事をリユース食器で供給し、弁当容器や食べ残し等の食品廃棄物等のごみを削減
3) パンフレットやチラシ等の配布物の最小化
4) 関係者通行証、招待券等にリサイクル素材を使用
5) 使い捨ての展示物(パネル等)の不使用等、できる限り環境負荷を低減する工夫を導入しています。これらの取組はイベントの中で紹介し、身近にできる環境にやさしい取組を呼びかけることによって参加者及び出演者の意識啓発を行っています。
また、このイベントは、WEBマガジン「Re-Style」内に特設ページを設けて参加者の募集を行い、マイ箸による割りばしの削減やエコバッグによるレジ袋の削減といった併設プロジェクトの実施、出演者へのインタビューやイベントに関する様々なレポート等を掲載するなど、WEBマガジン「Re-Style」との連携のもとで実施されています。

(5) 容器包装におけるリデュースの取組
ア 中央環境審議会等の審議状況
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)においては、法律の施行後10年を経過した場合において、法制度の評価・検討を行い、必要に応じて見直しを行うことが規定されています。これを受けて平成16年7月より中央環境審議会等において、容器包装リサイクル制度に関する審議を開始し、関係者からのヒアリング等も踏まえて、主な論点(排出抑制及び再使用の推進について、分別収集の在り方について、再商品化手法について及び「その他」の論点について)を整理しました。現在、これらの論点に沿って審議が進められているところであり、本年6月末には中間報告が取りまとめられる予定です。
中央環境審議会においては、容器包装のリデュースについても、論点の一つとして議論が行われています。容器包装リサイクル法は、3Rの全てに密接に関連していますが、リデュースの観点からは、以下のような課題が挙げられています。
(ア)消費者の役割
家庭から排出される容器包装廃棄物の総量については、必ずしも十分な減量効果が現れていません。例えば、買物袋の持参・レジ袋等の削減は十分に進んでおらず、簡易包装化がなされている商品、詰め替え可能な商品、リターナブル容器を用いている商品の選択等が消費者に十分浸透していないものと考えられます。
一方で、消費者の意識が高まり、率先して簡易包装されている製品を選ぶこと等により、製品を作る事業者の行動を変えることができます。
このため、消費者の意識・行動を変えるような具体的な取組について検討する必要があります。
(イ)市町村の役割
市町村のリデュースに係る取組は、住民への容器包装廃棄物のリデュースに対する意識・行動の変革と密接に関係しています。
例えば、本年度から新たに創設された循環型社会形成推進交付金の申請に際しては、廃棄物のリデュース等の取組を盛り込んだ循環型社会形成に関する地域計画を策定することとなっており、容器包装廃棄物についてもリデュース等に係る施策(普及啓発・環境教育のさらなる推進等)を位置付けた計画の策定及び実施を早期に定着させることが期待されています。
(ウ)事業者の役割
事業者による容器包装廃棄物のリデュースについては、容器包装の軽量化、簡易包装の徹底等の取組が進められてきました。
今後は、食品の安全性の確保等、容器包装が本来有している機能を損なうことなく、さらなる容器包装の軽量化を図る等、一層の取組が事業者に求められています。
イ 事業者による容器包装の軽量化等の対策
事業者によるリデュースの取組の一例として、容器の軽量化が進められています(序-2-4表)。
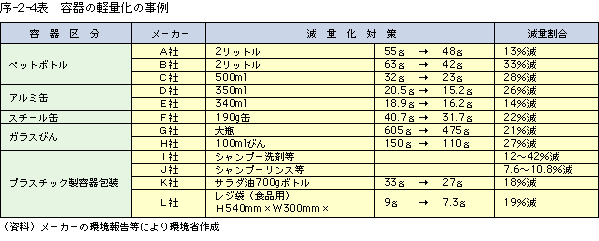
また、このような容器の軽量化の取組に合わせて、複合素材を使用した容器包装から、アルミボトル缶のアルミキャップ化など単一素材のものへの変更やミシン目入りシュリンクラベル採用による分離容易化、再生素材の使用、生分解素材の導入、詰替商品の販売と各種の取組が行われています。
|
コラム 3 ごみの排出量に係る政府の2つの目標
我々が普段何気なく使っている「ごみの排出量」という言葉。これを正確に定義すると以下のとおりとなります。 ■ごみ排出量:「計画収集量」+「直接搬入量」+「集団回収量」 ■1人1日当たりのごみ排出量:「ごみ総排出量」/「総人口」/365 (注) 計画収集量:市町村、委託業者又は許可業者が、一般廃棄物処理計画に従って、収集したごみ(し尿を除く一般廃棄物。以下同じ)の量 直接搬入量:市町村等の処理施設に事業者等が直接搬入したごみの量 集団回収量:自治会等によって行われた資源ごみの集団回収の量(市町村が用具の貸出、補助金の交付などにより関与したものに限る。) この定義に従って、政府ではごみの排出量に関する2つの目標を掲げ、その達成に鋭意取り組んでいます。 1つ目の目標は、循環型社会形成推進基本法に基づく「循環型社会形成推進基本計画(平成15年3月閣議決定)」に定められた目標です。 本計画では、1人1日当たりに家庭から排出するごみの量及び1日当たりに事業所から排出するごみの量(ごみの排出量:ただし資源回収される物を除く)を平成22年度に平成12年度比で約20%減とすることが目標とされています。 1人1日当たりに家庭から排出するごみの量は、平成12年度に平均約630gであることから、平成22年度に平均約504gにすることが目標となります。 同様に、1日当たりに事業所から排出するごみの量は、平成12年度に平均約10kgであることから、平成22年度に平均約8kgにすることが目標となります。 2つ目の目標は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(平成13年5月環境省告示)」に定められた目標です。 本方針では、「一般廃棄物については、平成9年度に対し、平成22年度において排出量を約5%削減」することとされています。具体的には、平成22年度の一般廃棄物の排出量の目標は約4,900万tとなります。 本文で述べたように、ごみの排出量に関して2つの政府目標があるのはなぜでしょうか。 廃棄物処理基本方針の目標は、いわゆる「マクロ」な目標です。これは我が国全体で見たときのごみの排出量に着目したものです。一方、循環型社会形成推進基本計画における減量化の目標は、いわゆる「ミクロ」な目標です。つまり、普段生活している住民一人ひとりの視点から策定したものです。 特に一般廃棄物の排出量の抑制については、事業者等の責任はもちろんのこと、我々国民一人ひとりが高い意識を持って積極的に取り組んでいくことが重要です。そのため、循環型社会形成推進基本計画における目標では、排出量の目標を国民一人ひとりが「自分の問題」として考えることができるように、国全体の目標を国民一人ひとりや事業者ベースで換算しています。 したがって、2つの目標は、目標の対象は異なりますが、根本の削減目標量は同じになっています。一人ひとりが自らに課せられた排出量の目標を達成することによって、我が国全体の排出量の目標達成が実現されるのです。 |
|
コラム 4 ごみ処理の有料化事例
青梅市では、ごみ収集の有料化後、一時減ったごみの量が、また増加しています。一番少ない平成11年度の774gまで、再度100gのごみの減量化を目指して、ごみを減らすこと(リデュース)、ごみになる物は断ること(リフューズ)、物を繰りかえし使うこと(リユース)、そして最後にどうしても使えなくなったらリサイクルするという“ごみ減量の4R”への協力を呼びかけるなど「ごみ減量チャレンジ100」を実施しています。 日野市でも、ごみの有料化後に半減したごみの量が、少しずつ増加しています。特に、不燃ごみの1人当たりの量は、改革後3年目は1年目と比べると13%も増加しています。このため、不燃ごみの中で8割近く(容積率)を占めるプラスチック製の容器・包装類に対する分別収集のモデル実験を一部地域を対象として実施しています。この実験の結果をもとに、プラスチック容器の分別収集を進めるべきかどうかを検討しています。 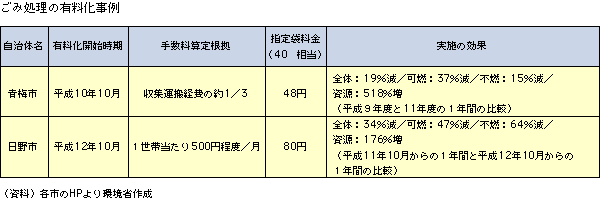
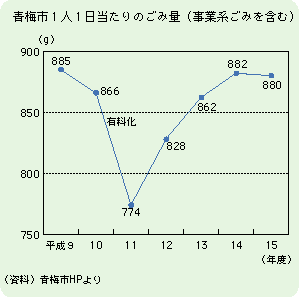
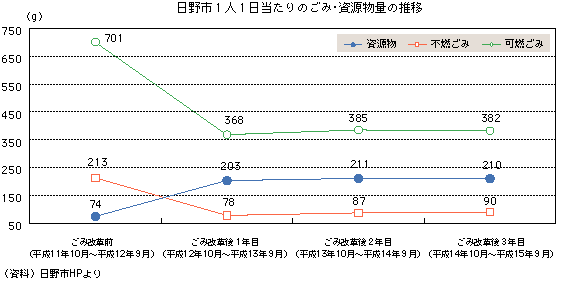
|
2. リユース(再使用)対策
リユースとは、不要になったものを捨てるのではなく、必要に応じて、修理、洗浄等を行った上で、「もう一度(何度も)使うこと」です。
フリーマーケットなどで品物を購入して使用することや、ビールびんを回収し再利用することがリユース対策に含まれます。一般的にリサイクルに比べて、追加的な消費エネルギーや環境汚染が少ないことから、リユースはリサイクルよりも優先されるべき取組です。
しかしながら、ごみのリユースは、近年、パソコン等の新たな分野での取組が見られる一方で、かつては一般的だったリターナブルびんについては、国民のライフスタイルの変化などに伴い後退が目立っており、リユースびんの推進には事業者、消費者の意識改革が求められています。
このため、環境省では、身近なところからごみのリユース対策を推進するため、主にリユースカップ、リユースびんの普及及びフリーマーケットの積極的な支援に取り組んできました。
ここでは、リユースの取組を一層促進していく観点から、ごみのリユースの現状と取組を踏まえつつ、1)デポジット制度の効果を含めたリユースカップを導入した事例の分析、2)容器包装におけるリユースの取組の検討等について紹介します。
(1) ごみのリユースの現状と取組
ア ごみのリユースの現状
我が国におけるリユース対策は、最近、住宅やコピー機、自動車部品等様々な分野で取組が進み始めています。特に、パソコンについては、ここ数年前から「再生パソコン」「リフレッシュパソコン」などの名称で、使用済パソコンが市場に出回り、その販売台数にも伸びが出ています(序-2-13図)。
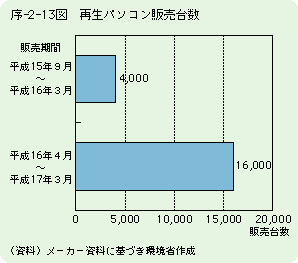
また、リユースと密接な関係にあると考えられる古物商の営業許可件数の推移を見ると、平成15年度は平成10年度と比較して約22.0%増加しています。必ずしも営業許可件数の増大がリユース対策と直接結びつくものとはいえませんが、社会全体の傾向として、古物業のニーズが増大してきているものと思われます(序-2-5表)。
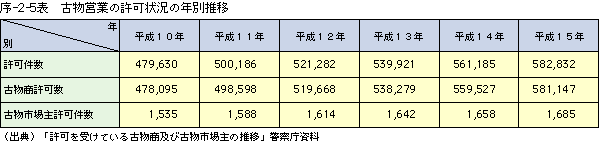
一方で、リユースの取組では最もなじみの深いビールびんや一升びんに代表されるリターナブルびんについては、再生パソコンの販売台数や古物商の営業許可が伸びているのとは対照的に、年々リターナブル率*6が低下しているとの資料もあります。
平成16年度に環境省が行った、リターナブル容器に関する国民の意識調査*7によると、
1) 「リターナブルびんを利用していますか」との問いに対しては、「ほとんど利用していない」(26.3%)、「利用していない」(14.3%)と答えた人の合計は40.5%に上っています(序-2-14図)。
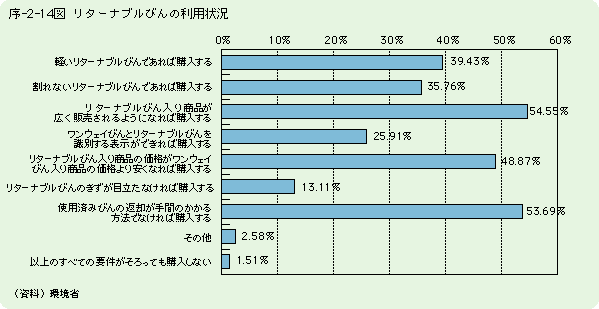
2) また、「以下のどの要件が揃えば、リターナブルびん入り商品を購入しますか」との問いについては、「リターナブルびん入り商品が広く販売されるようになれば購入する」(54.6%)、「使用済みびんの返却が手間のかかる方法でなければ購入する」(53.7%)、「リターナブルびん入り商品の価格がワンウェイびん入り商品の価格より安くなれば購入する」(48.9%)と回答されており(複数回答)、リターナブルびんの普及には様々な課題があることがうかがえます。
*6 リターナブル率
ガラスびんリサイクル促進協議会資料によると、リターナブル率(リターナブルびん使用量/(リターナブル使用量+ワンウェイびん出荷量))は、平成9年の67.6%から平成14年に56.8%へと減少している。
*7「リターナブル容器に関する国民の意識調査」
1)調査期間 平成17年1月26日~1月28日
2)調査対象 インターネットを利用したアンケート調査
3)有効回答数 3,837人
イ 政府の取組
リユース対策は、国民一人ひとりが物を大切にするといった意識と取組から始まるものであり、このような身近な取組が進んでいないことが課題となっています。このため、環境省としては、国民一人ひとりの取組を促進するため、主にリユースカップ及びリユースびんに係る普及や取組支援を行っています。
(ア)イベント会場などにおけるリユースカップの普及
リユースカップとは、使い捨ての紙コップに代わり、何度も洗ってリユースすることのできるカップです。
リユースカップシステムとは、このようなリユースカップを用い、サッカースタジアムや野球場、コンサートホールなど多数の人が集まる場所で、環境負荷を低減するために必要な回収所の設置、カップの洗浄、飲料販売者への説明等、包括的なシステムのことです。このシステムは、ヨーロッパ諸国、特にドイツでは普及が進んでおり、屋外イベントでの使い捨て容器の利用を禁止する条例もあります。
我が国でもJリーグでの取組をはじめとして、全国的な普及が進みつつありますが、デポジットの周知、回収場所の適正配置や保管時の衛生管理など課題を克服しつつ、今後急速な普及を実現するための一層の取組が不可欠です。
このため、環境省は、リユースカップシステムの実現・普及に向け、平成14年度に(財)地球・人間環境フォーラムを支援し、「リユースカップ検討委員会」を立ち上げました。
この検討委員会のメンバーを中心とした様々な関係者の協力により、主にJリーグ、音楽イベント、お祭り等の各種イベントにおいて、リユースカップの導入は急速に進んでいます。
a Jリーグにおける取組
平成15年3月からJ1の大分トリニータのホームグラウンドである大分ビッグアイにおいてシステムが本格導入されたのを皮切りに、横浜国際総合競技場(横浜F・マリノス)が平成16年8月21日から、名古屋の瑞穂公園陸上競技場(名古屋グランパスエイト)が平成16年9月23日からリユースカップの導入を実施しました。
その他にもJ2のヴァンフォーレ甲府でもリユースカップが導入されており、現在導入を検討している球団もいくつかあります。
b お祭り等における取組
平成15年度のエコ・コミュニティ事業で、お祭り・イベントへのリユースカップシステムの導入事業を採択し、祇園まつりや鴨川さくらまつり等で実証しました。平成16年度は、食器洗浄器とリユースカップを積み込んで移動するための車を導入し、より多くの屋外イベントに対応できる体制を作りました。
c 音楽イベント等における取組
このほか、NGO、企業の積極的な活動の結果、ライジングサンロックフェスティバル2003,2004、サマーソニック2004、in the city TOKYO 2003, 2004、Re-Style LIVE VOL.1, VOL.2など、比較的規模の大きい音楽イベントや東京近辺のライブハウスでも、リユースカップシステムの導入が進んでいます。
d リユース食器ネットワーク
リユース食器ネットワークとは、地域のお祭りやイベント等へのリユース食器の導入を促進するため、地域のNGO・NPOがリユース食器導入推進の拠点となり、ネットワーク化を通じて拠点同士の情報交換や交流を図ることにより、地域におけるリユース食器の貸出事業や情報発信、導入のコーディネートやノウハウの提供等の活動を支援するものです。このネットワークは(財)地球・人間環境フォーラム(http://www.gef.or.jp/reuse/)を事務局として北海道、新潟(予定)、三重、京都、大阪、大分のNPO・NGO等が参加して平成16年3月に設立されました。
環境省では、前述の「リユースカップ検討委員会」の協力を得て、これらの取組で得られたデータを用いて環境負荷低減効果、リユースカップシステム運用に係る課題等の抽出、リユースカップ回収率の向上に係るデポジットの有効性等について検証を行いました。その結果については、以下(2)のとおりです。
(イ)リユースびんに関する取組
環境省では、平成15年度のエコ・コミュニティ事業として、南九州における900ml茶びんの統一リユースシステムモデル事業を採択することにより、びんのリユース化を推進しています。
このような取組の一つとして、(社)環境生活文化機構は、九州地域で主に焼酎の販売に利用されている容量900mlの茶びんの規格を統一し、リユースする仕組みの構築を進めています。具体的には、統一びんの規格化、試作びんの作成、焼酎メーカーへの参加働きかけ、住民への協力呼びかけ、統一びんを用いた商品の試験販売など、リユースの仕組みづくりのための実証試験を行っています。
平成16年度は、焼酎メーカー1社の全面的な協力により4月下旬からリユースびんを使用した焼酎の出荷を開始し、11月からは更に2社が事業に参加しています(コラム13「エコ・コミュニティ事業」を参照)。
また、財務省では、日本酒造組合中央会が策定した「経営基盤強化計画」を認可し、当該計画の主要事業である300mlのリターナブル用規格統一びん(Rびん)の開発・導入の支援を行い、リターナブル化を推進しています。
(2)リユースカップの導入事例におけるデポジット制度の効果分析
現在、普及が進んでいるリユースカップシステムですが、カップの回収率の向上が最大の課題です。その理由は、リユースカップには主にプラスチック製のカップが用いられますが、これは単体では紙コップよりはるかに重く、石油を原料としていることから回収して一定回数以上使用しなければ、紙コップの使い捨てと比べ環境への負荷が大きくなるためです。
このため、回収率を上げるための方法として、リユースカップへのデポジット制度の導入が注目されています。
リユースカップの普及促進に伴って導入されたデポジット制度の効果と課題は以下のとおりです。
ア リユースカップの回収率と環境負荷との関係
環境省が平成14年度より実施している「リユースカップの実施利用に関する調査」で東京大学生産技術研究所の協力で行ったLCA(ライフ・サイクル・アセスメント)*8の結果によれば、リユースカップについては、
1) エネルギー使用量(環境への負荷)は6~7回の使用で紙コップを下回る。
2) CO2の排出量は4回で紙コップを下回る。
3) 固形廃棄物の排出量は5回で紙コップを下回るとの結果が出ています(序-2-15図)。
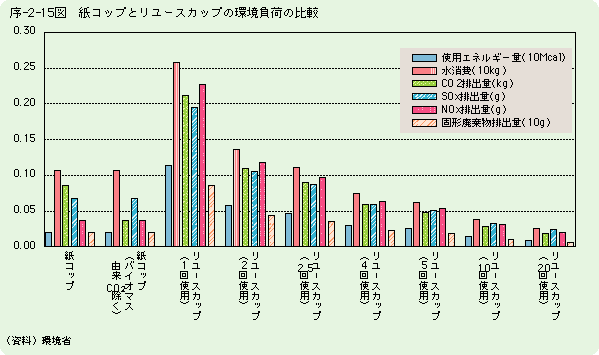
例えば、リユースカップの回収率が80.0%であれば、リユースカップの平均使用回数は5回となります。前述のLCAの結果を考えると、最低でも80.0%以上の回収率がないと(5回以上使用されないと)、リユースカップは紙コップよりも環境負荷が大きくなってしまう可能性があります。
そこで、回収率を上げるための1つの方法として、リユースカップへのデポジット制度の導入が考えられます。具体的には、リユースカップで飲み物を販売する際に、デポジット(預かり金)を上乗せし、カップを返却した人にはデポジットを返すという方法です。ドイツでは、デポジット制度の活用により99.0%もの回収率を達成している事例も多く見られます。
次に我が国でのリユースカップの活用の事例におけるデポジットの取組例について見ていくこととします。
*8 LCA(ライフ・サイクル・アセスメント)
原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品の一生涯(ライフサイクル)で、環境に与える影響を分析し、総合評価する手法。製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴がある。
イ 大分ビッグアイと日産スタジアム(横浜国際総合競技場)におけるリユースカップの導入事例
(ア)大分ビッグアイ
大分ビッグアイで導入されたリユースカップシステムは、大手給食サービス業を営むA社が自主的に導入したもので、飲料に100円のデポジットを上乗せして販売し、返却時にデポジットを返却するというもので、同一カップを使用して“お代わり”をした場合は飲料が50円引きとなっています。返却は場内6か所に設けられた回収所で行われ、平成16年度は17試合で約6万9,300個のカップを使用し、約5万9,100個のカップを回収しました。シーズンを通しての回収率は85.3%でした。
(イ)日産スタジアム
日産スタジアムでは、平成16年度の後節からリユースカップが導入されましたが、こちらはデポジットをかけずに販売し、出入り口や階段付近等に多数の回収ボックスを設け、客席に残されたカップやごみ箱に捨てられたカップを球場ボランティアが回収しています。その結果、6試合で約7万6,500個のカップが使用され、約7万3,600個のカップを回収しました。期間を通じての回収率は96.2%でした。
ウ デポジット制度の有効性と課題のまとめ
サッカー場でのリユースカップ導入については、前述のように一見するとデポジットを導入しなかった日産スタジアムの方が回収率は高いとの結果が出ています。では、果たしてデポジットはかけない方が本当に回収率は上がるのでしょうか。大分ビッグアイと日産スタジアムの比較をしてみます。
大分ビッグアイの特徴は、民間企業の取組であることから回収を含めてコストをかけられないため、回収所は6か所しか設けていませんし、横浜のような球場ボランティアの活用はできません。大分の場合は回収所で回収されるカップの割合が高く、客席に残されたりごみ箱に捨てられたりしたものはほとんどありません。
一方、日産スタジアムの特徴は、無人の回収ボックスが場内の至る所に設置されており、カップを返却しやすくしています。また、客席に残されたカップやごみ箱に捨てられたカップも球場ボランティアや清掃業者の手によって回収されています。
この二つの事例を比較すると、回収にかけられる人員の差が回収率の差になっています。純粋に回収所(回収ボックス)で回収されたカップだけで比較すると、デポジットをかけた大分がほとんどのカップを回収所で回収しているのに対し、日産スタジアムは回収所で回収されたカップは総回収量の76.0%ほどとなっており、デポジット制度の効果があったものと考えられます。
なお、大分の場合、回収されなかった約15.0%は、アンケートの結果、何らかの価値を見いだされて家庭に持ち帰られており、直ちに捨てられているとは限らないことから、必ずしも環境負荷を増大させる要因にはなっていません。
今回の調査結果を踏まえれば、デポジット制度は、コストや人員等の制約を考慮すれば、サッカースタジアムなどの閉鎖的な空間におけるリユースカップの回収に際し、ある程度の効果を発揮するものと考えられます。
(3) 容器包装におけるリユースの取組
リユース推進のためには、リターナブルびんを始めとした容器包装の面での取組が重要となっています。
このため、中央環境審議会等において、リターナブル容器の利用促進について、以下のような議論がなされています。
ア 現状
我が国のリターナブル容器は、欧州の一部の国で見られるペットボトルの利用はなく、ガラスびんが中心となっており、国民のライフスタイルの変化などにより、その利用量が、年々減少しています。
イ 課題
リターナブル容器については、ワンウェイ容器に比べ、ごみのリデュースには効果があると考えられていることや、容器包装リサイクル法の基本方針においても、リターナブル容器を利用した商品選択やリターナブル容器の利用促進を掲げていることなどから、その利用促進策について検討する必要があります。
ウ 対応の方向
リターナブル容器の利用を促進するための取組として、例えば、自主回収認定制度の要件の緩和、地方公共団体の回収協力、消費者意識の醸成、韓国で見られるような飲食店等における一回用品(使い捨て用品)の使用規制に係る自主協定を我が国でも導入すること等が検討されています。
|
コラム 5 韓国の一回きり製品規制の制度について
1994年、韓国では、過剰包装に対する規制、生ごみリサイクルの義務化、家庭ごみの有料化などとともに、一回用品の使用を規制する「資源の節約と再活用の促進に関する法律」が施行されました。「一回用品」とは、日本で使い捨て用品と呼ばれているもののことで、具体的には、ファストフード店やレストラン等のコップ、皿、割りばし、スプーンや、ホテル等のひげ剃り、歯ブラシ、シャンプーなどが規制の対象となっています。 韓国では、1980年代に入って、急速な経済成長とともに、ごみの適正な処理が深刻な社会問題になってきました。それまで、韓国のごみは8割近くが埋め立て処分されていましたが、既存埋立地のひっ迫、有害物質の流出といった環境汚染が深刻となったため、1990年代に入って、韓国政府は焼却方式の導入を進めようとしました。しかし、住民らの激しい反対運動もあり、焼却施設の建設も困難な状況となったため、韓国政府は政策的なごみの減量化に本格的に取り組むこととなったのです。 当初は一回用品の規制対象が、規模や業種を基準に一部の事業者に限定されていたこと、また、規制内容が一回製品使用の自粛程度の弱い措置にとどまったこと等から期待されていたほどの環境保全の効果を上げることができませんでした。そのため、韓国環境省は何度も法改正を行い、対象事業者を次第に拡大し、規制内容を強化してきました。 また、こういった行政の取組と併せて、企業やNGOもごみの減量化に積極的に取り組んでいます。1997年、ごみ問題に取り組んでいる270もの市民団体が、共に活動を行うために「ごみ問題解決のための全国市民協議会(Korean Zero Waste Movement Network,(KZWMN))」を設立しました。デパート、スーパーマーケットなどの流通業界は、KZWMNの働きかけで2002年5月、23社と韓国環境省の間で「一回用品使用削減のための自発的実践宣言」を結び、これまで法律で20ウォン(約2円)だった一回用プラスチック袋の価格を50ウォン(約5円)とすること、マイバッグ持参を促進するために、現金割引、クーポン提供等の優遇措置を提供すること等の取組を行っています。さらに、2002年10月には、KZWMNのコーディネートにより、ファストフード7社、コーヒーショップチェーン24社と環境省の間で「一回用品使用削減のための自発的協約」が結ばれ、2003年1月より全ての店舗でテイクアウトの一回用コップ等にデポジット(ファストフードは100ウォン(約10円)、コーヒーショップは50ウォン(約5円))を課すこと、店内飲食は一回用品から多回用品(リユースできる用品)に切り替える(ファストフードは100坪以上、コーヒーショップは50坪以上の店舗で必須)こととされています。KZWMNはこれらの取組の履行状況について、ほぼ3か月ごとに大規模な調査を行い監視しています。 このような韓国での「一回用品」の取組については、一般市民の環境意識よりも企業や、制度が先行してしているといった問題点も指摘されていますが、ごみの処分について、安易な埋め立てから脱却し、行政・企業・NGOが協働でごみの減量を進めていく韓国の取組は、循環型社会の構築を目指す日本にもおおいに参考となるでしょう。 |
3. リサイクル(再生利用)対策
リサイクルとは、不要になったものを捨てるのではなく分別収集して「再生利用」することです。リユースとの違いは、不要品をそのまま再使用するのではなく、一度原料の形に戻した上で、製品として再生産するという点です。新しいものを作る時と同じようにエネルギーが必要であり、追加的な環境負荷を生じることも多いことから、リユースに比べて優先順位は低いものとされています。
また、リサイクルの中に、「サーマルリサイクル(熱回収)」を含める考え方もあります。上記のリサイクルが不要品を材料(マテリアル)として、製品を再生産することから、「マテリアルリサイクル」と言われるのに対し、「サーマルリサイクル」とは、廃棄物を「燃料」として利用することを指します。不要品を破砕して埋め立てたり、単に燃やしたりしてしまうよりはせめて熱として回収しようとする考え方ですが、熱として回収した後は焼却灰が最終処分されるだけであり、それ以上循環しないことから、循環型社会の構築や全般的な環境保全の手段としてはマテリアルリサイクルを優先すべきとされています。
政府では、主な再生利用(リサイクル)対策として、廃棄物処理法、資源の有効な利用の促進に関する法律及び自動車、容器包装、家電、食品、建設の個別リサイクル法に基づく取組、エコタウン事業を通じた地方公共団体のリサイクル関連事業の支援等を実施しています。
このような取組の結果、我が国のごみリサイクル率は上昇していますが、その一方で、多くの課題が山積しているのも事実です。具体的には、1)循環利用率の伸び悩み2)広域的な処理の推進3)廃プラスチックの3R推進4)標準的な分別種類等について、中央環境審議会等の場で議論が重ねられてきました。
ここでは、上記の検討結果も含め、ごみに係るリサイクル対策の現状、問題点及び今後の取組の方向性について見ていきたいと思います。
(1) ごみのリサイクルの現状と取組
ア ごみのリサイクル量・率の推移
平成14年度に市町村等において分別収集されて資源化された、あるいは更に中間処理により資源化されたごみの量は583万t、住民団体等によって資源回収された集団回収量は281万tとなっています。
市町村等による資源化と住民団体等による資源回収とを合わせた総資源化量は864万t、リサイクル率は15.9%であり、資源化量、リサイクル率ともに着実に上昇しています(序-2-16図)。
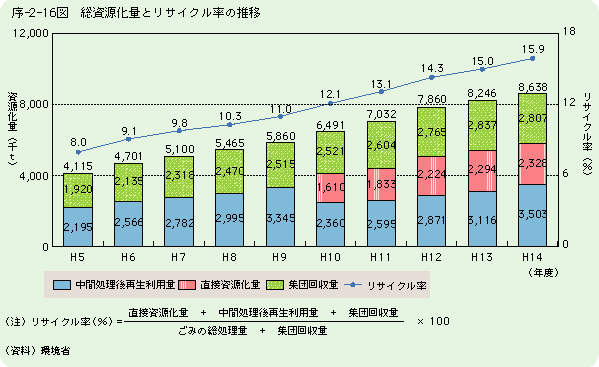
イ 政府の取組
ごみのリサイクルの目標には、循環型社会基本計画及び廃棄物処理基本方針に基づくものがあります(序-2-6表)。
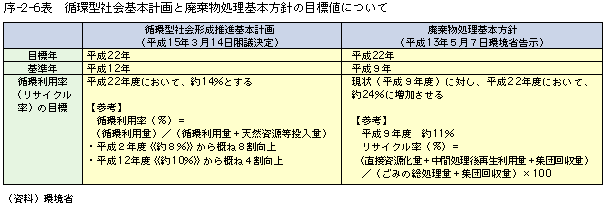
(ア)循環型社会基本計画
循環型社会基本計画では、平成2年度で約8.0%、平成12年度で約10.0%だった循環利用率(=循環利用量/(循環利用量+天然資源等投入量))を、平成22年度において約14.0%とする目標を掲げています。
平成14年度における循環利用率は10.2%となっており、基準年度(平成12年度)と比べて0.2ポイント向上しています(序-2-7表)。
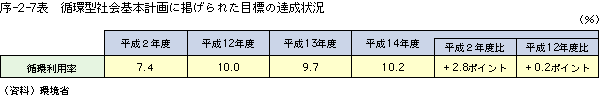
(イ)廃棄物処理基本方針
廃棄物処理基本方針では、平成9年度で約11.0%だったごみのリサイクル率を平成22年度において約24.0%に増加させる目標を掲げています。
平成14年度におけるごみのリサイクル率は15.9%であり、基準年度(平成9年度)と比較して4.9ポイント向上しています(序-2-8表)。
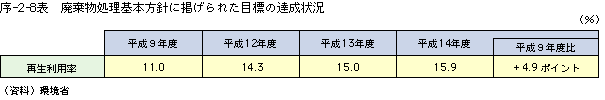
ごみのリサイクルの目標の達成状況を見ると、ごみのリサイクル率は比較的順調に伸びているものの、我が国全体での循環利用率はあまり伸びていません。これは、鉄くずや古紙等の海外への輸出量が伸びていることから、従来は国内でリサイクルされていたごみが資源として輸出され、国外でリサイクルされていることが要因の一つとなっているものと考えられています。このため、ごみの輸出量のより正確な把握が今後の検討課題となっています。
このような目標の達成に向け、容器包装リサイクル法を始めとする各種のリサイクル法に基づく取組が進められているところです。平成17年1月からは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)が新たに施行されています。自動車リサイクル法は、トラックやバスを含めほとんど全ての四輪自動車を対象としており、
1) 自動車メーカー・輸入業者には、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類の3品目の引取りとリサイクル、適正処理を義務付けるとともに、リサイクル率の目標を設定していること、
2) 1台ごとに電子情報により使用済自動車の流れを管理する移動報告制度(電子マニフェスト)を採用していること、
3) 不法投棄の防止に資する観点から、原則として新車販売時(既販車は車検時、車検前に廃止する場合は引取り時)にリサイクルに必要な費用の預託を求めていること
等を特徴としています。
(2) 一層のリサイクルの推進に向けた課題
今後、ごみのリサイクルを一層進めていくための課題としては、1)広域的なリサイクルの推進、2)廃プラスチックの取扱い、3)標準的な分別収集方法の確立といった点が指摘されています。
ア 広域的なリサイクルの推進
ごみのリサイクルについては、現在、市町村単位での処理が原則となっていますが、リサイクルを事業として実施する場合、ある程度まとまった量を取り扱わなくては採算が合わないことがあります。また、熱回収をする場合でも、効率の高い熱回収を行うためには、一定規模以上の全連続式施設等が必要となります。こうした観点から、ある程度まとまった量の循環資源を集めるためには、市町村単位ではなく、もっと広域的な処理を進める必要があります。
イ 廃プラスチックの取扱い
廃プラスチックについては、地方公共団体によってその処理の方法が異なり、資源物として回収して再生利用したり、可燃物として焼却され熱回収を行ったりしている一方で、不燃物として直接埋め立てている場合も多くなっています。
こうした廃プラスチックについては、今後、循環型社会基本法の基本理念に則り、まずリデュース・リユースを、次に容器包装リサイクル法等に基づくリサイクルを推進し、それでも残った廃プラスチックについては、直接埋立てによる最終処分は行わず、一定の熱回収率を確保しつつ熱回収していくことが望ましいと考えられ、このような方向でシステムを見直していくことが必要と考えられます(序-2-9表)。
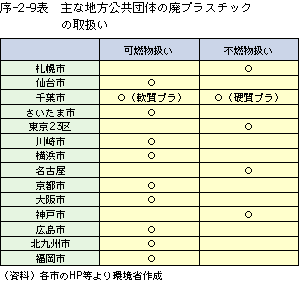
ウ 標準的な分別収集方法の確立
ごみの分別については、5~8種類程度としている地方公共団体が最も多くなっています(序-2-17図)。
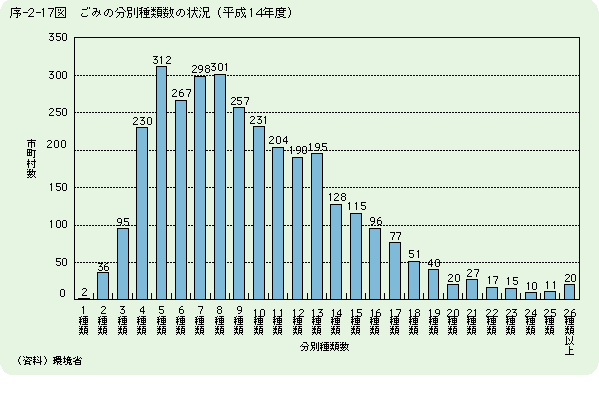
代表的な分別の例としては、可燃物、不燃物、粗大ごみ、有害ごみ、資源物(びん、かん、ペットボトル、新聞・雑誌等)ですが、徳島県上勝町(34分別)や熊本県水俣市(21分別)のように地方公共団体によっては更に細かく分別し、資源化を図っているところもあります。
分別収集には、素材ごと分別を徹底して収集することによってリサイクルがし易くなるというメリットがあります。また、住民のごみに関する意識も高めることができ、ごみのリデュースにも効果があります。一方、分別の徹底を図れば、住民の煩雑さを招くばかりでなく、収集・運搬のコストがかさむことにもなります。さらに、市町村単位の収集では効率的なリサイクルを行うための必要量が確保できないために結果的にうまくリサイクルが進まないことがあります。
よって、分別収集方法の変更など、ごみ処理システムの変更や新規導入を図る際には、その必要性とメリットを住民や事業者に対して明確に説明して、標準的な分別収集方法を確立することが必要です。
|
コラム 6 ボトル to ボトル
食品用として使用したペットボトルをリサイクルして再び食品用ペットボトルとして使用する完全循環型リサイクルシステムのことをボトルtoボトル(B to B)と呼びます。使用済みのペットボトルは従来、不純物が混じるため、食品用のペットボトルには使用できず、衣料など別の製品にしかリサイクルできませんでした。 ペットボトルを化学的に分解し、石油から作った化合物と同純度の原料に精製し直すことにより、障害となっていた毒性のある「異物」を完全に取り除くことができ、内閣府の食品安全委員会において、安全性が確認されました。 ボトル to ボトルの流れが確立すると、ペット樹脂の原料となる石油の使用が大幅に削減できます。 しかし、容器包装リサイクル法に基づき市区町村が分別回収を計画しているペットボトル21万2,000tに対し、全国に約70あるリサイクル業者の処理能力は29万2,000tと約8万tが不足しています。 市区町村によるペットボトルの回収率は年々増加し50%ほどとなっていますが、今後より一層の回収率向上の取組が必要となっています。 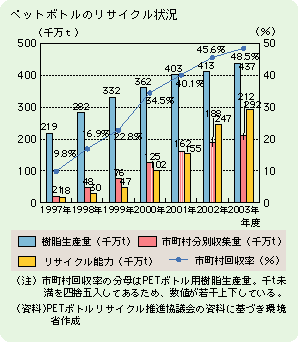
|
4. 適正な最終処分の実施
3Rを推進した上で残ったごみは、最終的に処分することになります。循環型社会基本法では、ごみの処理方法の中で最後に位置づけられる「最終処分」ですが、不適正な最終処分は、水質、土壌に多大な影響を及ぼし、悪臭の問題も生じるなど、周囲の生活環境に悪影響を及ぼす危険が大きいことからどうしても最終処分せざるを得ないものを適正に処分することは、国民生活の観点からも非常に重要です。
適正な最終処分を行うために、まず大前提となるのは、周囲の生活環境をしっかり守ることのできる最終処分場の確保です。最終処分場が十分整備されなければ、行き場をなくした廃棄物が不法投棄される可能性が高くなります。
また、最終処分場に搬入される廃棄物を極力減らすことも重要です。既に述べたとおり、リデュースやリユース対策の推進が非常に重要ですが、その上で中間処理施設における処理によって、廃棄物を減量・減容化、資源化することによって、最終処分量を大きく減らすことが不可欠です。
しかし、中間処理施設及び最終処分場等のごみ処理施設はいわゆる「迷惑施設」であり、施設周辺の環境に与える影響を不安に思う住民の反対等により、近年、施設の整備が非常に困難になっています。
ここでは、ごみ処理施設に係る国の関与の在り方を中心に、現状、問題点及び今後の方向性について見ていきたいと思います。
(1) ごみの最終処分の現状
ア 最終処分の状況
平成14年度における最終処分量(直接最終処分量と中間処理後に最終処分されるものとの合計)は903万t、1人1日当たりの最終処分量は194gであり、減少傾向が継続しています(序-2-18図)。
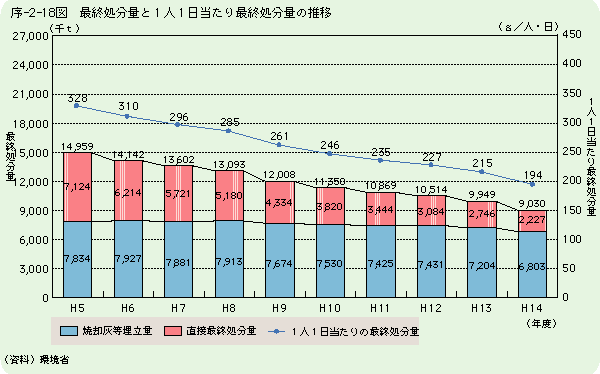
イ 最終処分に係る政府の目標と達成状況
循環型社会基本計画では、廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)最終処分量を平成22年度において約28百万tとすることを目標としています。
これは平成2年度(約110百万t)からおおむね75.0%減、平成12年度(約57百万t)からおおむね半減の数値です。
平成14年度の廃棄物の最終処分量は50百万tとなっており、平成12年度と比べ約12.3%減少しました。
廃棄物処理基本方針では、ごみの最終処分量を平成22年度に平成9年度(約12百万t)比でおおむね半分(6.4百万t)に削減することを目標としていますが、平成14年度の最終処分量は前述のとおり約9.0百万tなので、平成9年度と比べて約25%減少しています(序-2-10表、序-2-11表、序-2-12表)。
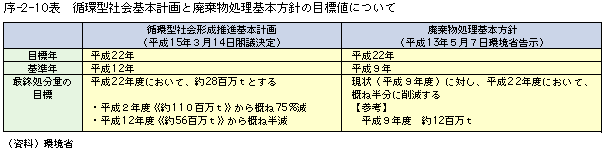
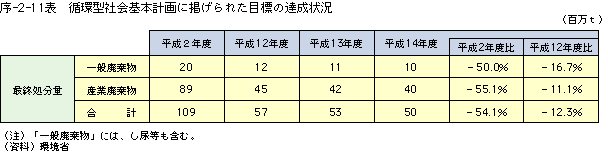
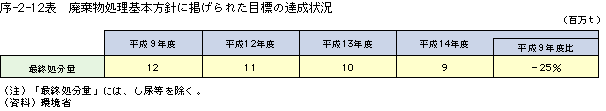
(2) ごみ処理施設の整備状況と今後の取組
ア 処理施設の整備状況
(ア)最終処分場の残余年数と残余容量
平成14年度末現在、ごみ最終処分場は2,047施設(13年度 2,059施設)、残余容量は1億4,477万m3(13年度 1億5,261万m3)であり、残余年数は、全国平均で13.1年分(13年度12.5年分)でした。最終処分量が前年度よりも減少しているため、残余容量は減少しているものの残余年数はわずかに増加しています(序-2-19図)。
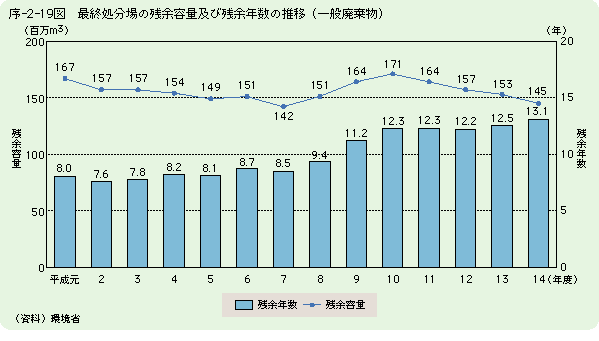
(イ)最終処分場のない市町村
平成14年度末現在、全国3,214市町村(東京都23区は1市とする。)のうち、当該市町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立てを委託している市町村数(大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村及び公社等の公共処分場のみに埋立てしている場合を除く。)は521市町村であり、その分布は序-2-20図のとおりです。
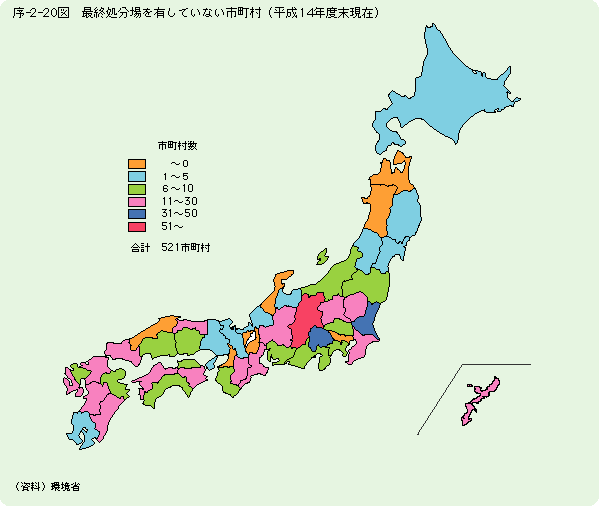
イ 今後の取組
最終処分場等のごみ処理施設は、いわゆる迷惑施設であることから、新たな立地は困難な状況にありますが、中でも最終処分場の確保は市町村単位では難しいケースが見られます。こうした状況から、広域的に最終処分場を確保する取組が既に始まっていますが、今後は、単に用地の確保が難しいから他の地域に確保するといった発想ではなく、管理すべき施設の数を減らし、確実かつ高度な環境保全対策を実施した上で、廃棄物のリデュース、適正な循環的利用を徹底した後の最後の受け皿として広域的に整備を進めていく必要があります。
こうした循環型社会の形成のために必要なごみ処理施設の整備は市町村において廃棄物の3Rに関する明確な目標を設定した上で、その実施に向けた総合的な施策を内容とする計画を策定して進めていくべきであり、この計画の策定に当たり、国は助言を行い、地方公共団体と一体となって推進していく必要があります。
|
コラム 7 ごみの掘り起こし
最終処分場に埋められたごみを掘り起こし、焼却や再資源化して減量し、埋め戻す事業が広がっています。 これは、最終処分場の廃棄物の受け入れ可能年数は一般ごみで約13年、産業廃棄物で約4年と限界に近づいている一方、新処分場の建設が難しいためです。 兵庫県高砂市の一般ごみ最終処分場では平成15年4月から、1日最大100tを掘り起こして選別し、可燃ごみ約20tを高温で溶融して15分の1程度のスラグにして埋め戻しています。選別の際に粉塵などが飛び散らないように可動式のテントの中で続けられています。 新潟県巻町など4町村でつくる衛生組合では、平成14年度から年間2,600~2,700tを掘り起こし、処理後に埋め戻しています。同町内の処分場では既に8割が埋まっていますが、今後10年~15年かけて掘り続けて40年以上の延命を図る計画です。 沖縄県与那城町の産業廃棄物処分場では、ごみの種類や有害ガスについて調査の後に掘り起こし、廃プラスチックや木くず、ガラスなどを選別し、洗浄、破砕後に建材や原料などとして利用します。環境省は沖縄県と協同で事業費の大半を補助して、他の地域での活用を図る予定です。 |
|
コラム 8 名古屋市におけるごみの総合的な対策とその成果~「環境首都なごや」を目指して~
1 ごみ量の増加と「非常事態宣言」 名古屋市のごみ量は、全市を挙げてごみの減量に取り組む以前、20世紀の「大量生産」「大量消費」「大量廃棄」型の社会を象徴するかのように一貫して右肩上がりで増え続け、平成9年度には年間100万トンの大台を突破し、焼却能力や埋立て容量の限界を迎えつつある状況となっていました。 市では、名古屋港の一部(藤前干潟)を埋め立てるという計画(名古屋港西1区埋立事業)を約20年前から進めていましたが、環境問題に対する意識の高まりを受け、平成11年1月、「快適で清潔な市民生活を確保すること」と、「自然環境を保全すること」との両立をいかに図るべきか、熟慮に熟慮を重ねた末、埋立て事業を中止しました。 翌2月には「ごみ非常事態宣言」を発表し、市のごみ処理の現状を率直に伝えるとともに、市民・事業者・行政の協働のもとでの大幅なごみ減量を訴えました。 2 「ごみ非常事態宣言」後の成果 「ごみ非常事態宣言」以降名古屋市では、プラスチック製容器包装・紙製容器包装などの資源収集を始めとする様々な取組を、市民・事業者の協力、とりわけ保健委員を始めとする地域役員の献身的な尽力により進めてきました。 その結果、平成10年度102万tに達していたごみ量は約4分の3にまで減少し、資源回収量は2倍以上に増加、埋立て量は半分以下に減少という成果を得ることができました。平成16年度のごみ量は73万tで、20年前の水準を下回るまでになっています(図)。 「説明不足など役所に対して不満は多いが、今はともかくごみを減らさなければ。」、「最初は、埋立処分場がもうなくなるというから仕方なしに協力していたが、次第にこれからの時代はこれくらいのことは当然だと思うようになった。」という声に代表されるように、市民・事業者・行政による危機意識の共有が、これらの成果をもたらしたといえます。 1) 地域からの盛り上がり 容器包装の新しい分別についての地域説明会に全世帯の4分の1が参加するなど、市民は新ルールに強い取組意欲を示しました。 こうした中で、保健委員を始めとする地域役員の奮闘はめざましいものでした。集積所での実地指導はもとより、手製の看板やカレンダーを作成したり、間違いやすい点を回覧板で周知するなど市の広報の行き届かない部分を補い、また、分別お助けマンを買って出るグループが現れるなど、様々な取組が地域から起こりました。 2) 分別意識(出口対策)が買い物意識(入口対策)へ波及 アンケート調査によれば、分別収集の実施を通して「不必要な容器包装の多さ」に気づかされ、「エコマーク等を意識するようになった」、「包装のシンプルな商品を選ぶようになった」など、自らの買い物行動が変化したと答えています。「分別」は、単にごみを資源へシフトさせるという「直接効果」だけでなく、買い物に際して「発生抑制」を意識するという「波及効果」を生みました。このことが、総排出量の減少をもたらしたと言えます。 同時に、「市民ばかりでなく、事業者が製造・販売段階から努力すべきだ」と感じる市民も多く、事業者による取組の強化が求められています。 3) 市民自主回収量の増加 名古屋市では古紙類の回収は、従来から行政が収集するのではなく、町内会・子ども会等による地域での自主的な活動として行われてきましたが、この自主回収量も平成10年度の5万tから現在13万5,000tへと約2.7倍に増加し、市の資源収集量の増加よりもごみ減量への貢献度は高くなっています。 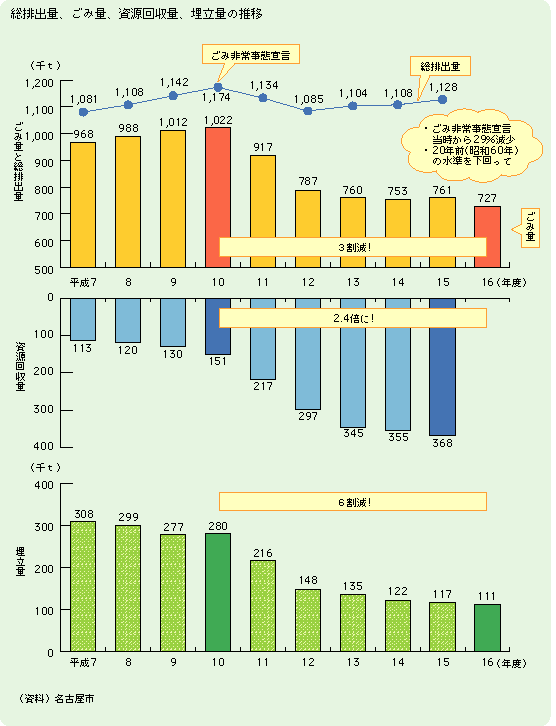
3 今後の課題 このところ、総排出量は増加傾向です。これまでの市民・事業者との協働による成果を、21世紀の「循環型社会」の実現へと着実に結び付けていくためには、従来の「分別・リサイクル(出口対策)」はもとより、一歩進めて「発生抑制(入口対策)」に取り組むなど、3Rの優先順位を踏まえた取組を進めていくことが重要です。平成14年5月に策定した「第3次一般廃棄物処理基本計画」では、 平成12年度 22年度 ・総排出量(ごみと資源の合計量)を増やさない 108万t → 108万t ・ごみ量を約2割削減(昭和51年度並みに) 79万t → 62万t ・埋立量を約1/10に削減(埋立ゼロへの布石) 16万t → 2万t を目標とし、市民・事業者・行政が適切な役割分担に基づき、主体的かつ協働した行動を進めていくこととしています(環境パートナーシップ)。 1) 発生抑制の取組 発生抑制の取組の第一弾として、平成14年5月に「容器・包装3R推進協議会」と名古屋市で「脱レジ袋宣言」を行い、レジ袋の削減運動を実施しています。 その一環として、削減運動に対する動機付けと実践行動を一層促進するため、平成15年10月から市内共通還元制度「エコクーぴょん」を導入しています。これは、レジ袋や紙袋を断った消費者に参加店ならどこでも同じシールを配付し、それが40枚集まると100円のお買い物券として、どこの参加店でも使用できるものです。 この削減運動を足がかりに、販売店の容器包装、メーカーの容器包装へと、順次取組を広げていきます。 2) リユースの取組 イベントや興行場などでの使い捨ての紙コップなどの使用を抑制し、ごみと二酸化炭素の排出抑制のため、食器洗浄機、乾燥機、カップなどを搭載したトラック「アラウくん」をイベントの主催者に有料で貸し出す「リユースカップ事業」を実施しています(カップだけの貸出しも可)。 3) リサイクルの取組 容器包装の分別収集を進めた結果、現在家庭ごみの約4割を占める生ごみの分別収集・資源化事業に取り組んでいます。現在約7,200世帯を対象に、家庭で分別された生ごみを市が収集し、民間の堆肥化施設で資源化しています。 今後は、ガス化などの他の手法を含め、「都市部に適した生ごみ資源化システム」づくりに向けての検討を進めていきます。 |