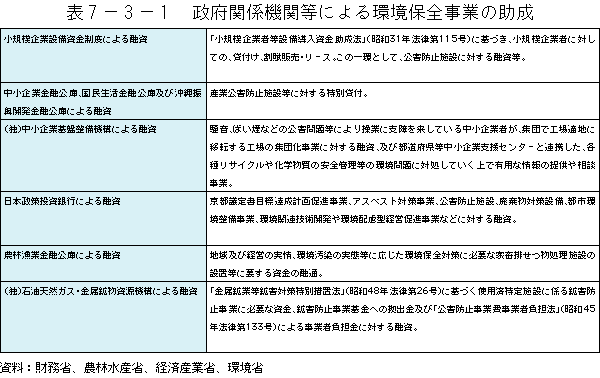
1 経済的措置
(1)経済的助成
ア 政府関係機関等の助成
政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表7-3-1のとおりでした。
イ 税制上の措置等
平成17年度税制改正において、低公害車や、最新排出ガス規制(平成17年規制)適合車(ディーゼルバス・トラック等)の取得に係る自動車取得税の軽減措置の延長、揮発性有機化合物排出抑制設備に係る特別償却制度及び固定資産税・事業所税の課税標準の特例措置を新設、緑化施設に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長などを講じました。
(2)経済的負担
ア 基本的考え方
環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、その具体的措置について判断するため、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、廃棄物の抑制などその適用分野に応じ、これを講じた場合の環境保全上の効果、国民経済に与える影響及び諸外国の活用事例等につき、調査・研究を進めました。
イ 具体的な取組事例
平成17年度においては、経済的措置の検討が深められた事例として以下のようなものがあります。
(ア)政府における環境関連税の検討状況
地球温暖化防止のための環境税については、京都議定書目標達成計画(平成17年4月28日閣議決定)では、「国民に広く負担を求めることになるため、関係審議会をはじめとする各方面における地球温暖化対策に係るさまざまな政策的手法の検討に留意しつつ、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題である。」とされています。
環境省は、平成16年に引き続き17年8月末に環境税の創設要望を提出し、同年10月25日に、環境税の具体案を公表しました。
これを受けて、税制改正論議において活発な議論が行われ、政府税制調査会では、平成17年11月の「平成18年度の税制改正に関する答申」において、「いわゆる環境税については、国・地方の温暖化対策全体の中での環境税の具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組みの現状、さらには既存のエネルギー関係諸税との関係といった多岐にわたる検討課題がある。現在、関係省庁等において、これらの課題について議論が行われているところであり、その状況を踏まえつつ、総合的に検討していく必要がある。」と答申しました。
中央環境審議会においては、平成15年に設置された施策総合企画小委員会において、環境税に関して国民の意見を聴くため地方ヒアリングを開催するなど、引き続き、環境税に関する総合的な検討を進めています。また、17年4月に設置された環境税の経済分析等に関する専門委員会においては、環境税の効果等について技術的・専門的な見地から検討を深め、「これまでの審議の整理」を同年9月13日に公表しました。
(イ)地方公共団体における環境関連税導入の動き
地方公共団体において、環境関連税の導入の検討が進められています。 例えば、産業廃棄物の排出量又は処分量を課税標準とする税について、平成18年3月末現在、26の地方公共団体で条例が制定され、22の団体で施行されました。税収は、主に産業廃棄物の発生抑制、再生、減量、その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てられています。
また、高知県や岡山県など8の県では、森林整備等を目的とする税が導入されています。例えば、高知県では、県民税均等割の額に500円を加算し、その税収を森林整備等に充てるために森林環境保全基金を条例により創設するなど、実質的に目的税の性格を持たせたものとなっています。