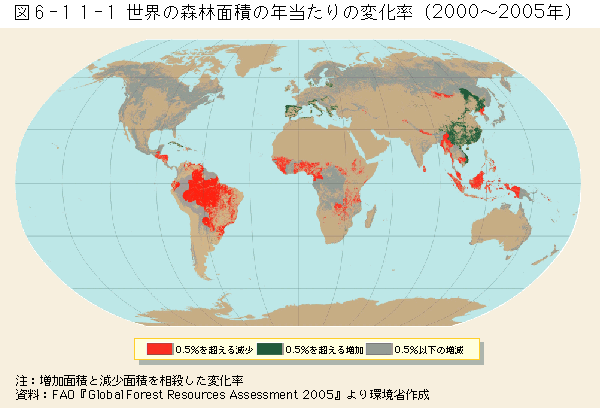
2 森林の保全と持続可能な経営の推進
(1)問題の概要
世界の森林は、陸地の約30%を占め、面積約40億haに及びますが、2000年(平成12年)から2005年(平成17年)にかけて、年平均732万haの割合で減少しました。特に、熱帯林が分布するアフリカ地域、南アメリカ地域及びアジア地域のうち東南アジアで森林の減少が続いています(図6-11-1)。
森林消失の原因として、農地への転用、非伝統的な焼畑移動耕作の増加、過度の薪炭材採取、不適切な商業伐採、過放牧、プランテーション造成、森林火災等が挙げられます。特に近年では、違法伐採が問題となっています。
(2)対策
平成18年2月に開催された国連森林フォーラム第6回会合(UNFF6)では、世界の持続可能な森林経営を推進するための今後の国際的枠組の強化について議論が行われ、2015年までは法的拘束力を伴わない枠組とすることや、森林の減少傾向の反転等2015年までの世界的な4つの目標などを内容とする文書が合意されました。
平成17年11月に横浜で開催された「アジア森林パートナーシップ」(AFP)第5回実施促進会合では、「AFPの強化のための組織事項と意思決定の仕組に関する発表」が採択され事務局や参加パートナーの役割が明確にされたほか、違法伐採対策や森林法の施行と統治に関連する取組事例が報告され、関連する国際的なプロセス等とのさらなる協調の必要性が確認されました。
国際熱帯木材機関(ITTO)においては、持続可能な森林経営の阻害要因の一つである違法伐採問題克服のため、合法な木材の適正な流通を図るための総合情報システムを開発するとともに、森林認証を推進する事業を含む持続可能な熱帯林経営を目的とした活動を行っています。
また、森林の保全と持続可能な経営を評価するための基準・指標について国際的な取組が進められていますが、日本は、欧州以外の温帯林・北方林を対象とした「モントリオール・プロセス」に参加しています。
違法伐採問題については、日本とインドネシアとの間で策定・公表した違法伐採対策のための協力に関する「共同発表」「アクションプラン」に基づいた取組を進めています。また、木材を輸入している諸外国における取組状況等の調査を行っています。平成17年7月には、G8グレンイーグルズサミットで合意された行動計画に、違法伐採対策を推進することが盛り込まれました。また、同サミットにおいて、日本は、政府調達等を通じて違法伐採対策に取り組むことを盛り込んだ「日本政府の気候変動イニシアティブ」を発表しました。
さらに、平成17年11月には、欧州・北アジア森林法の施行及びガバナンス(ENA-FLEG)に関する閣僚会合が開催され、同会合の閣僚宣言の中では、合法的に伐採された木材の貿易を促進するため、国際的な協力の強化に取り組むこと等が宣言されました。
上記の取組のほか、ITTO、国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関への拠出、国際協力機構(JICA)等を通じた協力、民間団体の植林活動等への支援、熱帯林における生態系管理に関する研究等を行いました。