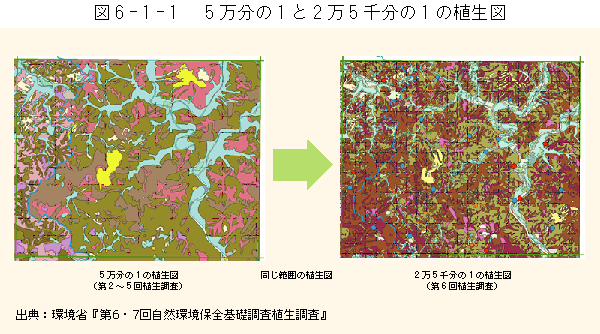
3 自然環境保全調査の推進
(1)自然環境保全基礎調査
平成17年度より第7回基礎調査を開始し、種の多様性調査、植生調査、生態系多様性調査(浅海域生態系調査)等に取り組んでいます。
植生調査では、従来は植生原図の作成に縮尺5万分の1の地形図を用いていましたが、第6回基礎調査からは新たに縮尺2万5千分の1の地形図を用いた作成をはじめ、17年度末時点で全国の約3割の作成が終了しています。「生態系多様性調査(浅海域生態系調査)」では、全国の干潟及び藻場の調査を実施しており、これらの調査結果を順次ホームページで公開しています(干潟調査http://www.higata-r.jp/、藻場調査http://www.moba-r.jp/)(図6-1-1)。
(2)モニタリングサイト1000
全国の自然環境の変化を把握するため、基礎調査に加え、全国の生態系を長期的にモニタリングする「モニタリングサイト1000」を平成15年度から開始しました。調査地は、森林、里地、湖沼、湿地、河川、海岸などのさまざまな生態系を網羅するように1,000か所程度を目安に配置していきます。16年度から、生態系のタイプごとに調査項目を設定して試行調査を始めており、17年度も引き続き実施しました。
(3)自然環境調査における各省庁連携
各事業法において環境への配慮等が規定されるにつれ、各省庁が実施する生物調査についても充実しつつあります。表6-1-3に示すように、各省庁の調査を加えると調査箇所数が数千を超えるものもあります。しかし、調査データについての連携はとられておらず、調査データの相互利用が必要です。このため、平成15年度に設置された環境省自然環境局、農林水産省農村振興局、林野庁森林整備部、国土交通省河川局、同港湾局からなるワーキンググループを引き続き開催しました。各省庁の生物調査データはGIS情報として使用可能なことを基本としており、16年度より岡山県南部地域を対象に試行的に関係省庁のデータの整理と重ね合わせを進めた結果、GISデータとして相互に利用可能であることが検証されました。