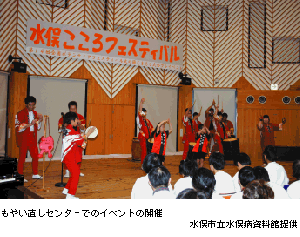
1 地域再生・情報発信
わが国の環境問題の原点とも言うべき水俣病は、被害者個人の健康被害や環境汚染をもたらしたばかりでなく、被害者への差別や住民間の軋轢による地域社会の疲弊などの様々な影響を地域社会にもたらしました。このため、熊本県及び水俣市による平成2年からの「環境創造みなまた推進事業」をはじめ、地域社会のきずなを取り戻し、地域を再生するというもやい直しのための取組が地元自治体によって進められ、その一つの成果として、平成4年から毎年5月1日に水俣病犠牲者慰霊式が行われるようになりました。また、国は平成7年の政治解決の際の閣議了解や総理大臣談話及び平成17年に発表した「今後の水俣病対策について」において、紛争の解決のみならず、地域の再生・振興、水俣病の経験の発信と国際協力などを行うことを示しました。現在、国、関係県市町及び関係団体では、以下のような取組を進めています。
1) 地域住民のきずなの修復等を図るために、国、熊本県、水俣市及び芦北町が出資し、水俣市に2カ所、芦北町に1カ所「もやい直しセンター」を建設し、地域住民等により交流や福祉サービスの拠点として活用されています。
2) 水俣病の経験を次世代に伝えていくために、国や関係県市では、水俣病の経験を次世代に伝えるセミナーや、「水俣市立水俣病資料館」、「新潟県立環境と人間のふれあい館−新潟水俣病資料館−」等における資料の展示及び水俣病患者から直接その体験を聞くことができる語り部の講演、熊本県の小学生が水俣市を訪問し、公害被害から環境再生へと立ち上がる水俣の姿を学ぶ「こどもエコセミナー」などを実施しています。また、(財)水俣病センター相思社は、「水俣病歴史考証館」での写真・パネル等の展示や、水俣病発生地域等を案内する「水俣まち案内・環境学習」という取組を行っています。
3) 水俣病の経験を海外に発信するために、環境省及び国立水俣病総合研究センターでは、水銀汚染問題がある国への研究者の現地派遣や、外国人研究者招聘による共同研究、国際シンボジウム・ワークショップ、開発途上国の行政担当者を対象に水俣病経験を伝えるセミナーを実施しています。また、水俣市では、平成12年度からJICA(国際協力機構)の委託を受け、「住民との協働による環境都市づくり(公害の経験から)」をテーマに、海外で環境行政に携わる外国人研修員を受け入れています。
4) 水俣市では、平成4年に「環境水俣賞」を創設し、環境保全に関する活動を育成しています。また、同年に宣言した「環境都市モデルづくり」に基づき、行政と市民が一体となり様々な取組を行っています(コラム参照)。新潟県においては、平成17年に新潟水俣病の公式確認40年を迎え、同年6月に新潟県知事が「ふるさとの環境づくり宣言」を発表し、水俣病を未来への教訓としていかし、今後の行政の運営に当たっていく決意を宣言しました。同年8月には記念事業を実施し、シンポジウムなどを開催しました。また、新潟水俣病被害者の会は、「新潟水俣環境賞」を創設し県内に関わる公害・環境問題において優れた功績を挙げた個人や団体を表彰するとともに、小・中学生を対象にした「新潟水俣環境賞作文コンクール」を実施しています。