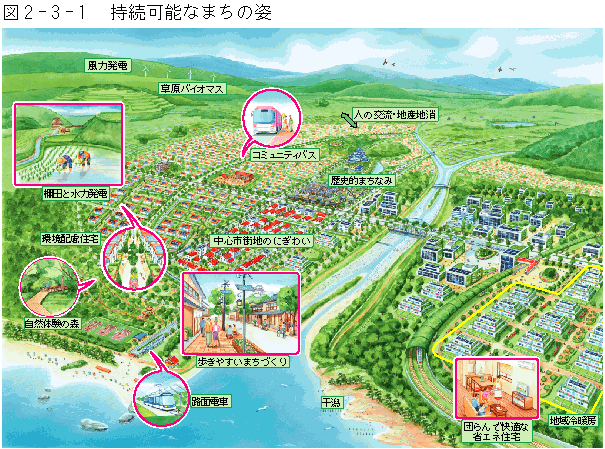
1 持続可能なまちづくり
ここまで持続可能な社会づくりに向けた取組を紹介してきましたが、ここではこのような取組を含む持続可能なまちの姿を分かりやすく示すことにします(図2-3-1)。
中心市街地では、お城や宿場町が歴史的まちなみとして保存され、ここをまちの中心として路面電車が整備されており、駅などの主要地点ごとに自転車の貸出が行われています。また、住宅地などの周辺部にはコミュニティバスが運行され、鉄道との相互の乗り継ぎもスムーズに行われるなど、高齢者でも歩いて暮らせるまちづくりが実現しています。
また、住宅地域に目を移すと、ここでは地域の木材を利用した低層の家が景観に配慮して建ち並び、太陽光発電など新エネ・省エネルギー設備が導入されています。また、住宅地域がコンパクトにまとまることにより地域冷暖房施設が配備され、効率的なエネルギー供給が行われています。室内では、家族が団らんしてコミュニケーションが取られ、また、電力消費の少ない省エネ家電が導入されるなど、省エネで快適な生活が営まれています。
このような都市部には緑があふれ、大規模な緑地が各地に整備され、河川などの水辺が人々の憩いの場となり、地域に潤いと涼しさを提供しています。また、都市内の建築物の配置は工夫され、緑や水辺からの涼しい風をうまく取り込むことで、汚染物質が拡散され、適度な熱環境が保たれています。
一方、里地里山地域に目を転じると、地域の様々な主体の創造力を活かしながら、棚田や二次林などの環境が大切に守られており、環境保全型農業や適切な森林整備・保全とともに農林産物の地産地消が行われるなど、人と自然との共生が図られています。野生鳥獣も奥山の豊かな自然環境に生息し、また自然資源としても活用がなされています。さらに、バイオマスや風力、水力など地の利を生かした地域自立型のエネルギー供給も実現しています。
このような取組の結果、都市と里地里山地域は食・住の地産地消といった物の交流だけでなく、エコツーリズムなど人の交流も増えており、地域のコミュニティも活性化しています。また、経験豊富な高齢者による若者への環境教育や、発展途上国への技術協力など、世代や海を超えた交流も盛んになっています。