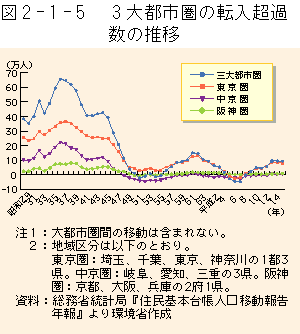
3 国土空間の見直し
(1)土地利用の変化
高度経済成長期においては、人口の増加とともに、工業化を背景に大都市圏を中心とする都市に人口が流入し、都市が発展してきました。しかし、同時に過密化や地価の高騰のほか、市街地の無秩序な外延化を招くとともに、これらに伴い環境負荷が増大しました。
今後、人口が減少するにつれて、大都市や地方都市における市街地の拡大傾向は、新規住宅の需要の減少などから終止符が打たれ、人口密度の低下と相まって大都市部での住宅・土地問題等の改善をはじめとするゆとりある生活環境の実現が可能になると考えられます(図2-1-5)。
(2)住宅ストック等の更新
高度経済成長期に大量に整備を行った住宅や社会資本ストックは、更新時期を迎え始めており、今後、大量のストックの更新が見込まれます(図2-1-6)。
また、住宅の空き家の戸数は年々増加の傾向にあります。今後、人口減少の進展により一層この傾向が加速されると考えられます。今後2015年までは人口減少となっても世帯数の増加が見込まれますが、住宅ストックの量から見て新規住宅の需要はそれほど多く見込むことはできないことから、住宅ストックについては、既存のストックの修繕・改修等による有効活用や空き家の用途転換が進められることが予想されます(図2-1-7)。
住宅、業務用ビル等の既存ストックがもたらすエネルギー消費量は相当量に上ることから、これらの既存ストックのエネルギー効率を高めることは極めて有効であると考えられます。このため、こうした大量の更新や修繕・改修等の機会をとらえて、省エネルギーのための住宅の改修や省エネ機器の導入を図ることによって、大きな効果が期待できます。
現在、省エネ法による一定規模以上の住宅の大規模改修時等の省エネ措置の届出義務づけ、公庫融資や証券化ローンの枠組みを活用した誘導、断熱資材や太陽光発電システム、高効率給湯機器等の導入促進を行い、既存住宅も含めた住宅の省エネルギー性能の向上を図っています。
(3)国土の有効活用
これまでは、急増する人口や産業振興に対応した国土空間の利用が中心であり、災害に対する脆弱な構造や環境問題、景観の悪化など生活面での質が問題となっていました。
今後、人口減少という新たな局面を迎え、住宅や社会資本ストックの大量更新等の時期が到来しつつあることを好機としてとらえ、ゆとりある生活環境と環境配慮を同時に実現した人口減少時代にふさわしい取組を行うことにより、持続可能な社会へと方向転換していくことが重要です。
パソコン、携帯電話、周辺機器等のIT関連機器の利用には電力を必要とすることから、これらによるエネルギー消費がこれからの新たな環境負荷要因になることが懸念されており、「情報通信技術(ICT)サービスの環境効率事例収集及び算定基準に関する検討成果報告書」((社)産業環境管理協会)によれば、IT利用に伴う国内の情報通信業及びインターネットユーザーからのエネルギー消費量は、2000年から2010年までに0.4%増加し、わが国全体のエネルギー消費量の約1.1%を占めると試算されています。また、パソコンや携帯電話など、大量のE-waste(電気電子機器廃棄物)を生み出します。
一方で、ITを活用した新たなビジネスモデルやライフスタイルなどにより、環境負荷を低減する効果も期待されており、上記報告書によれば、わが国全体のエネルギー消費削減効果として約3.9%を削減できると予測しています。
政府は平成18年1月に「ITを駆使した環境配慮型社会」を重点課題の一つとした「IT新改革戦略」を策定しており、今後、自宅や郊外の小さな事務所を仕事場にすることで通勤に伴うエネルギーの削減効果があるテレワークなど、官民連携してITを活用して環境負荷を低減する取組が進展することが期待されます。ただし、ITを利用する際には、環境負荷の低減を図るだけでなく、利用による環境負荷の増大も含め、その影響・効果を総合的に把握した上で、適切に利用することが重要となります。