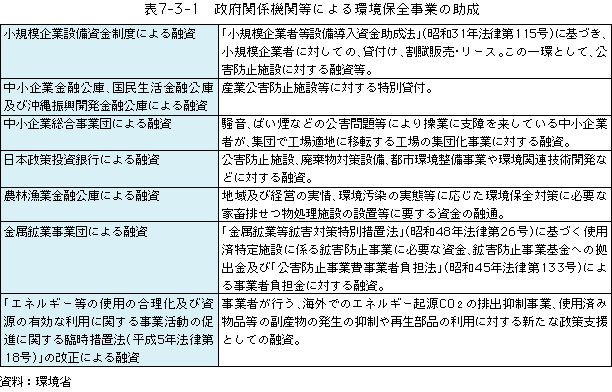
1 経済的措置
(1)経済的助成
ア 政府関係機関等の助成
政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表7-3-1のとおりでした。
イ 税制上の措置等
平成16年度税制改正において、自動車税のグリーン化及び低燃費車に係る自動車取得税の特例措置については、より排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に軽減対象を重点化するとともに適用期限を延長、廃棄物処理法に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者の事業の用に供する施設に係る事業所税の資産割の課税標準の特例措置の新設、新たな狩猟税の創設などが講じられました。
(2)経済的負担
ア 基本的考え方
環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す措置については、その具体的措置について判断するため、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、廃棄物の抑制などその適用分野に応じ、これを講じた場合の環境保全上の効果、国民経済に与える影響及び諸外国の活用事例等につき、調査・研究を進めました。諸外国の温暖化に関する税制の概要について、中央環境審議会資料をもとに整理したものは表7-3-2のとおりです。
イ 具体的な取組事例
平成16年度においては、経済的措置の検討が深められた事例として以下のようなものがあります。
(ア)政府における環境関連税の検討状況
環境省は、平成16年8月末に、環境税の創設要望を提出し、同年11月5日に、環境税の具体案を公表しました。
これを受けて、税制改正論議において活発な議論が行われ、政府税制調査会では、平成16年11月の「平成17年度の税制改革に関する答申」において、「いわゆる環境税導入の是非については、国・地方の温暖化対策全体の中での具体的な位置付けを踏まえて検討せねばならない。現時点では、他の政策手段との関連において、環境税の位置付けは必ずしも明らかでない。来年3月までに行われる「地球温暖化対策推進大綱」(平成14年3月)の見直し作業を通じ、京都議定書の目標達成を念頭に、環境税の果たすべき役割が具体的かつ定量的に検討されることが必要である。環境税の役割としては、本来、価格インセンティブを通じた排出抑制効果を重視すべきであろう。他方、追加的な温暖化対策の財源確保により重点をおいて環境税を活用することについては、既存の温暖化対策予算との関係、税収の使途を特定することの是非を慎重に検討する必要がある。環境税は、国民に広く負担を求めることになるため、その導入を検討する際には、国民の理解と協力が不可欠である。国民経済や産業の国際競争力に与える影響、既存のエネルギー関係諸税との関係、その他税制全体の中での位置付けなど、多岐にわたる検討課題がある。今後、温暖化対策全体の議論の進展を踏まえ、環境税に関する多くの論点をできる限り早急に検討せねばならない。」と答申しました。
平成15年12月に設置された中央環境審議会施策総合企画小委員会は、温暖化対策税制とそれに関連する施策について、16年8月に中間取りまとめを公表し、「温暖化対策税制は有力な追加的施策である」としました。また、16年12月27日には、これまでの議論を整理した「温暖化対策税制とこれに関連する施策に関する論点についての取りまとめ」を公表しました。
さらに平成17年3月11日には、中央環境審議会は、「地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しを踏まえた新たな地球温暖化対策の方向性について(第2次答申)」を答申しました。京都議定書の目標達成のためには、対策を導入するインセンティブを付与する経済的手法を重視すべきであり、とりわけ環境税は、その価格インセンティブ効果により省エネ機器の導入等を促すほか、幅広く国民に対しライフスタイルやワークスタイルの変革を促す強いメッセージとなるもの、とされました。さらに、京都議定書の目標を達成するために必要な対策の実行を確保するためには、追加的財源を安定的に確保する仕組みが必要であり、その仕組みとしては、二酸化炭素の排出又は化石燃料の消費に対して負担を求める税財源が適当であるとされました。とりわけ、排出量・消費量に応じて公平に負担を求める環境税は早急に検討する必要がある、とされました。
また、平成17年3月14日に、産業構造審議会環境部会地球環境小委員会は、「今後の地球温暖化対策について京都議定書目標達成計画の策定に向けたとりまとめ」を行いました。とりまとめでは、「化石燃料に課税することによりエネルギー起源CO2の排出量の抑制・削減を企図する、いわゆる環境税については、価格弾力性を通じて各主体の温室効果ガス排出の抑制を図ることが重要であり、京都議定書の約束達成を図る観点から、環境税を手法の1つとして検討すべきとの指摘があった。他方、環境税は、エネルギー消費の増大が著しい民生・運輸部門の対策としての効果が不明確であること、米国や中国等と厳しい競争関係にある我が国産業に対して既存のエネルギー諸税に加えて新たに税負担が増大すれば、国際競争力に悪影響を及ぼすのみならず生産の海外移転を促進し地球規模の温暖化防止に逆行する恐れがあること、温暖化対策のための予算は既存の枠組みの中で十分に確保されておりその有効活用が先決であることなどから、その導入には反対であるとの指摘もなされた。経済的手法としての環境税の取扱いに関しては、こうした意見を十分踏まえるとともに、他の手法との比較や国際的な動向、これまでの地球温暖化対策の実績と評価などを十分考慮しつつ、総合的かつ慎重に検討することが重要である」とされました。
京都議定書目標達成計画では、環境税については、国民に広く負担を求めることになるため、関係審議会をはじめとする各方面における地球温暖化対策に係る様々な政策的手法の検討に留意しつつ、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、諸外国における取組の現状などを踏まえて、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進めていくべき課題であるとされています。
(イ)地方公共団体における環境関連税導入の動き
地方公共団体において、環境関連税の導入の検討が進められています。
例えば、産業廃棄物の排出量又は処分量を課税標準とする税について、これまで12の地方公共団体で条例が制定され施行されました。税収は、主に産業廃棄物の発生抑制、再生、減量、その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てられています。
また、高知県や岡山県など8つの県では、森林に関する税金が施行されています。例えば、高知県では、県民税均等割の額に500円を加算し、その税収を森林整備等に充てるために森林環境保全基金を条例により創設するなど、実質的に目的税の性格を持たせたものとなっています。